育児休業(育休)の取得を希望しても、企業側から拒否されるケースは少なくありません。しかし、育休は法律で認められた権利であり、取得を拒否されることは違法となる場合があります。そのため、育休についての知識を深め、会社の誤った認識を指摘することが重要です。
本記事では、育休の取得を拒否された場合の対処法を紹介します。育休の取得を拒否された事例や違法性についても詳しく解説していますので、参考にしてください。
・育休取得を拒否された場合、対象となる労働者からの申請に対し、企業か拒否するのは違法
・企業が育休取得を拒否できるケースは、育休の取得対象者ではない、有期契約で子が1歳6ヶ月になる前に契約終了が確定しているなどの場合のみ
・育休取得を拒否された場合の対処法・相談先は、社内の相談窓口、雇用環境・均等部(室)、労働組合、弁護士など
目次
育休取得を拒否された場合は違法?取得条件をおさらい
育児休業は、育児と仕事を両立するために設けられた制度です。しかし、実際には人手不足だから、正社員ではないからなどの理由で、育休取得を拒否されるケースも見受けられます。こうした対応が果たして法的に認められるのか、取得条件を見ていきましょう。
- 育休とはどのような制度?取得条件は?
- 育休の取得を拒否された場合は違反!罰則は?
育休とはどのような制度?取得条件は?
育児休業(育休)は、原則1歳未満の子どもを育てる従業員が、一定期間会社を休んで育児に専念できる制度です。これは育児・介護休業法に基づいており、男女問わず取得が認められています。育休の取得を希望するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 原則として1歳未満の子を養育していること
- 子どもが1歳半になるまでに雇用契約が満了しない見込みであること(期間の定めのある社員の場合)
申請期限にも注意が必要です。通常、育休開始希望日の1か月前までに申し出なければなりません。このような要件を満たしている場合、育休を取得できます。
育休の取得を拒否された場合は違反!罰則は?
育児・介護休業法では、対象となる労働者からの申請に対し、企業は育休を認めなければならないと明記されています。これに反して取得を妨害する行為は、違法です。
違反が認められた場合、厚生労働省や労働局が企業に対し、是正指導や勧告を行います。それでも改善されない場合は、企業名の公表や6カ月以下の懲役または、30万円以下の罰金が科されることもあります。場合によっては損害賠償請求の対象にもなり得ます。
育休は労働者の当然の権利であり、取得条件さえ満たしていれば企業は申し出を拒否できないことを覚えておきましょう。
育休取得を拒否できる場合もある
育児休業は基本的にすべての労働者に認められた制度ですが、状況によっては会社側が取得を認めないケースも存在します。これは企業の都合による拒否ではなく、法律上「対象外」とされている場合に限られます。育休を希望するすべての人が取得できるわけではない点を、あらかじめ理解しておくことが大切です。
- 育休の取得対象者ではない場合
- 有期契約で子が1歳6ヶ月になる前に契約終了が確定している場合
- 労使協定で取得を拒否する定めがある場合
- 育休取得を拒否できると勘違いしている会社もある
育休の取得対象者ではない場合
育休はすべての労働者が無条件で取得できるわけではありません。法律上、育児休業の取得対象となるのは「1歳未満の子どもを養育する労働者」であり、配偶者が専業主婦(夫)であっても、一定の条件を満たせば取得は可能です。
しかし、すでに育児を担っている配偶者が専業で、かつ育児に専念している場合などは、育休の必要性が認められないことがあります。また、日雇い労働者や試用期間中の労働者など、法の想定する対象外である場合も取得はできません。
このような場合、企業が育休の取得を認めないのは違法ではありません。
有期契約で子が1歳6ヶ月になる前に契約終了が確定している場合
契約社員やパートタイムなど、期間の定めがある雇用形態の場合、育休の取得には追加の条件が課されます。とくに重要なのが、育休期間中に雇用契約が継続していることです。具体的には、子どもが1歳6ヶ月になる日までに契約が満了することが明らかな場合、育休の取得は認められません。
例えば、子どもが生後6か月のときに契約が残り半年しかない場合などが該当します。これは、育児休業の趣旨が復職を前提とした一時的な休業であるためです。育休後の復帰が見込めない場合には、企業側が申請を拒否しても違法にはなりません。
労使協定で取得を拒否する定めがある場合
企業によっては、労使協定により一部の労働者を育休の対象から除外している場合があります。これは育児・介護休業法で定められた例外措置で、特定の条件に当てはまる労働者について、事前に労使間で取り決めがあれば育休取得を拒否することが可能です。
例えば、入社1年未満の社員や、週の所定労働日数が2日以下の短時間労働者などが除外対象となります。ただし、こうした取り決めが有効となるには、あらかじめ労働組合や過半数代表者との協議を経た労使協定が存在している必要があります。
企業側の判断のみで適用することは認められていません。
育休取得を拒否できると勘違いしている会社もある
一部の企業では、法令の内容を正しく理解していないまま、育休の取得を拒否するケースがあります。例えば以下の理由が挙げられます。
- 「忙しいから育休は取れない」→社内状況に関係なく取得できる
- 「育休を取得した前例がなく制度が整っていない」→社内制度の有無に関係なく取得できる
- 「男性は育休を取る必要がない」→男女関係なく取得できる
- 「育休を取得できるのは大企業だけ」→会社規模に関係なく取得できる
- 「パート・アルバイトは取得できない」→雇用形態に関係なく取得できる
- 「すでに奥さんが育休しているから取得できない」→夫婦のどちらも取得可能(ただし、同時に取得する場合は子が1歳2ヶ月までの期間)
このような場合、企業側に説明を求めることや、社内の人事担当者・労務部門に相談することが有効です。労働基準監督署や厚生労働省の窓口に問い合わせることで、正しい情報を得られる場合もあります。誤解による拒否を受けた際は、自分の権利を守るために冷静かつ確実に対応しましょう。
育休取得を拒否された場合の対処法・相談先
育休の取得を申請したにもかかわらず、会社から拒否された場合は、まず落ち着いて対処法を確認しましょう。一人で悩まず、しかるべき窓口に相談することで、状況の改善や法的サポートを受けられる可能性があります。
- 会社の相談窓口に相談する
- 都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」に相談する
- 労働基準監督署に相談する
- 労働組合に相談する
- 弁護士に相談する
会社の相談窓口に相談する
まずは社内の相談窓口に状況を伝えることが第一歩です。多くの企業では、人事部や労務担当者、コンプライアンス窓口が設けられています。担当者に対して、育児・介護休業法に基づき育休取得が認められていることを伝え、自身の状況が法の要件を満たしていることを冷静に説明しましょう。
企業によっては、上司や現場責任者が制度を正しく理解していないケースもあります。正規の相談ルートを通すことで、誤解が解けて対応が改善される場合もあります。まずは社内で解決を図ることが基本です。
社内の相談窓口に相談しても問題が解決しない場合は、次に紹介する相談窓口を利用してください。
都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」に相談する
育休取得を会社から拒否されたときは、都道府県労働局に設置されている「雇用環境・均等部(室)」に相談するのが有効です。雇用環境・均等部(室)は厚生労働省の下部機関で、育児・介護休業法を含む雇用均等関連の問題を扱う専門部署となっています。
申請の拒否や嫌がらせ、育休を理由とした不当な評価・降格なども相談の対象です。相談は無料で、匿名でも可能なため、会社に知られずに助言を受けたい人にも適しています。具体的な相談内容を整理し、育休申請書や就業規則などの資料を手元に用意しておくと、より適切なアドバイスを得られます。
相談内容や企業の対応によって、労働局から企業に対して指導や勧告が行われることも少なくありません。また、企業の対応が改善されない場合は、企業名の公表といった行政処分につながる可能性もあるため、抑止力としても効果があります。
自分の権利を守るために、積極的に活用したい制度です。
労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は、労働条件や職場の安全衛生などを監督する機関で、労働基準法に関するさまざまな相談に対応しています。育児休業そのものは、どちらかといえば労働局の「雇用環境・均等部(室)」が管轄していますが、労働基準法に関連する問題が発生している場合は労基署に相談しても構いません。
例えば、育休申請を理由に減給されたり、解雇されたりしたなど、不当な扱いを受けた場合は、明らかに労働基準法違反です。また、育休に関する会社の制度や書面での説明義務が果たされていない場合も、対応を求められます。
労基署への相談は無料で、匿名での問い合わせも可能です。事前に状況を整理し、どのような不利益を受けたのか具体的に説明できるよう準備しましょう。公的な立場から企業に是正勧告を行ってくれるため、会社に対する強いプレッシャーにもなります。
ただし、労働基準監督署への相談は多いため、相談内容によっては動いてもらえないことも少なくありません。そのため、労働基準監督署に相談する前に雇用環境・均等部(室)へ相談することをおすすめします。
労働組合に相談する
勤務先に労働組合がある場合、育休を拒否されたときにはまず相談してみましょう。労働組合は、労働者の権利を守るために会社と交渉を行う立場にあり、個人では難しい要求や改善を企業側に伝える強力な手段となります。
育休取得の拒否が違法であると判断されれば、組合が企業に対して説明や是正を求めることも可能です。また、職場に労働組合が存在しない場合でも、地域ユニオンや個人加盟型の労働組合に相談できます。
これらの団体は、業種や雇用形態に関係なく労働者の相談を受け付けており、法的な知識や交渉ノウハウにも精通しています。組合に加入することで、団体交渉という形で正式に企業へ申し入れを行うことができ、育休問題に限らず職場の待遇全般に関する支援も受けられます。
労働組合に相談できる内容については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説
弁護士に相談する
会社の対応がどうしても改善されない場合や、不利益な取り扱いがエスカレートしている場合には、弁護士への相談を検討しましょう。とくに、育休申請を理由とした降格、減給、解雇といった処遇は明確な違法行為にあたる可能性が高いので、法的措置をとることで状況が改善されます。
弁護士は労働法や育児・介護休業法に精通しており、企業との交渉や訴訟対応も含めて専門的なサポートを提供してくれます。また、弁護士を通じて内容証明を送付することで、企業に対して法的リスクを認識させ、対応を見直させることも可能です。
費用が心配な場合は、法テラスの無料相談制度や、初回相談無料の法律事務所を活用する手もあります。自分の権利を守るためには、専門家の力を借りることをためらう必要はありません。感情的にならず、証拠を整理して冷静に行動することが大切です。
育休取得を拒否された事例!相談事例を紹介
雇用環境・均等部(室)では、会社に育休の取得を拒否されたといった相談が多く寄せられています。雇用環境・均等部(室)に相談すれば、どのような対応を取ってもらえるのか、事例をもとに見ていきましょう。
- 育休取得を申し出たが男性であるため拒否された事例
- 育休取得を拒否されたうえに労働局の勧告に従わなかった事例
- 派遣労働者が育休を申請すると退職を促された事例
育休取得を申し出たが男性であるため拒否された事例
まずは、育休取得を申し出たが男性であることを理由に拒否された事例を紹介します。
【相談内容】
男性労働者が、子どもが1歳になるまでの間に育児休業を取得したいと申し出たところ、会社から拒否されました。その理由は以下の3つです。
- 育児休業は女性のための制度なので、男性は対象ではない
- 社内で休業を許可する決裁が通らないため認められない
- 就業規則に育児休業に関する記載がないから対応できない
相談者はこの対応に納得できず、労働局の雇用均等室に助けを求めました。
【雇用均等室の対応】
労働局の最初の対応としては、育児・介護休業法に基づき会社への事情聴衆です。会社側は、小規模事業者であるため長期の休業者を出すのは難しい、相談者が担当する業務は専門性が高く、代替要員を確保できないと説明しました。
これに対して雇用均等室は、育児休業は男性も女性も等しく取得できる法的権利であることを会社に伝えました。あわせて、企業の規模や社内規定の有無を理由に、法律で認められた申請を拒否することはできないと明確に指導したのです。
【会社の対応等】
雇用均等室の指導を受けて、会社はこれまでの対応を見直しました。最終的に、相談者の育児休業申請を受け入れ、労働者は希望通りに育児休業を取得できたのです。
育休取得を拒否されたうえに労働局の勧告に従わなかった事例
次は、育休取得を拒否されたうえに労働局の勧告に従わなかった事例です。
【相談内容】
正社員として11年勤務していた女性が、産休後に育児休業の取得を申し出たところ、会社から育休は取らせられないと断られました。さらに、産後休業終了直前に「子育てで休みがちになるだろうから」として、パートへの身分変更を提案されたのです。
女性が原職での正社員復帰を希望し、改めて育休取得を申し出たところ、それも拒否され、「パートに応じないなら解雇する」と告げられました。
【雇用均等室の対応】
労働局が報告を求めたところ、パート変更は本人の了承済、解雇を告げた事実はないと会社が主張し、育休については小規模事業であり取得は難しいと回答しました。これに対し雇用均等室は、育休は会社が拒否できない権利であることや、パートへの変更が労働者の真意に基づかない場合は違法と指導しましたが、会社は全く応じません。
【会社の対応等】
雇用均等室が是正勧告を出しましたが、会社は文書が来ても構わないと拒否したのです。最終的に、正社員からパートへの強制的な変更は不利益取り扱いにあたるとして勧告が出されましたが、会社はパート復職のみを認めました。
相談者は行政対応に限界を感じ、損害賠償を求めて訴訟に踏み切りました。
派遣労働者が育休を申請すると退職を促された事例
最後は、派遣労働者が育休を申請すると退職を促された事例です。
【相談内容】
相談者は、数年間同じ派遣元で働いていた派遣労働者です。妊娠が判明したため、産前・産後休業および育児休業を取得したいと申し出ましたが、派遣元からは派遣労働者は育児休業を取得できないと断られ、さらに退職を勧められました。
相談者は納得できず、雇用環境・均等室に相談し、紛争解決援助の申し立てを行ったのです。
【雇用均等室の対応】
雇用均等室は、派遣労働者であることを理由に産前・産後休業や育児休業の取得を拒否し、退職を勧めることは不利益取扱いに該当する旨を派遣元に助言しました。また、相談者が適切に休業を取得できるように、派遣元に対して指導を行いました。
【会社の対応等】
派遣元は雇用均等室の指導を受け入れ、不利益取扱いを改めたのです。これにより、相談者は産前・産後休業および育児休業を問題なく取得できることとなり、紛争解決援助は終了しました。
育休取得を拒否する会社は取得後にも注意
育児休業を取得できたからといって安心は禁物です。育休取得を拒否するような会社は、休業後に不当な扱いをする可能性があります。例えば以下のような場合は違法です。
- 育休取得後に配置転換される場合がある
- 育休取得後に短時間勤務制度が利用できない場合がある
- 育休取得後に身分変更を求められる場合がある
- 育休取得後に仕事を与えてもらえない場合がある
- 育休取得後に退職勧奨される場合がある
育休取得後にトラブルが発生した場合は、早めに相談機関へ連絡しましょう。
育休取得後に配置転換される場合がある
育休明けに復職した際、これまでと異なる部署に異動を命じられるケースがあります。会社側は人手不足や業務上の都合といった理由を挙げることが多いですが、原則として育休からの復帰後は、休業前と同じ職務・同じ部署への復帰が前提です。
育児・介護休業法でも原職復帰が基本とされており、業務内容や勤務地が大きく変わる場合には、本人の同意や合理的な理由が求められます。とくに、本人の能力やキャリアを活かせない部署に一方的に異動させられるようなケースでは、不利益取り扱いとして法に触れる可能性が高いです。
嫌がらせされたと感じた場合は、会社に異議を申し立てたり、労働局に連絡するなど、早めの対応が重要です。復職前に異動を打診された場合でも、その理由や必要性をきちんと確認しましょう。
育休取得後に短時間勤務制度が利用できない場合がある
子どもが3歳になるまでは、育児・介護休業法により短時間勤務制度の利用が認められています。しかし、育休から復帰した後に育休を取得したから、業務が忙しいからといった理由で、制度の利用を拒否されることがあります。
企業には制度を整備する義務があり、合理的な理由がない限り、短時間勤務の申請を断ることは違法です。また、制度があっても利用しづらい空気がある場合や、申請したことによって不利益を被るようなことがあれば、それも違法に当たる可能性が高いです。
時短勤務を希望する際は、事前に就業規則や社内制度を確認し、申請内容を文書で残すことをおすすめします。会社側が非協力的な姿勢を示す場合は、雇用均等室や労働組合など、外部の第三者機関に相談することで改善につながるでしょう。
育休取得後に身分変更を求められる場合がある
育休から復帰する際に、会社から正社員ではなくパートや契約社員になってほしいと言われるケースがあります。しかしこれは、育児休業を取得したことを理由にした不利益な取扱いであり、育児・介護休業法に違反する可能性が高い行為です。
中には会社の都合でフルタイムは難しい、として正社員から外そうとするケースもありますが、労働者の同意がない一方的な契約変更は認められません。また、表向きは本人の希望とされていても、実際は半ば強制されたような状況であれば、真意に基づく合意とはいえません。
育休から復帰する労働者には、もとの労働条件で職場に戻る権利があります。仮に身分変更を強く求められた場合は、記録を残しておくとともに、雇用均等室や労働基準監督署などへ相談しましょう。
育休取得後に仕事を与えてもらえない場合がある
育休から職場に戻ったにもかかわらず、明らかに業務量が少ない、責任ある仕事を任されないなど、仕事を与えてもらえない状況に置かれる人もいます。これはいわゆる「職場内での干し上げ」とも呼ばれ、育児休業を取得したことに対する報復的な扱いの一つです。
本人としては復職の意志もあり、働く準備も整えているのに、仕事をさせないというのは大きな精神的負担になりますし、キャリアにも悪影響です。会社側に意図的な冷遇や嫌がらせがある場合、育児・介護休業法だけでなく、労働契約法やパワハラ防止法にも違反する恐れがあります。
業務の配分について疑問がある場合は、まずは上司や人事部に理由を確認し、改善が見られない場合は外部機関に相談しましょう。仕事を与えてもらえない場合は、以下の対処法を参考にしてください。
関連記事:仕事を与えられないのはパワハラにあたる?7つの対処法を徹底解説
育休取得後に退職勧奨される場合がある
育休を終えて復職しようとした際に、このまま辞めたほうがいい、続けるのは厳しいのではといった形で退職を促されるケースがあります。これは退職勧奨と呼ばれますが、強制ではないとはいえ、事実上の圧力となる場合も多く、法的な問題に発展することもあります。
とくに、育休を理由に退職を勧められた場合は、育児・介護休業法が禁じている不利益取扱いに該当する行為です。会社側としては本人の意思として処理したい思惑がありますが、背景に圧力があったと判断されれば、無効になる可能性があります。
育児と仕事の両立が難しいという印象を与えないように、復職後の働き方については事前にプランを立てておくと安心です。もし納得のいかない退職勧奨を受けた場合には、記録を残しておき、早い段階で専門機関に相談することが重要です。退職勧奨されたときの対処法は、以下の参考にしてください。
関連記事:退職勧奨されたらどうするべき?適切な対応方法と退職勧奨のよくある手口を解説します
育休取得を拒否された場合に関するよくある質問
育休取得を拒否された場合に関するよくある質問について紹介します。
- 育休取得を拒否できる正当な理由は?
- 育休取得後に延長できるの?
- 会社に入社1年未満は育休取得できないと拒否された場合は?
- 育休取得できない場合は退職すべき?
育休取得を拒否できる正当な理由は?
育休取得を拒否できる正当な理由は、主に希望者が取得条件を満たしていない場合です。例えば、入社してから1年未満の従業員や、有期契約で子どもが1歳6ヶ月になる前に契約終了が確定している場合などです。また、労使協定で特定の労働者を対象外とする定めがある場合も、取得が制限されることがあります。
ただし、これらは法律上の要件に該当する必要があり、企業側の独断で判断できるものではありません。国が定めた条件を満たしている場合は、性別や雇用形態に関係なく取得できます。
育休取得後に延長できるの?
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、一定の条件を満たせば最長で2歳まで延長可能です。延長が認められるのは、保育所に入所できない場合や、育児を行う予定だった配偶者が病気などで育児できなくなった場合などが該当します。
延長を希望する場合は、就業規則や会社の手続きに従って申請することが必要です。育休延長の申請は、子どもが1歳になる前に行う必要があるため、保育所の申し込み状況などを踏まえて、早めにスケジュールを立てておくと安心です。
なお、育休の延長も労働者の権利として法的に認められており、正当な理由があれば企業が拒否することは許されません。
会社に入社1年未満は育休取得できないと拒否された場合は?
育児休業の取得要件として、原則として同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることが必要です。このため、入社して1年未満の場合は、会社が育休を拒否できる場合もあります。ただし、これはあくまで例外的なケースであり、将来的に1年以上の雇用が見込まれる場合には、企業の判断で取得を認めることも可能です。
なお、1年未満でも会社が認めれば取得は可能なため、希望がある場合は会社に相談してみましょう。拒否された場合には、その理由や対応の記録を残し、必要に応じて外部機関への相談も視野に入れてください。
育休取得できない場合は退職すべき?
育児休業を取得できないからといって、すぐに退職を選ぶ必要はありません。まずは、その取得不可の理由が法律に基づいた正当なものであるかを確認しましょう。例えば、会社が法的な要件を満たしていないまま取得を拒否している場合、それは違法となる可能性があります。
このようなケースでは、会社に再度説明を求めるか、雇用均等室や労働局に相談することで解決できます。それでも解決しない場合に限って、転職などを検討すると良いでしょう。
まとめ
育休取得を拒否されたときの対処法について紹介しました。国が指定している条件を満たしている場合は、原則会社が育休取得を拒否できません。そのため、会社が拒否した場合はほとんどのケースが違法であると思っておきましょう。
会社の認識不足などが原因で取得できないケースもあるので、雇用環境・均等部(室)に相談して会社に指導してもらうのが好ましいです。中には頑なに取得を認めない会社もありますが、そのような会社はブラック企業である可能性が高いため、退職を検討しましょう。
無駄なトラブルを避けて退職するためには、退職代行サービスがおすすめです。退職に関する悩みや不安を抱えている人は、退職代行ほっとラインへご相談ください。




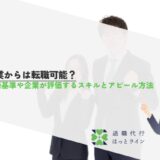
コメントを残す