仕事で成果を出していると、上司から昇進や昇格の打診を受けることがあります。しかし「今は責任の重いポジションに就きたくない」「ライフスタイルを重視したい」など、さまざまな理由から昇進を断りたいと考える方もいるでしょう。
とはいえ、断り方を間違えると、評価が下がったり、今後のキャリアに悪影響が出るリスクもあります。本記事では、昇進や昇格を拒否したいときに評価を下げない上手な伝え方と、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
・昇進(昇格)を拒否したいと思っている人は、約82~67%
・昇進を拒否したい理由は、ワークライフバランスが崩れるのが怖い、報酬や待遇が見合わない、ワークライフバランスが崩れるなど
・昇進を拒否するときに評価を下げない伝え方は、伝える前に自分の気持ちを整理する、基本マナーと心構えを守るなど
・昇進を拒否したことで考えられる悪影響は、評価が下がる、人間関係が悪化する、キャリアパスが限定される
目次
昇進(昇格)したいと思っている人は約18~33%
内閣府男女共同参画局が実施した「令和5年度 男女の健康意識に関する調査報告書」によると、昇進(昇格)したいと答えた人の割合は、「男:33%、女:18%」です。年齢別でみると、以下の通りです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20歳 | 51.2% | 28.1% |
| 30歳 | 43.5% | 21.5% |
| 40歳 | 34.6% | 18.9% |
| 50歳 | 25.9% | 14.6% |
| 60歳 | 14.4% | 6.9% |
参考元:内閣府男女共同参画局|令和5年度 男女の健康意識に関する調査報告書
男女ともに、年齢を重ねるごとに昇進したいと思っている人は少なくなります。とくに女性は年齢が低くても昇進したいと思っている人は少ないです。この結果を見てわかる通り、昇進したいと思っている人は少なく、昇進を拒否したいと思うのは間違ったことではありません。
昇進を望まない人が増えている背景
昇進を希望しない人が増えている背景には、現代特有の社会変化があります。ひとつは、役職に就くことで仕事量や責任が格段に増えるため、ワークライフバランスが崩れるリスクを避けたいと考える人が多くなっている点です。
また、昇進による給与アップが期待できないケースもあります。管理職手当がわずかであったり、残業代が支給されなくなったりするなど、実質的な収入減につながることも少なくありません。
このような時代背景から、あえて昇進を選ばないキャリア観が一般的になりつつあります。そのため、昇進を断ることは、必ずしもネガティブな選択ではないのです。内閣府が行った同調査では、管理職として働きたいと思える環境や要素は何か、という質問に対して以下のような回答が多くなっています。
| 管理職として働きたいと思える環境や要素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 管理職でもきちんと休暇がとれること | 27.6% | 26.2% |
| 管理職でも残業や長時間勤務が極力ないような体制・配慮 | 20.1% | 19.1% |
| 管理職の残業や長時間勤務にも給与反映があること | 20.3% | 17.4% |
| フレックスタイムなど始業・終業時間が柔軟であること | 16.6% | 20.4% |
| 管理職は家庭やプライベートより仕事を優先すべきといった空気感がないこと | 17.4% | 19.1% |
昇進を拒否しても問題ない
昇進を拒否しても、適切に対応すれば大きな問題にはなりません。むしろ、無理に昇進して心身に負担をかけるよりも、自分の意思を尊重したほうが長期的にはプラスに働きます。
ポイントは、上司や会社に対して敬意を持った伝え方をすることです。今はスキルアップに集中したい、家庭との両立を重視したいなど、ポジティブな理由を伝えると、理解を得やすくなります。また、昇進を断る代わりに、現職でどのような貢献ができるかを具体的に伝えると、評価への悪影響を防ぎやすくなります。
昇進を拒否することは、自分自身のキャリアを主体的に選ぶ行動です。堂々と自分の考えを伝え、納得できる働き方を目指しましょう。
昇進を拒否したい理由は?
昇進や昇格は、多くの人にとってキャリアの成功と捉えられています。しかし、すべての人が喜んで受け入れるわけではありません。責任の重さ、ワークライフバランス、今の仕事への愛着などから、昇進を拒否したいと考える人も多くいます。
- 責任・プレッシャーが増えることへの不安
- ワークライフバランスが崩れるのが怖い
- 現在の仕事が好き・やりがいを感じている
- 報酬や待遇が見合わないと感じる
- 社内の人間関係や評価への不安
- 昇進後の仕事内容に魅力を感じない
- キャリアの方向性が異なる
責任・プレッシャーが増えることへの不安
昇進すると、これまで以上に大きな責任が伴います。部下の育成、チーム全体の成果管理、問題発生時の対応など、業務量だけでなく精神的な負荷も格段に上がるでしょう。例えば、プロジェクトの失敗が自分一人の評価に直結したり、部下のトラブル対応で夜間や休日にも呼び出される可能性があります。
これまで個人の成果を重視して働いてきた人にとって、チーム全体を背負うプレッシャーは非常に大きなものです。また、社内だけでなく取引先や上層部への対応も求められるため、精神的な余裕がなくなり、プライベートにまで悪影響を及ぼすリスクも高まります。
このように、昇進には単なる役職の変化以上に、日常生活を一変させるだけのインパクトがあるため、慎重に考えたいと感じるのは自然なことです。仕事の責任が重いときの対処法は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:仕事の責任が重くて耐えられないときの対処法!責任を持つメリットも紹介
ワークライフバランスが崩れるのが怖い
昇進によって仕事量が増えると、今まで保ってきたワークライフバランスが崩れる懸念があります。管理職になると、通常業務に加えて部下指導、チームマネジメント、業績報告などの業務が追加され、業務時間が長くなる傾向にあります。
とくに大企業や成果主義を重視する企業では、長時間労働が暗黙の了解となっている場合もあり、精神的にも肉体的にも負担が増大するでしょう。仕事に追われるあまり、健康を害したり、大切な人との関係性が悪化したりするリスクも無視できません。
将来のライフプランを大切に考える人ほど、ワークライフバランスの観点から昇進を慎重に判断する傾向が強まっています。理想のワークライフバランスを実現するコツについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:人生と仕事のバランスが重要な理由!理想のワークライフバランスを実現するコツを紹介
現在の仕事が好き・やりがいを感じている
昇進によって現場から離れ、管理業務中心になることに抵抗を感じる人も少なくありません。とくに、現場で直接お客様と接する業務、技術職、クリエイティブな仕事に強いやりがいを持っている人にとっては、プレイヤーからマネージャーへの転向は大きなジレンマとなります。
例えば、営業職であれば、顧客との関係構築や直接契約を取る達成感がモチベーションだったものが、チーム全体の数字管理に変わることで充実感が薄れるかもしれません。また、日々の業務で得られる「できた」という実感が減少し、仕事へのモチベーション維持が難しくなる可能性もあります。
自分の働き方や価値観を重視するなら、今の仕事を続けることも立派なキャリア戦略です。無理に昇進するより、自分らしくいられる選択肢を選びましょう。
報酬や待遇が見合わないと感じる
昇進によって給料が上がるとはいえ、負担に見合った報酬が得られないケースも少なくありません。例えば、昇進後の役職手当が数万円程度しか増えないのに、残業代がつかなくなる、成果に対するプレッシャーが強くなる、といったデメリットを感じる場合も多いです。
とくに最近は、名ばかり管理職問題も指摘されています。責任だけ増えたのに、収入や労働条件に反映されないケースでは、モチベーションが低下するのも当然でしょう。また、会社の業績によって昇給や賞与に大きな差が出ることもあり、安定した収入が見込めないリスクも考慮すべきです。
昇進によって失うものと得られるものを冷静に比較し、自分にとってプラスとなる道を選択することが大切です。管理職の残業については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:管理職には残業代が出ないの?もらえるケースともらえないケースを解説します
社内の人間関係や評価への不安
昇進すると、これまでとは異なる立場で同僚や部下と接する必要が出てきます。これまで友人のように接していた同僚に指導や指摘をする立場になれば、ギクシャクした関係になるリスクもあります。
また、昇進したことで周囲から妬みや嫉妬を買う可能性もあり、人間関係のストレスが一気に高まるでしょう。上層部からの期待や厳しい評価にさらされる場面も増えます。昇進は必ずしも認められた証だけではなく、新たな試練の始まりでもあります。
こうした社内政治に巻き込まれるのを避けたい、これまで通りの気楽な人間関係を維持したいと考える人にとって、昇進を断る選択は非常に理にかなったものといえるでしょう。社内政治への対処法は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:社内政治に疲れてしまう人へ!勝ち抜くスキルや巻き込まれないようにする行動とは?
昇進後の仕事内容に魅力を感じない
昇進後の仕事内容が、自分にとって魅力的でない場合、キャリアに対するモチベーションを失う恐れがあります。例えば、実務から離れ、書類作成や予算管理、上層部への報告ばかりの日々になった場合、やりがいや達成感を感じにくくなります。
現場でお客様と直接やり取りすることで充実感を得ていた人や、ものづくりに没頭することに喜びを感じる人にとっては、間接業務中心の仕事は苦痛に感じるかもしれません。
また、マネジメントに向いていないと自覚している人にとっては、昇進によってむしろパフォーマンスが低下するリスクもあります。自分がどんな業務に情熱を持てるのかを見極め、仕事内容に魅力を感じないのであれば、あえて昇進を断る勇気も必要です。
キャリアの方向性が異なる
自分が目指すキャリアビジョンと、会社が用意する昇進ルートが一致しないこともあります。専門職としてスキルを磨き続けたいのに、ゼネラリストとしてのマネジメントを求められる場合、キャリアの方向性に大きなズレが生じます。
このように会社の評価軸と自分の価値観が違う場合、昇進は必ずしもメリットにはなりません。近年ではポータブルスキルを重視し、社外でも通用するスキルを高めたいと考える人も増えています。
そのため、自社内での地位向上にこだわらず、あくまで自身のキャリアを優先する人も少なくありません。昇進の話を受けたときは、その場の感情だけで決めるのではなく、将来の自分像に合致するか慎重に判断しましょう。
昇進を拒否する方法|評価を下げない伝え方
昇進の打診を受けたものの、さまざまな事情から断りたいと考える人も少なくありません。しかし、伝え方を間違えると、上司や周囲からの評価に悪影響を与えてしまう可能性もあります。昇進を拒否したいときに評価を下げず、今後の関係性を良好に保つためのポイントを解説します。
- 伝える前に自分の気持ちを整理する
- 昇進を拒否するときの基本マナーと心構え
- 評価を下げないための伝え方
- 昇進の拒否した後の関係性を良くするには?
- どうしても拒否できない場合の対処法
- 昇進を拒否するタイミングは?
- やってはいけない拒否のやり方
伝える前に自分の気持ちを整理する
昇進を断る前に、まずは自分の本音をしっかり整理しましょう。なぜ昇進を拒否したいのか、どのような働き方を望んでいるのか、できるだけ具体的に言語化することが大切です。
責任の重さに不安を感じているのか、ワークライフバランスを守りたいのか、それとも現職に強いやりがいを感じているのかなど、理由を明確にすることで、後のコミュニケーションがスムーズになります。
また、自分の気持ちを整理しておけば、感情的な発言を防ぎ、冷静かつ丁寧に断る態度を取れます。勢いだけで断ると、後悔したり、必要以上に相手を不快にさせたりするリスクもあるので注意しましょう。メモにまとめる、第三者に話してみるなど、客観的に見直す時間を作るのもおすすめです。
昇進を拒否するときの基本マナーと心構え
昇進の辞退を伝える際は、基本的なビジネスマナーを守ることが重要です。まず、直接面談の場を設けて丁寧に話すことが大切です。メールやチャットなどの文章だけで済ませると、誠意が伝わりにくく、印象が悪くなりやすくなります。
また、上司の提案に対して感謝の意をしっかり伝えることも欠かせません。「評価していただきありがとうございます」と前向きな言葉を添えることで、断る印象を和らげられます。
さらに、自分の希望を押し通すのではなく、「現時点では」や「今後のキャリアを考えたうえで」など、柔らかい表現を意識すると角が立ちません。マナーと心構えを持って丁寧に伝えることが、結果的に自分を守ることにもつながります。
評価を下げないための伝え方
昇進を拒否するときは、伝え方次第で印象が大きく変わります。ここでは、評価を下げないために使いたい具体的な例文を2つ紹介します。
【例文1】
「このたびは昇進のお話をいただき、誠にありがとうございます。非常に光栄な提案ですが、現時点では現在の業務に専念し、さらなる成果を出したいと考えております。将来的に自分自身の成長を見据えながら、改めて挑戦できるタイミングを見極めたいと考えています。
」
【例文2】
「昇進のお話をいただき、大変感謝しております。ただ、今は家庭との両立を重視した働き方を続けたいと考えております。今後も現職で全力を尽くし、チームや会社に貢献できるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
」
これらの例文に共通するポイントは、「感謝の気持ちを必ず伝えること」「前向きな理由を添えること」「今後も会社に貢献する意志をしっかり示すこと」です。
単なる断りではなく、タイミングの問題や現在の働き方とのバランスを理由にすることで、決してネガティブな印象を与えません。
また、感情的な表現を避け、冷静かつ誠実な態度で伝えることも重要です。自分のキャリアや生活を大切にしつつ、会社へのリスペクトを忘れない姿勢を見せることで、評価の低下を防げます。
昇進の拒否した後の関係性を良くするには?
昇進を断った後も、職場の人間関係を円滑に保つことは非常に重要です。まず、昇進を断ったことを引きずらず、今まで通り仕事に取り組む姿勢を見せましょう。周囲が昇進を断ったからといってやる気を失ったと誤解しないよう、これまで以上に成果を意識することが求められます。
また、上司や同僚に対して感謝の気持ちを言葉で伝える場面を増やすことも有効です。仕事の中で信頼関係を深め、ポジティブな存在感を示していけば、昇進を断ったことによる悪影響は最小限に抑えられます。継続的な努力と誠実なコミュニケーションが、今後のキャリアに必ずプラスに働きます。
どうしても拒否できない場合の対処法
どうしても昇進を断れない状況に追い込まれた場合は、受け入れる覚悟を持ちつつ、リスクを最小限に抑える方法を考えましょう。まず、無理にすべてを背負い込まず、周囲に相談する体制を作ることが大切です。
上司に対しても、自分一人で抱えきれない部分についてはサポートを仰ぐ旨を伝え、無理なく業務を進める工夫をしましょう。また、自己研鑽を続けながら、必要以上にプレッシャーを感じすぎないようメンタルケアを心がけることも重要です。
場合によっては、数年後にキャリアの方向転換を検討する選択肢も視野に入れておくとよいでしょう。
昇進を拒否するタイミングは?
昇進を拒否するなら、タイミングも重要です。理想は、正式な辞令が下る前の段階で打診されたタイミングです。この段階で理由を説明し、丁寧に辞退することで、会社側も別の人材を選びやすくなります。
一方で、打診の直後に即答するのは避け、少し時間をもらって熟考する姿勢を見せると、真剣に考えた上での決断だと伝わります。昇進のオファーが出たその日に断るのではなく、数日以内に正式な意思を伝えるのが理想的です。
やってはいけない拒否のやり方
昇進を断る際には、絶対に避けたいNG行動もあります。まず、上司に対して感情的に拒否する態度は厳禁です。そのような仕事をやりたくない、責任なんて負いたくないといった否定的な言葉を使うと、今後の評価だけでなく人間関係も壊しかねません。
また、理由をあいまいにしたまま断るのも避けましょう。納得感のない説明では、上司も本人に任せられないと感じてしまいます。さらに、陰で文句を言ったり、不満を周囲に漏らす行為も、信用を大きく損ないます。拒否するときは、誠実かつ冷静な態度を貫き、信頼を守る行動を徹底しましょう。
昇進を拒否したことで考えられる悪影響
昇進を断る選択は、個人のキャリアや働き方を守るために重要な判断です。しかし、会社側にどう受け取られるかによっては、少なからず悪影響が生じることもあります。昇進を拒否したときに考えられる主なリスクについて詳しく解説していきます。
- 評価に影響が出る可能性がある
- キャリアパスが限定されるかもしれない
- 人間関係にトラブルが生じることがある
評価に影響が出る可能性がある
昇進を断ったことで、上司や会社から成長意欲が低いと受け取られる可能性があります。会社はポジションにふさわしい人材を育て、抜擢しようと考えています。そのため、昇進を辞退する行動が、本人のやる気や貢献意欲に対する疑念につながるケースも少なくありません。
また、短期的な成果よりも長期的な成長を重視する企業文化の場合、昇進辞退はネガティブな評価になりやすいです。とくに管理職やリーダー層への期待をかけられていた場合、今後の重要プロジェクトへの起用が見送られるリスクもあります。
ただし、伝え方次第で悪影響を最小限に抑えることは十分可能です。感謝の気持ちを伝えつつ、今後も組織に貢献する姿勢をアピールすることが大切です。
キャリアパスが限定されるかもしれない
昇進を断る選択は、自らキャリアの選択肢を狭める可能性があります。多くの企業では、昇格や役職経験が将来のキャリアパスに直結しています。例えば、管理職経験がない場合、別の部署やプロジェクトのリーダー候補から外されることもあるでしょう。
また、転職市場においてもマネジメント経験が重要視される傾向があります。昇進を一度拒否した経歴が、外部から見たときにマイナス要素と捉えられる場合もあります。
とはいえ、自分にとって何を最優先するかを明確にしておけば、キャリアの軸がぶれることはありません。無理に昇進を受け入れてストレスを抱えるより、自分らしいキャリアを歩むほうが長期的にはプラスになります。
人間関係にトラブルが生じることがある
昇進を辞退したことで、周囲との人間関係に微妙な変化が生じることも少なくありません。とくに、上司や先輩が強い期待をかけていた場合、失望感を抱かれたり、距離を置かれたりする可能性があります。
また、同期や後輩からなぜチャンスを無駄にしたのかと疑問を持たれる場面もあるでしょう。場合によっては、チーム内での立場が微妙になり、業務に支障が出るリスクもゼロではありません。
人間関係のトラブルを避けるためには、昇進辞退の理由をネガティブに見せない工夫が必要です。自分の成長や組織への貢献を引き続き重視していることを丁寧に伝え、前向きなコミュニケーションを心がけましょう。
昇進を拒否してもいい?後悔しないための判断基準
昇進を拒否する選択は、キャリアにおいて重要な決断です。しかし、この判断が正しいかどうかを後悔しないためには、いくつかの基準を持っておくことが重要です。
昇進を拒否することで得られる自由と、拒否しないことで得られる成長のバランスを取るためには、どのような視点で判断すべきなのでしょうか。後悔しないための判断基準を紹介します。
- 5年後・10年後のキャリアから逆算する
- 今の自分の価値観・人生観と向き合う
- 一度受け入れてみるという選択肢もある
5年後・10年後のキャリアから逆算する
昇進を拒否するかどうかを判断する際、5年後や10年後のキャリアをイメージしてみましょう。昇進を拒否することで今後のキャリアにどう影響するのかを、長期的に考えることが重要です。
例えば、昇進を拒否した場合、今後の昇格のチャンスが少なくなる可能性が高いです。そのため、現在の役職で自分がどのような経験を積み、将来的にどのような役割に就きたいのかを考えることが、昇進を受け入れるかどうかの判断材料になります。
一方で、昇進を受け入れることで、新しい責任や仕事の幅が広がり、キャリアの成長に繋がることもあります。自分が望むキャリアの方向性を明確にし、その道に進むためにどの選択が最適かを逆算して考えましょう。
特に、キャリアの早い段階で昇進を拒否すると、長期的に見て役職経験を積む機会が減少する可能性があることを踏まえて判断することが大切です。
今の自分の価値観・人生観と向き合う
昇進を拒否する決断をする際は、自分の価値観や人生観とも向き合うことが必要です。昇進は、通常、役職に就くことで責任が増え、仕事のプレッシャーが大きくなります。その一方で、昇進を受け入れることで新たな挑戦が待っています。
この選択が、自分の人生で大切にしているものにどう影響するのかを考えてみましょう。
例えば、今の自分にとって仕事のやりがいやワークライフバランスが重要だと感じているなら、昇進を受け入れることでそのバランスが崩れることを懸念するかもしれません。
逆に、成長や新しい挑戦を求めているのであれば、昇進を受け入れることで自身のキャリアをさらに広げるチャンスが生まれるかもしれません。自分の価値観や人生観と照らし合わせて、昇進を拒否する理由が本当に自分にとって正しいものかどうかを見極めましょう。
一度受け入れてみるという選択肢もある
昇進を拒否する前に、まずは一度受け入れてみるという選択肢も考えてみましょう。昇進を辞退することで失われるチャンスがある一方、実際に昇進を経験してみることで、自分に合うかどうかがわかる場合もあります。
とくに、昇進によって新たな経験やスキルを得られる可能性があるため、後になってからもっと挑戦すればよかったと後悔することを避けられるかもしれません。
もし、昇進してみてやっぱり自分には合わなかったと感じた場合、その後で役職を返上することも選択肢の一つです。最初から拒否するのではなく、まずは経験してみて、その結果をもとに判断することも有効です。
昇進後に自分に合わなかった場合は、その経験を通して自分のキャリアの方向性が明確になり、次に進むべき道が見えてくることもあります。
まとめ
昇進を拒否する決断は慎重に行うべきですが、自分のキャリアやライフスタイルに合った選択をすることが大切です。昇進を断る際は、感情的にならず冷静に理由を説明し、評価が下がらないよう配慮しましょう。
昇進を拒否したことで不当な扱いを受ける場合は、転職を検討してください。また、退職手続きに不安を感じる場合は、退職代行ほっとラインへご相談ください。

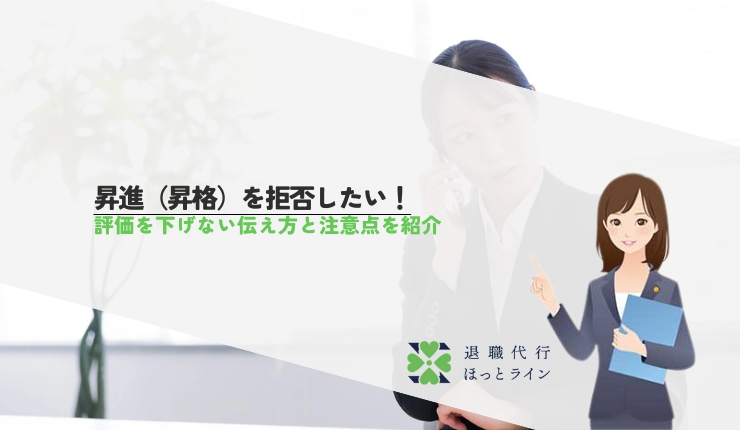


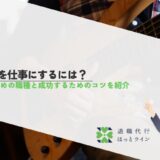
コメントを残す