「転職先が決まってから退職する」か「退職してから転職する」かどちらの順番が正しいのか疑問に思う人は多いのではないでしょうか。結論からいえば、正解はありません。自分の状況に応じて、どちらを先にすべきか決めましょう。
本記事では、「転職先が決まってから退職」か「退職してから転職」か判断するために、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。また、転職・退職で押さえておきたいポイントや、失敗しないための手順を紹介しますので、参考にしてください。
・「転職先が決まってから退職」か「退職してから転職」か順番に正解はない
・転職先が決まってから退職するメリットは、経済的な不安を回避できる、空白期間が生まれにくい、安心して退職手続きを進められる
・退職してから転職活動するメリットは、転職活動に専念できる、現職を気にせずに済む、体調やメンタルを整えられる
目次
「転職先が決まってから退職」か「退職してから転職」か順番はどっち?
冒頭でも述べましたが、どちらの選択肢にもメリットとデメリットがあるため、自分の状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。
転職先が決まってから退職するメリットは、収入が途切れないことや、次の職場が決まっている安心感が得られる点です。在職中に転職活動を進めれば、経済的な不安を抱えずに求人を比較できるため、より良い条件の企業を選びやすくなります。
退職してから転職活動をするメリットは、転職活動に集中できる点です。仕事をしながら求人を探すストレスがなくなり、面接や企業研究の時間を十分に確保できます。また、現職の引き継ぎを終えてから新しい職場に移るため、気持ちを切り替えやすいのも利点です。
結論として、経済的な余裕があり、早期に転職先が見つかる自信がある場合は退職してから転職でも問題ありません。しかし、安定した転職を目指すなら、転職先を決めてから退職するのが無難な選択です。自分の状況や優先順位を考え、最適な方法を選びましょう。
転職先が決まってから退職するメリット
転職を成功させるためには、退職のタイミングが重要です。一般的には「転職先が決まってから退職する」方法を選択する人が多いです。先に転職先を確保しておくことで、経済的な不安を避けながら計画的にキャリアを進められます。
- 経済的な不安を回避できる
- キャリアの「空白期間」が生まれにくい
- 安心して退職手続きを進められる
経済的な不安を回避できる
転職先を決めてから退職すれば、無職の期間が発生しないため、収入が途切れる心配がありません。仕事を辞めてから転職活動をすると、次の職場が決まるまでの間、貯金を切り崩しながら生活することになります。転職活動が長引けば、貯金が少ない人は経済的に不安定になってしまいます。
在職中に転職活動を進めれば、安定した収入を維持しながら求人を選ぶことが可能です。年収アップや待遇改善を狙う場合は、より良い条件の企業を探すためにも、経済的な安定が重要になります。
また、転職活動には意外と費用がかかることも考慮すべきポイントです。面接の交通費やスーツの購入費、新しい職場で必要な準備資金など、一定の出費が発生します。現職の収入を維持しながら転職活動を行えば、これらの費用も負担になりにくいでしょう。
経済的な余裕があることで、冷静に転職先を選び、納得のいく形でキャリアを築けます。そのため、特別な事情がない限り、転職先を決めてから退職するのが賢明な選択といえるでしょう。
キャリアの「空白期間」が生まれにくい
転職活動をスムーズに進めたいなら、キャリアの空白期間を最小限に抑えることが重要です。転職先を決める前に退職してしまうと、次の仕事が決まるまでの間にブランクが発生しやすくなります。3カ月~半年程度のブランクであれば問題になりませんが、半年以上の空白期間があると、転職先の企業からなぜこの期間は働いていなかったのかと疑問を持たれる可能性が高くなります。
多くの企業は、応募者の職務経歴をチェックする際、直近の勤務状況を重視しがちです。ブランクが長いと、ネガティブな印象を持たれる可能性があるので注意が必要です。とくに、即戦力を求める企業では、空白期間が長い人よりも、直近まで仕事をしていた人のほうが優先されるケースが多くなります。
在職中に転職先を決めておけば、現在の仕事を辞めるタイミングと新しい職場に入るタイミングを調整しやすく、空白期間ができません。このように、転職先を確保してから退職すれば、キャリアの空白を最小限に抑え、スムーズに次のステップへ進むことができるのです。
安心して退職手続きを進められる
転職先が決まっている状態で退職すれば、精神的なプレッシャーを軽減しながら退職手続きを進められます。退職を伝える際、上司や会社から引き止めにあうことは珍しくありません。しかし、すでに次の職場が決まっていれば、転職先が決まっているので、〇月〇日で退職しますと明確に伝えられるので、スムーズに退職できるでしょう。
転職先が決まっていれば、退職日を明確に決めやすくなります。引き継ぎのスケジュールを調整しやすくなり、会社との関係を良好に保ったまま退職できる可能性が高くなります。
このように、転職先を決めてから退職すれば、精神的な安心感を持ちながら、計画的に退職を進めることが可能です。焦らずに転職活動を進めたい人や、円満退職を希望する人にとって、最もリスクの少ない方法といえるでしょう。
転職先が決まってから退職するデメリット
転職先を決めてから退職することには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。在職中の転職活動はスケジュール調整が難しく、仕事との両立に苦労するケースが多いです。また、転職活動をしていることが職場にバレてしまうリスクもあります。
- スケジュール管理が難しい
- 会社に転職活動がバレるリスクがある
スケジュール管理が難しい
在職中に転職活動を進める場合、仕事と面接のスケジュール調整が大きな課題となります。通常の業務をこなしながら求人を探し、企業研究を行い、履歴書・職務経歴書を作成するのは想像以上に大変です。書類選考を通過した場合、面接の日程調整が必要になりますが、平日の勤務時間内に設定されることが多いため、対応が難しくなることもあるでしょう。
多くの転職希望者は、面接のために体調不良を装って休む、有給休暇を利用するといった方法で対応しています。しかし、急に休みを取ることが続くと、職場の上司や同僚に不審がられる可能性があるため注意が必要です。
また、転職活動の進捗によっては、複数の企業と同時に選考を進めることもあるため、スケジュール管理がより複雑になります。例えば、第一志望の企業の最終面接がまだなのに、他社から内定をもらったといった状況になった場合、どのように対応するか慎重に判断しなければなりません。
会社に転職活動がバレるリスクがある
在職中に転職活動をする場合、慎重に進めないと現在の職場にバレてしまうリスクがあります。転職を考えていることが会社に知られると、上司や同僚からの態度が変わったり、不当な扱いを受けたりする可能性があるため、注意が必要です。
転職活動していることを誰にも話してはいけません。仲の良い同僚であっても、同僚がうっかり他の人に話してしまったり、同僚と話している内容を他の人に聞かれてしまったりする恐れがあります。
このように、転職先を決めてから退職することにはメリットが多い一方で、会社にバレないように細心の注意を払う必要があります。転職活動を成功させるためには、適切なスケジュール管理と情報の取り扱いに気をつけることが重要です。
「転職から退職」の順番におすすめな人は?
「転職から退職」の順番におすすめな人は、以下の通りです。
- 経済的な安定を重視する人
- ブランク期間を作りたくない人
- 転職活動に十分な時間を確保できる人
- 今の職場環境が耐えられる人
- 退職を切り出しにくい人
転職先を決めてから退職するのがおすすめなのは、経済的な安定を重視する人や、キャリアの空白期間を作りたくない人です。在職中に次の職場を決めておけば、収入が途切れる心配がなく、安心して転職活動を進められます。
また、強く引き止められたり、圧力をかけられたりする職場では、転職先を先に決めておくのがおすすめです。転職先が決まっていれば、会社も無理に引き留めにくくなります。人間関係や労働環境に大きな問題がない場合は、無理に退職せず、慎重に転職活動を進めたほうがよいでしょう。
退職してから転職活動するメリット
退職してから転職活動する場合、仕事と転職活動の両立による負担がなくなり、余裕を持って転職活動に取り組めるのが大きなメリットです。また、職場の人間関係を気にせず自由に動けるため、より自分に合った企業を見極められます。
- 転職活動に集中できる
- 現職に気を使う必要がない
- 体調やメンタルを整えられる
転職活動に集中できる
退職後に転職活動をする最大のメリットは、時間や労力をすべて転職活動に充てられることです。在職中の転職活動では、日々の業務をこなしながら求人を探し、履歴書や職務経歴書を作成し、面接の日程を調整する必要があるため、スケジュール管理が難しくなります。
フルタイムで働いている人にとっては、時間的な制約が大きな負担となるでしょう。
一方で、退職してから転職活動を始めれば、平日の昼間でも自由に時間を使えるため、面接の日程調整がしやすくなります。また、業界研究や自己分析にじっくり時間をかけられるため、より自分に合った転職先を見極めやすいです。
面接前の準備もしっかり行えるため、自信を持って選考に臨めるでしょう。
在職中に転職活動をすると、忙しさのあまり、じっくり考えずに内定を受けてしまうケースも少なくありません。退職後であれば、慎重に判断しながら転職活動を進めることが可能です。
現職に気を使う必要がない
在職中に転職活動をすると、会社にバレないように細心の注意を払わなければなりません。求人サイトの設定や、面接のための休暇取得など、転職活動そのもの以外の部分でも気を遣う場面が多くなります。また、転職活動が職場に知られてしまうと、上司や同僚の態度が変わったり、不当な扱いを受けたりする可能性も少なくありません。
その点、退職後に転職活動をする場合は、そうしたストレスを感じることなく自由に行動できます。面接の日程も自分の都合に合わせやすく、職場の人間関係に気を使う必要がないため、よりリラックスした状態で選考に臨めるでしょう。
また、退職後であれば、現職の仕事を理由に転職活動を妥協する必要がありません。例えば、現職が忙しくて面接の準備が不十分になる、転職活動に割ける時間が少ないため、条件が合わなくても内定を受けてしまうといった問題を回避できます。
体調やメンタルを整えられる
現在の職場が激務であったり、人間関係のストレスが大きかったりする場合、退職後に一度リフレッシュすることも重要です。とくに、心身の疲労が溜まっていると、転職活動に対する意欲が低下し、十分な準備ができないまま面接に臨んでしまう可能性があります。その結果、納得のいく転職先を見つけられず、後悔することになりかねません。
退職後に一定期間の休息を取ることで、体調を整えたり、精神的なリフレッシュを図ったりする時間を確保できます。焦らずに次のキャリアを考えることで、より前向きな気持ちで転職活動に取り組めるでしょう。
このように、退職後に転職活動を行うことで、焦らずに準備を進められ、より満足度の高い転職が実現しやすくなります。
退職してから転職活動するデメリット
退職してから転職活動をする方法には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。事前にデメリットを理解し、適切な対策を講じることで、より安心して転職活動を進められます。
- 収入が途切れるリスクがある
- 転職活動が長期化するリスクがある
収入が途切れるリスクがある
退職してから転職活動を始めると、次の職場が決まるまで収入が途絶えてしまいます。貯金が少ない状態で退職してしまうと、生活費の確保が大きな課題となるでしょう。家賃や光熱費、食費などの固定費はもちろん、急な出費が発生する可能性も考慮しなければなりません。
また、転職活動が予定よりも長引いた場合、金銭的な余裕がなくなり、希望条件を妥協せざるを得なくなることもあります。
このリスクを回避するためには、最低でも数カ月分の生活費を確保してから退職することが重要です。退職後の転職活動を考えている場合は、在職中にしっかりと貯金をしておくことで、金銭的な不安を軽減し、落ち着いて転職活動を進められるでしょう。
また、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できる場合もありますが、支給開始までに一定の期間が必要なため、すぐに資金が得られるわけではありません。その点も考慮しながら、計画的に転職活動を進めることが大切です。
転職活動が長期化するリスクがある
退職後に転職活動を始めると、時間の制約がなくなるため、じっくりと企業選びができるというメリットがあります。しかし、その一方で、気持ちに余裕がある分、つい転職活動を先延ばしにしてしまい、結果的に転職活動が長期化するリスクもあります。
仕事を辞めたばかりなので少し休みたいと思っていると、気づけば数カ月が経過してしまい、焦り始めるケースも少なくありません。転職活動が長引くほど、貯金は減っていき、精神的なプレッシャーも大きくなるため、当初の計画通りに進めることが重要です。
また、ブランク期間が長くなると、長期間の空白について合理的な説明ができるかどうかを重視するため、しっかりとした理由を準備しておくことが必要です。
このリスクを防ぐためには、退職後の転職活動に明確なスケジュールを設定し、計画的に進めることが大切です。〇月までに応募を開始する、〇社以上の企業に応募するなど、具体的な目標を決めることで、モチベーションを維持しながら転職活動を進められるでしょう。
また、転職活動を長期化させないためには、資格取得やスキルアップのための学習時間を確保するのも一つの方法です。新しいスキルを身につけることで、転職市場での競争力を高め、より良い条件の企業に内定をもらいやすくなるでしょう。
「退職から転職」の順番におすすめな人は?
「退職から転職」の順番におすすめな人は、以下の通りです。
- 仕事を続けながら転職活動をするのが難しい人
- 精神的・身体的に疲れが溜まっている人
- キャリアチェンジやスキルアップを目指す人
- 貯金が十分にあり、生活費の心配がない人
- 時間をかけて転職活動を進めたい人
「退職してから転職する」方法が向いているのは、現職が多忙で転職活動の時間を確保できない人や、精神的・身体的な疲れが溜まっていて一度リフレッシュしたい人です。とくに、キャリアチェンジを考えている場合や、新しいスキルを習得してから転職したい場合は、退職後にじっくり準備を進めることで有利になります。
また、焦らず納得のいく転職先を選びたい人にも適しておりますが、貯金に余裕があることが前提です。
転職・退職どちらの順番が先でも押さえておきたいポイント
転職の成功には、退職と転職の順番以上に、計画的な準備が重要です。どちらを先に選ぶとしても、しっかりとスケジュールを立て、経済的な備えを整え、スムーズな退職と転職活動を進めることが求められます。また、円満退職のための引き継ぎや、転職エージェント・退職代行の活用など、適切なサポートを受けることもポイントです。
- 転職活動のスケジュールを立てる
- 貯金などの経済的な準備を整える
- 退職のタイミングと伝え方に注意する
- 円満退職するなら引き継ぎを丁寧にする
- 転職エージェント・退職代行サービスを利用する
転職活動のスケジュールを立てる
転職を成功させるには、事前にスケジュールを立て、計画的に進めることが重要です。無計画に進めると、転職活動が長期化したり、退職後に焦って就職先を決めてしまったりするリスクがあります。
まず、転職活動の開始時期を決めましょう。在職中に転職活動をする場合、仕事の合間に応募書類の作成や面接をこなす必要があるため、スケジュール管理が重要になります。応募から内定までには平均3〜6カ月程度かかるため、余裕を持った計画を立てることが大切です。
一方、退職後に転職活動をする場合は、生活費を考慮しながら、どのくらいの期間で次の仕事を決めるかを明確にしておくとよいでしょう。転職活動の長期化を防ぐためにも、毎月の応募数や面接の目標を決め、計画的に進めることが求められます。
また、企業の採用スケジュールにも注意が必要です。業界によっては求人が増える時期が異なるため、転職を考えている業界の採用動向をリサーチし、最適なタイミングで動くことが大切です。初めて転職活動する人は、下記の記事も参考になりますのでご確認ください。
関連記事:初めての転職活動で失敗しない21の注意点!転職の流れを押さえよう
貯金などの経済的な準備を整える
転職活動中は、想定以上に時間がかかることもあるため、金銭的な余裕を持っておくことが重要です。在職中は安定して収入があるのであまり心配いりませんが、退職してから転職活動する場合は注意しましょう。
一般的には、少なくとも3〜6カ月分の生活費を貯めてから退職するのが理想的です。家賃や光熱費、食費だけでなく、交通費や通信費なども考慮して、転職活動に必要な資金を見積もっておきましょう。
また、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる場合は、手続き方法を事前に確認しておくと良いでしょう。ただし、自己都合退職の場合は、受給開始までに時間がかかるため、当てにしすぎるのは危険です。貯金と合わせて、計画的に経済的な準備を進めることが大切です。
退職のタイミングと伝え方に注意する
退職のタイミングは、転職活動の進捗や企業の繁忙期などを考慮して決めることが重要です。会社の就業規則によっては、退職の申し出が必要な期間が定められている場合があるため、事前に確認しておきましょう。一般的には、退職の1〜2カ月前には上司に伝えるのが望ましいとされています。
退職を伝える際は、できるだけ円満に進めることが大切です。感情的にならず、冷静かつ丁寧に退職の意向を伝えることで、トラブルを防げます。退職理由についても、ネガティブな内容は避け、新しいことに挑戦をしたい、キャリアアップを目指したいといった前向きな表現を心がけると良いでしょう。
また、引き止めに遭う可能性もあるため、退職の意思を固めた上で伝えることが重要です。会社側から条件改善の提案を受けることもありますが、転職の意思が強い場合は、揺らがないようにしましょう。
退職を伝えるタイミングについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:退職は何日前までに伝えるべき?法的ルールと正しい辞め方を解説します
円満退職するなら引き継ぎを丁寧にする
円満退職を目指すなら、引き継ぎをしっかり行うことが不可欠です。引き継ぎが不十分だと、退職後にトラブルが発生し、前職との関係が悪化する可能性があります。
引き継ぎの際は、業務内容を整理し、後任者がスムーズに業務を進められるようにすることが大切です。自分しか把握していない業務がある場合は、マニュアルを作成したり、具体的な手順を文書化したりするのがおすすめです。
また、取引先や社内の関係者に対しても、適切なタイミングで引き継ぎを行うことが重要です。信頼関係を保つためにも、退職後の影響を最小限に抑えるよう努めましょう。円満退職のやり方は以下の記事を参考にしてください。
関連記事:円満な退職の伝え方を解説!上司や同僚に伝えるポイントや例文を紹介
転職エージェント・退職代行サービスを利用する
転職活動をスムーズに進めるためには、転職エージェントを活用するのも有効な手段です。転職エージェントを利用すると、非公開求人の紹介や履歴書・職務経歴書の添削、面接対策などのサポートを受けられます。とくに、忙しい人や転職に不安がある人にとって、プロのアドバイスは大きな助けとなるでしょう。
一方で、退職意思を伝えにくい場合は、退職代行サービスを利用するのも選択肢の一つです。退職代行を利用すれば、会社との直接のやり取りをせずに退職できるため、精神的な負担を軽減できます。転職エージェントや退職代行サービスを上手に活用しながら、自分にとって最適な方法で転職・退職を進めることが大切です。
転職・退職で失敗しないための手順
転職と退職を成功させるには、しっかりとした計画が必要です。転職・退職で失敗しないための手順を紹介します。
- 1.転職活動の「軸」を明確にする
- 2.現在の仕事の状況を確認する
- 3.転職活動に必要な準備を進める
- 4.転職活動と現職のバランスを取る
- 5.内定後の確認事項をチェックする
- 6. 引き継ぎと退職手続きを計画的に行う
1.転職活動の「軸」を明確にする
転職を成功させるためには、なぜ転職したいのか、どのような条件を求めているのかといった転職の軸を明確にすることが重要です。軸が定まっていないと、求人を探す際に迷ってしまい、適切な企業を選べなくなる可能性があります。例えば、以下のような観点で自分の希望を整理すると良いでしょう。
- キャリアの方向性:今後どのようなキャリアを築きたいのか
- 仕事内容:どのような業務に携わりたいのか
- 給与・待遇:最低限必要な給与や福利厚生の条件
- 働き方:リモートワークやフレックスタイム制などの希望
- 企業文化:会社の雰囲気や価値観が自分に合うか
これらの軸を明確にしておくと、求人を比較しやすくなり、ミスマッチを防げます。
2.現在の仕事の状況を確認する
転職活動を始める前に、まずは現在の仕事の状況を整理することが重要です。自分が担当している業務の進捗状況や、繁忙期かどうかを把握し、退職を申し出る適切なタイミングを見極めましょう。また、引き継ぎの必要性や、退職までに終わらせるべき業務があるかどうかもチェックが必要です。
3.転職活動に必要な準備を進める
転職活動をスムーズに進めるためには、事前準備が欠かせません。まず、履歴書や職務経歴書を作成し、自分の強みやスキルを整理することが大切です。企業が求める人物像に合わせてアピールポイントを明確にすることで、選考を有利に進められます。
また、転職サイトや転職エージェントに登録し、求人情報を収集することも必要です。
転職エージェントを利用することで、非公開求人の紹介を受けられるだけでなく、履歴書の添削や面接対策のサポートも受けられます。また、面接の準備として、よく聞かれる質問を想定し、適切な回答を用意しておくことも重要です。万全の準備を整えることで、転職活動をスムーズに進められます。
4.転職活動と現職のバランスを取る
在職中に転職活動を進める場合、仕事との両立が大きな課題となります。仕事に支障をきたさないようにしながら、効率的に転職活動を進めるためには、スケジュール管理が欠かせません。例えば、求人の検索や応募書類の作成は夜や週末に行い、面接の日程はフレックス制度や有給休暇を活用して調整するのが理想的です。
また、転職活動をしていることを職場の同僚や上司に気付かれないように注意することも大切です。業務のパフォーマンスが突然下がると、不審に思われる可能性があるため、普段通りの仕事ぶりを維持することを心がけましょう。仕事と転職活動のバランスを上手に取ることで、円滑に次のステップへ進めます。
5.内定後の確認事項をチェックする
無事に内定を獲得したら、入社前に確認すべきポイントをしっかり押さえておきましょう。給与や待遇が希望と合っているか、労働条件に問題がないかを細かくチェックすることが重要です。雇用契約書や労働条件通知書に記載されている内容を確認し、疑問点があれば入社前にしっかり解消しておきましょう。
また、入社日についても現職の退職スケジュールと照らし合わせながら調整することが求められます。焦って退職を早めたり、無理に入社日を前倒ししたりすると、引き継ぎが十分にできずトラブルにつながる可能性があるため、慎重に進めることが大切です。
6. 引き継ぎと退職手続きを計画的に行う
内定が決まった後は、引き継ぎと退職手続きを計画的に進めることが重要です。退職を円滑に進めるためには、業務の整理や後任者への引き継ぎを丁寧に行うことが求められます。まず、自分が担当している業務をリストアップし、引き継ぎが必要な項目を明確にしましょう。
その上で、マニュアルを作成するなど、後任者がスムーズに業務を引き継げるよう工夫すると、会社に対する印象も良くなります。また、退職意向を上司に伝える際には、感謝の気持ちを述べつつ、できるだけ円満に進めることが大切です。
必要な書類の提出や、会社貸与物の返却など、退職に関する手続きを漏れなく進めることで、スムーズな退職を実現できます。
まとめ
転職と退職の正しい順番について紹介しました。結論、転職と退職に正しい順番はありません。個々で状況が異なりますので、自分の状況に合わせてどちらの順番を先にするか考えましょう。順番に迷っている人は、メリット・デメリットを参考に考えてください。
転職や退職を効率よく進めるには各々のプロからサポートを受けることです。退職に関する悩みがある方は、退職代行ほっとラインへご相談ください。退職に関するご相談はいつでも無料です。

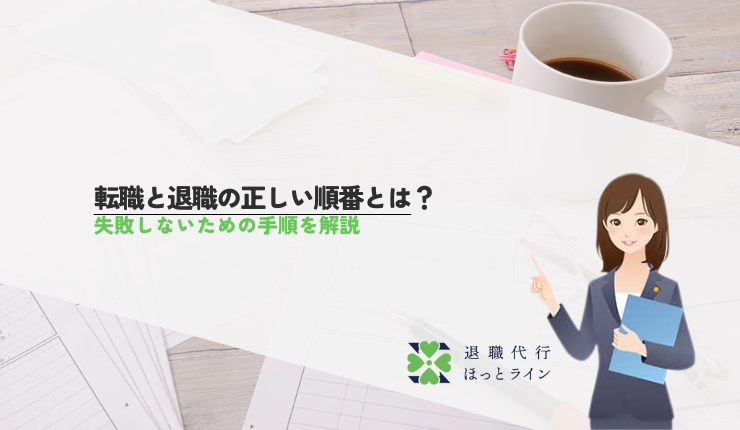



コメントを残す