毎日のように残業を強制させられて、夜遅くまで働き続ける人は少なくありません。残業するのが当たり前になっている職場では、残業せずに帰りにくいものです。残業があまりにも長すぎたり、上司の命令で拒否できない状況が続いていたりする場合は、違法な働かせ方かもしれません。
本記事では、残業を強制させられる場合の対処法について紹介します。違法性や拒否できる条件も解説しますので、参考にしてください。
・残業を強制させられる場合に違法となるケースは、36協定が締結されていない、残業代が支払われない、パワハラで帰れない雰囲気を作られているなど
・残業の強制を拒否できる条件は、体調不良や健康上に問題があるとき、育児・介護・家庭の事情があるとき、妊娠中・出産から1年未満のとき
・残業を強制させられる場合の対処法は、残業を強制させられている証拠を集める、上司、社内の相談窓口、労働基準監督署などに相談する
目次
残業を強制させられる場合に違法となるケース
会社が労働者に対して残業を強制する際には、法律上のルールを守る必要があります。36協定の未締結や、協定の上限を超える労働時間の強要、残業代の未払いなどは明確な違法行為です。具体的に見ていきましょう。
- 36協定が結ばれていないのに残業を強制させられる
- 36協定が結ばれていても上限を超える場合は違法
- 残業代が支払われない・みなし残業を超えているのに残業を強制させられる
- 正当な理由なしに残業を拒否できない
- パワハラで帰れない雰囲気を作られている
- 業務に関係ない残業を強制させられる
- 残業の強制が認められるケースは?
36協定が結ばれていないのに残業を強制させられる
労働基準法では、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて労働させる場合、会社は労働者と「36(さぶろく)協定」を結ばなければなりません。正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれ、労使間で書面により取り交わすことが必要です。
36協定が結ばれていない状態で残業を強制することは、法律違反にあたります。
とくに、中小企業では36協定をきちんと提出せずに、口頭や慣習だけで残業を命じるケースが少なくありません。しかし、これは重大な労働法違反です。厚生労働省に申告すれば、監督署の指導や企業への是正勧告が行われる可能性もあります。
会社に曖昧な理由で残業を強制させられた場合、まずは自社の36協定の有無を確認してみましょう。
36協定が結ばれていても上限を超える場合は違法
36協定を締結していても、無制限に残業させてよいというわけではありません。厚生労働省が定めたガイドラインでは、月45時間・年360時間を超える残業は原則として認められていません。特別条項付き36協定を結んだ場合でも、年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内など、明確な上限があります。
これらの上限を超えて残業を命じる行為は違法となり、会社は行政指導や罰則の対象となります。繁忙期は残業が増えがちですが、無制限に残業を押しつけられることは認められていません。
会社から36協定を結んでいるからと説明があったとしても、上限時間を確認せずに従ってしまうのは危険です。基本的には会社が労働者の残業時間を管理しましが、自分でも残業時間を把握しておきましょう。
残業代が支払われない・みなし残業を超えているのに残業を強制させられる
残業を強制させられているにもかかわらず、残業代が支払われないケースは重大な違法行為です。とくにみなし残業(固定残業代)制度を導入している企業では、支給されているから問題ないと思い込みがちですが、実際の労働時間がみなし分を超えている場合、その差額を別途支払わなければなりません。
例えば、月20時間分の残業代を含む給与が支払われているとしても、実際に30時間働いていれば、追加の10時間分の残業代を請求する権利があります。この差額が支払われず、なおかつ残業を強制されている場合、二重に違法となります。
未払いの残業代を請求する方法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:残業代が計算されない理由は?未払いの残業代を請求する方法を解説
正当な理由なしに残業を拒否できない
労働者は原則として、会社からの業務命令に従う義務があります。残業を命じられたとしても、家庭の事情や体調不良など、正当な理由があれば残業を拒否することは可能です。逆に、正当な理由があるにもかかわらず、会社が一方的に残業を強制させることは労働契約法第5条や労働安全衛生法に違法する行為です。
現場では、忙しいから、会社の指示に従うのは当たり前、などの理由をつけて正当な理由があっても認めてもらえないケースがあります。このような場合は、労働相談窓口や労働基準監督署に相談し、第三者のサポートを受けることを検討しましょう。
パワハラで帰れない雰囲気を作られている
上司からの直接的な命令がなくても、暗黙のうちに残業を強いられるケースがあります。これはパワハラの一種であり、立派な労働問題です。
このような状況では、労働者は自由に退勤する選択ができず、実質的に残業を強制されている状態に置かれています。とくに、上司が威圧的な態度をとったり、帰ろうとすると嫌味を言ったりする場合は、精神的な圧力によるパワハラといえるでしょう。
パワハラによって自主的に残業しているように見せかけても、実態としては強制労働です。パワハラの対処法や判断基準については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:パワハラ被害にあった場合の無料相談窓口8選!被害にあったときの対処法とセットで解説します
パワハラか判断するためには?判断基準や判例をわかりやすく紹介
業務に関係ない残業を強制させられる
業務に直接関係ない作業を残業時間に行わせることは、違法行為に該当する場合があります。業務終了後に個人的な仕事をさせられる、あるいは本来の業務とは関係ない雑務を押し付けられるケースです。
業務に関係ない残業を強制させられるケースも上記で説明したように、パワハラに当たる可能性があります。例えば、草むしりやトイレ掃除など誰にでもできるような仕事を押し付けるのは、パワハラの「過小な要求」です。
残業を命じられた際には、仕事内容が業務に関連するものかどうかを確認することが大切です。
残業の強制が認められるケースは?
基本的に会社が残業を強制することは、違法ではありません。残業指示が正当である場合、会社の指示に従わなければならない義務があるからです。
例えば、突発的な業務の急増や緊急のプロジェクト、納期が迫った場合など、会社がやむを得ず残業を求める状況があります。このようなケースでは、企業側には労働者に対して追加労働を求める正当な権利があるとされています。
ただし、残業が必要となる場合でも、36協定の範囲内であり、残業代を支払うことが必要です。また、休憩時間や休日を適切に設けることが求められます。これらの条件を満たすことなく残業を強制した場合、法的に問題となります。
残業の強制を拒否できる条件とは?合法的に断れるケースを紹介
残業を強制された場合でも、一定の条件においては合法的に断れます。合法的に断れるケースを3つ紹介します。
- 体調不良や通院など健康上の理由があるとき
- 育児・介護・家庭の事情があるとき
- 妊娠中・出産から1年未満のとき
体調不良や通院など健康上の理由があるとき
体調不良や通院など健康上の理由があるときは、残響を拒否することが可能です。労働基準法では、健康を害するような労働環境を強制することを禁じています。労働安全衛生法では、従業員の健康や安全を守る義務があると定めています。
つまり、体調不良を訴えているにもかかわらず残業を強制することは、これに違反する行為です。体調不良の線引きは難しいですが、熱がなかったとしても基本的には従業員の健康を気遣うのが会社の義務です。体調不良の基準については、以下の記事で説明していますので参考にしてください。
関連記事:仕事を休むときの判断基準は?仕事を休めないときの対処法も紹介
育児・介護・家庭の事情があるとき
家庭の事情によっては、残業を合法的に拒否できるケースがあります。とくに育児や介護が理由であれば、育児・介護休業法により、時間外労働の制限を申し出ることが可能です。例えば、小学校就学前の子どもを育てている労働者は、1日2回、各30分の育児時間の請求や、残業の免除を求める権利が認められています。
また、要介護状態の家族がいる場合も、一定の条件下で残業の制限を申し出ることが可能です。
これらの制度を利用するには、事前に会社へ申し出る必要があります。書面で提出することが一般的で、提出後は会社側に正当な理由がない限り、残業を強制できません。ただし、業務の性質や就業規則によっては一部制限がある場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
妊娠中・出産から1年未満のとき
妊娠中や出産から1年未満は、法律によって残業を断る権利が明確に定められています。労働基準法では、妊娠中および産後1年未満の女性労働者が申し出た場合、時間外労働(残業)、休日労働、深夜業をさせてはならないと規定されています。これは母体の保護と育児支援を目的とした重要な法律です。
産後の体調不良や育児負担の程度によっては、医師の診断書を添付するとよりスムーズに受け入れられやすくなります。
残業を強制させられる場合の対処法
正当な理由もなく残業を強制させられる場合、適切な対応を取ることが大切です。状況に応じて以下の対処法を検討してください。
- 残業を強制させられている証拠を集める
- 就業規則や労働契約書を確認して正当性をチェックする
- 直属の上司に冷静に相談する
- 社内の相談窓口や労働組合に相談する
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談して法的措置を取る
- 改善が見込めない場合は転職する
残業を強制させられている証拠を集める
違法な残業を拒否するためには、まず残業を強制された事実を証明できる証拠が必要です。証拠がなければ、会社側に本人の意思で残業していたと主張される可能性があります。そこで、タイムカードや勤怠管理システムの記録、メールやチャットでの残業指示の文面、日報や業務報告など、日々のやりとりを保存しておくことが大切です。
スマートフォンで出退勤時刻を記録するのも有効な手段といえるでしょう。
証拠を集める際は、できるだけ客観的かつ改ざんされにくいものを選びましょう。また、職場の録音が認められる場合には、上司との会話を録音することで、強制の実態を残せます。これらの証拠は後々、労働基準監督署や弁護士に相談する際の重要な資料となります。
就業規則や労働契約書を確認して正当性をチェックする
残業の強制が違法かどうかを判断するには、就業規則や労働契約書に記載された労働条件を確認しましょう。就業規則には残業の上限や対象となる業務、指示の出し方などが定められているはずです。これらの記載と実際の勤務状況を照らし合わせて、企業側が正当な手続きで残業を命じているかを確認してください。
直属の上司に冷静に相談する
残業の強制に疑問を感じたら、まずは直属の上司に冷静に相談しましょう。感情的に訴えると話し合いがうまく進まないこともあるため、事実に基づいて状況を説明することが大切です。体調不良や家庭の事情など明確な理由を説明すれば、納得してもらえる可能性があります。
もし、上司が相談に応じなかったり、逆にプレッシャーを強めてきたりする場合は、社内の他部署や労務担当へ相談ルートを切り替えることが必要になります。社内の相談窓口や労働組合、労働基準監督署など、状況に応じて相談窓口を選びましょう。
社内の相談窓口や労働組合に相談する
直属の上司に相談しても改善が見られない場合は、社内の相談窓口や労働組合を活用するのが効果的です。多くの企業には、コンプライアンス担当部門や人事部門など、労働環境の問題を受け付ける窓口が設置されています。
匿名での相談を受け付けている企業もあるため、報復を恐れずに問題提起することが可能です。
また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて会社側に改善を申し入れてもらえます。個人では伝えにくい内容も、団体交渉によって正式な形で会社に届けられるため、交渉力が高まります。とくに大企業の場合、労働組合が積極的に活動しているケースが多く、組合を通すことで問題解決が進みやすくなるでしょう。
会社の内部制度を活用することは、外部に訴える前の重要なステップです。内部の力をうまく使って状況を改善できるかどうかを確認してから、次の対応に移ることをおすすめします。労働組合に相談できる内容や相談の流れについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説
労働基準監督署に相談する
社内での相談がうまくいかなかった場合は、労働基準監督署に相談しても良いでしょう。労働基準監督署は厚生労働省の下にある行政機関で、労働基準法違反の申告を受け付け、必要に応じて会社へ指導や是正勧告を行います。残業の強制や未払い残業代などの問題がある場合には、証拠を持って申告することが重要です。
申告は匿名でも可能ですが、実名で行う方が調査が進みやすい傾向があります。担当官が会社に立ち入り調査を行うこともあり、悪質な場合は企業名が公表されることもあります。実際に改善された例も多く報告されており、社内で変化が見られなかったときの有効な手段となります。
ただし、申告後の対応には時間がかかることもあるため、早めに行動を起こすことが大切です。
弁護士に相談して法的措置を取る
強制残業が明らかに違法であり、会社側も対応しない場合には、弁護士に相談して法的措置を検討する必要があります。労働問題に強い弁護士であれば、残業代請求や不当な労働環境に対する損害賠償請求、労働審判の申し立てなど、状況に応じた対応をアドバイスしてくれます。
無料相談を実施している法律事務所や、労働問題を専門に扱うNPO団体もありますので、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。証拠を揃えておけばで、弁護士とのやりとりもスムーズです。口頭のやりとりだけでなく、文書や録音、チャット記録など、時系列に沿った資料が役立ちます。
改善が見込めない場合は転職する
あらゆる対処を試みても職場環境が改善されない場合は、転職を検討しましょう。労働環境は心身の健康に直結するため、無理に働き続けることは長期的に見て大きなリスクとなります。とくに、残業の強制が常態化していたり、社内の相談窓口が機能していない場合は、根本的な体制に問題がある可能性が高いといえます。
自分の希望に合った企業を効率的に探すには、転職エージェントを活用がおすすめです。また、残業を強制させられる、職場環境が改善されないといった企業はブラック企業である可能性があります。退職したくても退職できない場合は、退職代行サービスを利用しましょう。
残業を強制させられる場合に関するよくある質問
残業を強制させられる場合に関するよくある質問を紹介します。
- 残業の強制はおかしい!拒否した場合はクビになる?
- パート・アルバイトでも残業の強制を断る権利はありますか?
- 残業を強制されるのはパワハラに当たりますか?
- 残業代を支払ってもらえない!会社に残業代を請求する方法は?
- サービス残業を強制させられるときの対処法は?
残業の強制はおかしい!拒否した場合はクビになる?
正当な理由がある場合でも、残業を拒否したらクビになるのではと不安に思う方もいます。しかし、残業を断ったことだけを理由に解雇するのは、労働契約法第16条に違反する可能性が高いです。
企業は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ従業員を解雇できません。また、36協定が未締結である、もしくは法定上限を超える残業を命じられているような場合は、命令自体が無効になります。万が一解雇されたとしても、不当解雇として争うことが可能です。
パート・アルバイトでも残業の強制を断る権利はありますか?
パートやアルバイトであっても、残業の強制を断る権利はあります。雇用形態に関わらず、残業命令には法的根拠や36協定の締結が必要です。これがない場合、企業に残業を命じる権限はありません。自身の契約内容を再確認したうえで、不当な要求であれば毅然と対応しましょう。
残業を強制されるのはパワハラに当たりますか?
状況によっては、残業の強制がパワハラと見なされることもあります。例えば、明らかに業務に関係のない作業を残業として強要される、上司の威圧的な態度によって断れない雰囲気を作られている、そういった場合にはパワハラの要素があると判断されやすいです。
残業代を支払ってもらえない!会社に残業代を請求する方法は?
残業をしているのに賃金が支払われない場合、労働基準法違反です。まずは、自分の労働時間と実際の賃金を記録しておきましょう。タイムカードやメール、勤怠アプリなど、客観的な証拠が重要です。そのうえで、会社に対して未払い残業代を請求する意思を伝えます。
話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署への申告や、弁護士を通じた法的請求も検討してください。未払い残業代は時効があるため、早めに行動することが大切です。
サービス残業を強制させられるときの対処法は?
サービス残業は違法です。労働基準法第37条では、1日8時間・週40時間を超える労働が発生した際には、通常の賃金よりも高い割増賃金を支払う義務があるとされています。サービス残業を要求された場合は、きっぱりと断ることが重要です。
断り切れず引き受けていると、サービス残業が常態化してしまいます。より詳しい対策方法については、以下の記事を確認してください。
関連記事:タイムカード打刻後に残業を要求されたときの対処法と違法性について解説
まとめ
残業を強制させられるときの対処法について紹介しました。基本的に会社から残業命令を受けた場合は、引き受けなければなりません。しかし、業務に関係のない仕事や、36協定を超える残業は拒否できます。残業を断ることは勇気がいりますが、自分の健康のためにもきっぱりと断りましょう。
違法な残業が正当化されている場合、働きやすい環境へ移ることをおすすめします。また、違法な残業を強制させられるような会社は、ブラック企業である可能性が高いです。退職時にトラブルを避けるためにも、退職代行サービスの利用をおすすめします。退職に関する悩みや不安がある人は、退職代行ほっとラインへご相談ください。

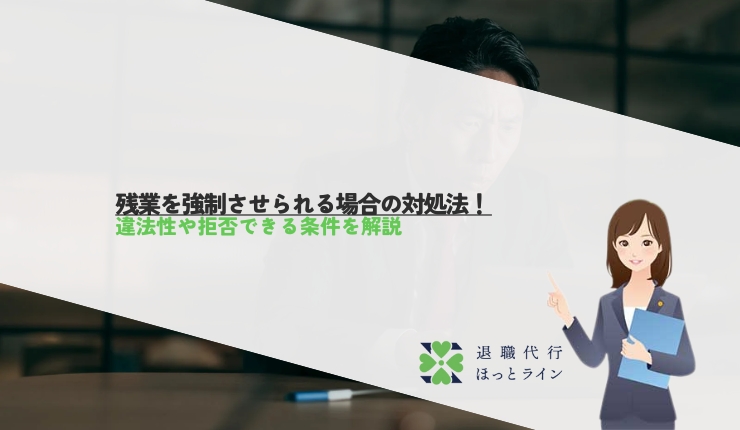


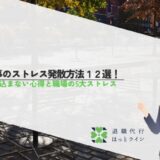
コメントを残す