近年、副業を解禁する企業は増えていますが、まだまだ社内副業を許可しない会社も少なくありません。収入を少し増やしたい、新しい分野にチャレンジしてみたい、と考えている人にとっては障壁となります。
本記事では、社内副業が許可されない理由を紹介します。また、副業が禁止されているときの対処法や、副業以外で収入を得る方法について紹介するので、参考にしてください。
・社内副業は法律で禁止されていないが、公務員は法律で副業が禁止されている
・社内副業が許可されない理由は、本業に支障が出るリスクを避るため、情報漏洩のリスクを防ぐため、会社の信用・ブランドに悪影響が出るのを防ぐためなど
・社内副業が許可されないときの対処法は、会社の就業規則を詳しく確認する、副業できないか交渉する、副業OKな会社に転職する
・副業以外で収入を得る方法は、株式投資、株式信託、不動産投資、車のシェア、不用品販売など
社内副業は法律で禁止されていない!
副業は禁止と言われると、法律で規制されているように感じるかもしれません。しかし、民間企業の会社員に対して副業を禁止する法律は存在しません。厚生労働省も働き方改革の一環として、副業・兼業を推進する方針を明確に打ち出しています。
実際に、モデル就業規則でも副業・兼業の推奨が明記され、企業側にはできるだけ認めるよう求められています。つまり、法律上は副業は認められており、禁止するかどうかは各企業の就業規則に委ねられているのが現状です。
とはいえ、企業によっては労務管理の複雑化や情報漏洩リスクなどを理由に、副業を禁止している場合もあります。このため、副業を始める際は、まず自社の就業規則や社内ルールを確認することが大切です。
国家公務員は副業を禁止されているので注意
民間企業の会社員とは異なり、国家公務員には明確な副業禁止規定があります。国家公務員法第103条と第104条によって、副業や兼業、営利企業への従事が原則として禁止されています。
このルールが定められているのは、公務員の公正中立な職務遂行を守り、私的な収入活動が、公務に影響を与えることを防ぐためです。
ただし、すべての活動が一律に禁止されているわけではありません。ボランティア活動や、一部の公益活動については、事前に許可を得れば認められるケースもあります。
地方公務員についても、基本的には同様に副業が制限されていますが、地域貢献型の副業を例外的に認める動きも出てきています。いずれにせよ、公務員の方が副業を検討する場合は、必ず所属先に確認し、許可を得た上で行動することが必要です。
社内副業が許可されない理由は?
副業を希望しても、社内規則によって禁止されるケースは少なくありません。社内副業が許可されない背景には、企業側のさまざまなリスク回避の意図が存在します。社内副業が許可されない理由について見ていきましょう。
- 本業に支障が出るリスクを避るため
- 情報漏洩のリスクを防ぐため
- 競業(同業他社)で働かれることを防止するため
- 会社の信用・ブランドに悪影響が出るのを防ぐため
- 過重労働による健康リスクを懸念しているため
本業に支障が出るリスクを避るため
副業に多くの時間やエネルギーを費やすことで、本業のパフォーマンスが落ちるリスクがあります。企業は、従業員に対して本業で最大限の成果を求めています。
そのため、副業により集中力や体力が削がれ、業務に悪影響が出ることを懸念するのです。
また、副業によって疲弊し、遅刻や欠勤が増えると、チーム全体にも悪影響を与える可能性があります。こうした事態を未然に防ぐために、副業を原則禁止している企業も多いのが実情です。
従業員個人の自由を尊重する一方で、企業としての経営責任を果たすための措置でもあります。副業を希望する場合は、まず自分の労働時間やパフォーマンス管理に注意を払いましょう。
情報漏洩のリスクを防ぐため
副業によって、会社の機密情報が外部に漏れるリスクが高まることも、企業が副業を制限する理由のひとつです。とくにIT業界やコンサルティング業界など、機密性の高い情報を取り扱う業種では、その傾向が顕著です。
たとえ意図的でなくても、副業先で自社のノウハウや技術情報を利用してしまうケースも考えられます。こうしたリスクは、会社の競争力低下や信用失墜につながりかねません。
企業はリスク管理の観点から、情報漏洩を防ぐために副業を禁止または厳格に制限しています。副業を考える際には、自社の情報管理規定を十分に確認し、トラブルを未然に防ぐ意識が求められます。
競業(同業他社)で働かれることを防止するため
同業他社での副業は、企業にとって大きなリスクとなります。競業にあたる副業を許可してしまうと、自社の顧客情報や営業戦略が漏洩する可能性があるからです。
また、同業他社で働くことで、利益相反の問題が発生することも懸念されています。自社よりも副業先に力を入れてしまえば、本業への忠誠心や成果に悪影響が及ぶ恐れもあるでしょう。
このため、多くの企業では就業規則に競業避止義務を設け、競合他社での副業を明確に禁止しています。副業を検討する際には、自社がどの業界を競業とみなしているかを事前に把握しておくことが重要です。
会社の信用・ブランドに悪影響が出るのを防ぐため
副業先でのトラブルや不適切な行動が、自社の信用やブランドイメージに悪影響を与えるリスクもあります。例えば、副業中の言動が炎上した場合、その個人の所属企業まで批判の対象となる可能性があるのです。
SNS時代においては、個人の行動がすぐに拡散され、会社の評判に直結しやすくなっています。企業はブランド価値を守るため、社員の副業を慎重に管理しようとする傾向が強まっています。
副業を始める場合は、自身の行動が所属企業にどのような影響を与えるかを常に意識することが大切です。副業先でも、社会人としてのマナーやコンプライアンスを厳守する姿勢が求められます。
過重労働による健康リスクを懸念しているため
副業によって労働時間が増加すると、過労による健康リスクが高まります。企業は従業員の安全配慮義務を負っており、社員が健康を損なうことを防ぐ責任があります。
もし副業によって体調を崩した場合、労働災害として企業の責任問題に発展する可能性もあるのです。このため、企業は過重労働を未然に防ぐため、副業を制限または禁止する判断を下しています。
副業を始める際には、自分自身の体力や生活リズムをよく見極め、無理のない範囲で計画的に取り組むことが大切です。心身の健康を第一に考えた働き方を心がけましょう。
社内副業が許可されないときの対処法
副業を始めたいと考えても、社内規定により禁止されている場合があります。しかし、諦める前にできる対処法を検討することが重要です。社内副業が許可されないときの対処法を紹介します。
- 会社の就業規則を詳しく確認する
- 会社に副業できないか交渉する
- 副業OKの会社に転職するのも一つの選択肢
会社の就業規則を詳しく確認する
副業を始めたいときは、会社の就業規則をきちんと確認することです。就業規則には、副業に関する規定や許可基準、手続き方法などが明記されているケースが多くあります。
例えば、「事前申請が必要」「会社が認める場合のみ許可」「特定業種は禁止」など、細かいルールが設定されているかもしれません。しかし、逆に言うと、規則に細かい記載がない場合は、副業の実施方法について抜け道があるかもしれません。
原則として副業が禁止されている場合でも、一定の条件を満たしたり、会社と特別な契約を結ぶことで認められることもあります。どのケースが認められ、どの場合が許可されないのかをきちんと確認することが重要です。
必要であれば、正確な情報を得るために人事部や労務担当者に直接確認することをおすすめします。
会社に副業できないか交渉する
副業を希望する場合、会社に交渉して許可を得る道もあります。単に副業したいと伝えるだけでなく、どのような内容の副業を考えているのか、会社に与える影響がないことを具体的に説明しましょう。
例えば、副業の内容は本業と無関係であり、勤務時間外にのみ行う、体力や業務パフォーマンスには影響しないといった説明を準備しておくと、説得力が増します。また、副業によるスキルアップが本業にもプラスに働く可能性がある点をアピールするのも効果的です。
企業によっては、事業貢献に資する副業なら柔軟に許可する方針を採る場合もあります。一方的に禁止と決めつける前に、建設的な対話の機会を持つことが成功への近道です。誠意を持って交渉に臨み、会社側の懸念にも真摯に対応する姿勢が求められます。
副業OKの会社に転職するのも一つの選択肢
どうしても副業が認められない場合、思い切って副業OKの会社へ転職するという選択肢もあります。近年では、社員の自己実現やスキルアップを支援する目的で、副業を推奨する企業が増えています。
とくに、IT業界やベンチャー企業では、副業を通じた人材育成や組織の活性化を狙う動きが顕著です。転職を考える際には、「副業制度あり」「副業実績あり」といった条件で求人を探すとよいでしょう。
また、転職エージェントを活用すれば、自分に合った副業OKの求人を効率よく見つけることが可能です。キャリアアドバイザーに相談することで、非公開求人や交渉ノウハウなど、通常では得られない情報も手に入ります。
自分の理想の働き方を実現するために、柔軟に環境を変える決断も大切です。転職はリスクを伴う一方で、大きなチャンスでもあるため、慎重かつ前向きに検討しましょう。
副業以外で収入を得る7つの方法
副業ができない場合でも、収入を得る方法は多く存在します。これから紹介する方法は、いずれも比較的低リスクで始めやすいものが多いため、生活費の補填や資産形成に役立つかもしれません。本業に影響を与えずに実践できる収入源を増やすために、以下の方法を検討してみましょう。
- 1.株式投資(配当金)
- 2.投資信託(インデックスファンド)
- 3.不動産投資(賃貸収入)
- 4.駐車場・スペースの貸し出し
- 5.車のシェア(Anyca など)
- 6.不用品の売却
- 7.ポイ活
1.株式投資(配当金)
株式投資は、企業の株を購入し、その企業から配当金を得る方法です。安定した企業の株を選び、長期的に保有することで、定期的な配当金を得られます。株式投資は元手が必要ですが、株価の上昇と配当金の両方で利益を得られるため、資産を増やす手段として有効です。
株の取引には一定の知識が必要ですが、インターネットで学びながら始められます。リスクは伴いますが、正しい知識と戦略を持って取り組むことで、安定的な収益源に育てられます。投資信託やETFなど、株式投資以外の方法でも配当収入を得られる手段もありますので、初心者でも始めやすいです。
2.投資信託(インデックスファンド)
投資信託は、多くの株や債券などに投資するファンドにお金を預ける方法です。その中でも、インデックスファンドは市場全体の平均的な成績を追求するため、比較的安定した運用が期待できます。
少額から投資を始められ、長期的な視点で資産形成を目指せる点が魅力です。手間が少なく、プロが運用してくれるため、初心者にも向いています。
また、分散投資を行うため、リスクを低減できるのも大きな利点です。インデックスファンドは手数料も低めで、長期間投資を続けることで複利効果を享受できるため、時間を味方につけて資産を増やせます。
3.不動産投資(賃貸収入)
不動産投資は、物件を購入して賃貸収入を得る方法です。賃貸物件として貸し出すことで、定期的に家賃収入が得られます。初期費用がかかりますが、安定した収入源を確保できる可能性が高いです。
物件の立地や管理方法によって収益が大きく変わるため、慎重に物件選びを行うことが成功のカギです。また、不動産の価格が上昇すれば、将来的に物件を売却することでも大きな利益を得られる可能性があります。賃貸管理を代行してくれる業者もあり、手間を減らして安定した収入を得られます。
4.駐車場・スペースの貸し出し
もし自宅に使っていない駐車場や空きスペースがあれば、それを貸し出すことでも収入を得られます。駐車場やスペースを貸し出すサービスを利用することで、安定した収益が期待できます。
とくに都市部では需要が高いため、短期間で収益を上げやすいです。管理が比較的簡単で、手間が少ないため副収入として始めやすい方法です。
駐車場を貸し出す場合、近隣の交通アクセスや需要を事前に調査しておきましょう。スペース貸しは、自宅以外でも空いている土地や施設を貸し出すことで安定収入を得られます。
5.車のシェア(Anyca など)
車を所有している場合、その車をシェアリングサービス(Anycaなど)を利用して貸し出すことができます。車を使っていない時間帯や日常的にシェアすることで、レンタル料金を収入として得ることが可能です。
自分の車を最大限に活用できるため、無駄なコストを削減しつつ収益化できる方法です。車のメンテナンスが必要なことや保険の確認など、事前にしっかりと準備をすることが求められます。
また、シェアする車が清潔で整備されていると、利用者からの評価も高まり、安定した収益を得られるでしょう。シェアリングサービスの中には、特定のプラットフォームで人気が高い車両にはプレミアム料金がつく場合もあります。
6.不用品の売却
不要になった物をフリマアプリ(メルカリなど)やオークションサイトで売却することで、手軽に収入を得られます。使っていない洋服や家具、家電製品などを売るだけで、意外な収益が得られることも少なくありません。
物を整理できるだけでなく、売却後の生活空間もスッキリとします。売りたい物が多ければ、一度に大量に処分して収益化することも可能です。
また、不用品を販売する際に、写真や説明を丁寧にすることで、購入者の信頼を得やすくなります。自分が使わない物を有効活用できるので、無駄を減らすことにもつながります。
7.ポイ活
ポイ活とは、ポイントサイトを活用してポイントを貯め、現金やギフト券に交換する活動のことです。買い物やアンケート回答、アプリのダウンロードなどでポイントを獲得できます。
手軽に始められ、特別なスキルがなくても誰でもできる点が魅力です。少しの手間で貯めたポイントを現金化すれば、副収入として活用できます。
ポイントサイトによっては、紹介制度を活用してさらにポイントを増やすことも可能です。ポイントの使い道も広がり、現金以外にも旅行券や商品と交換することができ、ライフスタイルの充実にも繋がります。
社内副業するときの注意点
社内副業を行う際には、いくつかの注意点があります。副業を始める前に、これらを理解し、トラブルを避けるためにしっかりと準備をすることが重要です。副業は本業とのバランスを取ることが大切ですが、会社との関係を良好に保ちながら進めるためのルールも理解しておく必要があります。
- 会社に許可を得ず副業するとバレる可能性がある
- 副業で得た収入額によっては確定申告が必要になる
- 社内副業が許可されている会社でも事前報告がいる
会社に許可を得ず副業するとバレる可能性がある
多くの企業では、社員が副業をする場合、事前に会社の許可を得ることが義務付けられています。もし、許可を得ずに副業を始めると、社内のチェック体制によってバレる可能性があります。例えば、給与明細や税金の申告内容、または人事異動などで副業が発覚するケースが考えられます。
会社が副業を禁止している場合、発覚すると懲戒処分を受ける可能性もあります。副業を始める前には、必ず自分が所属する会社の就業規則を確認し、必要な手続きを踏むようにしましょう。許可を得ていれば、問題なく副業を行えます。
副業で得た収入額によっては確定申告が必要になる
副業で得た収入が一定額を超えると、確定申告をしなければならない場合があります。具体的には、年間の副業収入が20万円以上であれば、確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、税務署から指摘を受けることがあり、追加で税金を支払わなければならないこともあります。
副業の収入額が少額でも、いずれは本業と合算して税金が引かれる仕組みとなっているため、税務処理を正確に行うことが重要です。副業を行う際には、収入の管理をしっかり行い、必要に応じて確定申告を行う準備をしておきましょう。
社内副業が許可されている会社でも事前報告がいる
社内副業が許可されている企業でも、事前に報告をすることが求められる場合があります。許可制の副業制度では、副業の内容や時間帯、本業への影響を考慮したうえで、上司や人事部門に報告し、承認を得ることが必要です。
この手続きがあることで、副業が本業に支障をきたさないように調整できます。また、許可された副業内容が適切でない場合や、社内規定に違反するような場合は、会社から警告や指導を受けることがあります。副業を始める前には、会社の規定を再確認し、事前に報告を行うことが重要です。
まとめ
社内副業は法律で禁止されていないものの、会社によっては禁止や制限が設けられています。本業への影響や情報漏洩を懸念するケースが多いため、まずは就業規則を確認しましょう。副業が難しい場合でも、投資やスペース貸し出し、不用品販売など収入を得る方法はあります。
どうしても副業したい場合は、副業可能な会社へ転職することも視野に入れておきましょう。

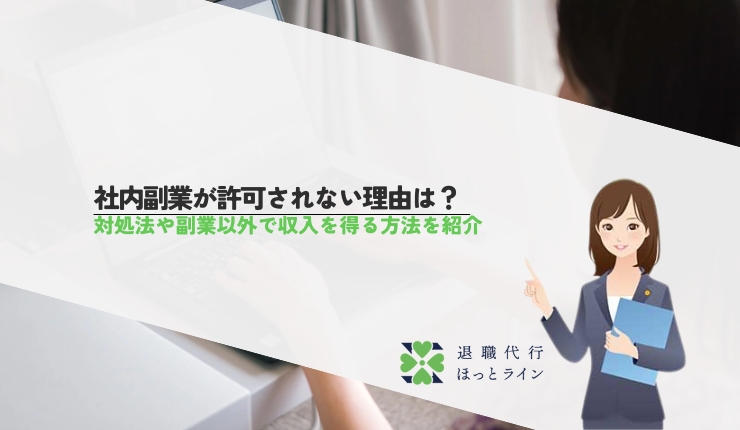

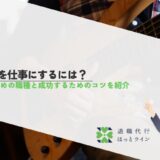

コメントを残す