歓送迎会や社員旅行、忘年会など、業務とは関係のないイベントへの参加が強制である会社もあります。本来、業務時間外の行事への出席は自由であるべきですが、実際には断りにくい雰囲気や、参加を拒否したことで不利益を受けたという声も少なくありません。
本記事では、社内イベントの強制は違法なのか紹介します。また、参加を断る方法や困ったときの相談愚痴も紹介しますので、参考にしてください。
・社内イベントの強制が違法になるケースは、業務時間外・休日に強制参加させられる、参加しないと不利益を受けるなど
・社内イベントの強制が違法にならないケースは、労働時間に当てはまる場合、残業代が支払われる場合
・社内イベントへの参加を強制させられるときの断り方・対処法は、業務命令か任意参加なのか確認する、体調不良や業務上の都合で断るなど
目次
社内イベントの強制が違法になるケース
社内イベントへの参加は、あくまで任意であるべきです。企業が業務の一環として開催することはあっても、法的に参加を強制できるものではありません。とくに、休日や業務時間外に無理やり出席を求めたり、参加を拒否した社員に対して不利益を与えるような行為は、違法と見なされる可能性があります。
どのようなケースが違法となり得るのかを具体的に見ていきましょう。
- 業務時間外・休日に強制参加させられる
- 社内イベントを断ることができない雰囲気・圧力がある
- 社内イベントに参加しないと不利益を受ける
- 社内イベントでセクハラ・パワハラが発生する
業務時間外・休日に強制参加させられる
業務時間外や休日に行われる社内イベントに対し、強制的に参加を求める行為は違法とされる可能性があります。社員のプライベートな時間を侵害することになり、労働基準法違反と見なされる場合があるからです。
また、休日に行われるイベントに出席した場合、会社は労働時間として計算しなければなりません。会社の指示で参加しなければならず、実質的に業務と同じ扱いであれば、時間外労働として割増賃金の支払い義務が発生します。
このような点からも、社員の自由意思に基づかない社内イベントへの強制参加は、法的リスクを伴います。参加するかどうかは、あくまで本人が決めるべきものですので、無理に参加しなくても構いません。
社内イベントを断ることができない雰囲気・圧力がある
社内イベントを断りづらいと感じる背景には、職場特有の暗黙のルールや人間関係のプレッシャーがあります。表向きは自由参加とされていても、実際には上司や先輩の視線、周囲の同調圧力によって、断る選択肢がないように感じてしまうことも少なくありません。
例えば「みんな来てるのにどうして来ないの?」といった言葉や、参加して当たり前といった空気感に圧倒され、気が進まなくても参加せざるを得ないというケースもあります。業務とは直接関係のないイベントであっても、職場での評価や人間関係に影響しそうだと不安になり、無理をして出席する人も多いでしょう。
とくに、新入社員や若手社員にとっては、空気を読むことが求められる雰囲気の中で、自分の意思を通すのは容易ではありません。
社内イベントに参加しないと不利益を受ける
社員が社内イベントに参加しなかったことを理由に、人事評価を下げたり昇進に影響させたりするのは明らかに不当です。イベントの出欠が業務に直接関係ない以上、評価や待遇に影響を与えることは法律上問題があります。
例えば、社内イベントに参加しなかったから昇進に響いた、ボーナスの査定に影響したなどがあれば違法な可能性があります。ただし、具体的な評価基準や不利益を受けた証拠がなければ違法性を訴えることは難しいでしょう。
たとえ任意参加であっても、不参加によって不利益を被るのであれば、それは実質的な強制に近い状況といえます。
社内イベントでセクハラ・パワハラが発生する
社内イベントの場では、業務時間中とは異なり緊張感が緩和されるため、ハラスメントにつながるリスクを高めます。とくに飲み会のようにアルコールが入る場では、言動のハードルが下がりやすく、セクハラやパワハラの温床となることもあります。
例えば、身体的な接触や容姿へのコメント、恋愛に関する発言など、普段の業務中にはありえないような行為が、冗談として処理されるケースが少なくありません。上司や先輩の立場を利用した無理な誘い、断れない雰囲気での過剰な要求なども、ハラスメントに該当する可能性が高いです。
社内イベントでのハラスメントは、被害者の心身に深刻なダメージを与えるだけでなく、その後の職場生活に悪影響を及ぼします。たとえ業務外の時間であっても、関係者間のトラブルは職場の問題として扱うべきです。
社内イベントの強制が違法にならないケース
社内イベントの強制がすべて違法になるわけではありません。会社が適切な対応を取っていれば、企業活動の一環として認められることもあります。ここでは、社内イベントの強制が違法とされにくい代表的なケースを紹介します。
- 業務時間内に実施され労働時間に当てはまる場合
- 業務時間外であっても残業代が支払われる場合
業務時間内に実施され労働時間に当てはまる場合
社内イベントが業務時間内に実施され、かつその時間が正式な労働時間として扱われている場合は違法とはなりません。例えば、平日の午前中に会議室で行うレクリエーションや研修の一部として開催される行事などがこれに該当します。
このようなケースでは、イベントも含めて業務として取り扱われるため、参加すること自体が勤務の一環です。したがって、従業員にとっては通常の業務を行うのと同様に、会社の指示に従う義務が生じます。
また、給与が発生しており、拘束時間が明確である場合には、法的な問題になりにくいのが一般的です。ただし、業務の範囲を超えるような過度な飲酒を強要される、プライバシーを侵害されるような内容が含まれる場合には、別の問題として扱われます。
重要なのは、そのイベントが正当に労働時間として計上されているかどうかです。
業務時間外であっても残業代が支払われる場合
イベントが業務時間外に行われたとしても、その時間が労働時間として認められ、残業代が支払われている場合には、法律違反とはなりにくいです。例えば、社内研修や営業会議に準ずる形で行われるイベントに強制参加が求められたとしても、適切に時間外手当が支給されていれば、労働基準法上の問題は少なくなります。
労働時間の定義は、会社の指揮命令下にある時間です。つまり、業務としての参加が明確であり、その対価が支払われていれば、法的には労働として成立します。逆に、イベントへの参加を強制されながら、賃金が発生しない場合は、違法となる可能性が出てきます。
ここでのポイントは、会社がイベントの性質を明確にし、対価としての賃金をきちんと支払っているかどうかです。社員が自発的に参加しているように見えても、実質的には業務命令であるなら、当然ながら残業代が発生するべきです。
残業代が支払われないときは、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:残業代が計算されない理由は?未払いの残業代を請求する方法を解説
社内イベントへの参加を強制させられるときの断り方・対処法
社内イベントは、基本的に自由参加であるべきです。しかし、実際には圧力がある職場も少なくありません。ここでは、参加を強制されたときに取るべき対応や、断り方の具体例を紹介します。
- 業務命令か任意参加なのか確認する
- 体調不良を理由に断る
- 業務上の都合を理由にして断る
- 断ったことで不利益を受けた場合は記録を残す
- 参加を強制するようなブラック企業であれば退職も検討する
業務命令か任意参加なのか確認する
最初に確認すべきことは、そのイベントが業務命令か任意参加かどうかです。上司や人事からの案内に、明確な表現がない場合は、遠慮せず質問しましょう。「このイベントは業務に含まれますか?」「参加は自由ですか?」と確認するだけでも、自分の立場を明確にできます。
企業によっては、任意参加としながらも実際には出席が強く求められる場合があります。そのような場合、表向きの案内と実態にズレが生じている可能性があるため注意が必要です。
業務命令であると明示された場合は、労働時間や賃金の扱いがどうなるのかも併せて確認してください。時間外での参加を求められているなら、残業代の対象かどうかを聞いておくことが自分を守る手段になります。
体調不良を理由に断る
社内イベントを断る際の理由として、体調不良は比較的使いやすい方法の一つです。とくに精神的なストレスや人間関係の悩みで参加を避けたいときも、体調が優れないと伝えれば深く追及されにくくなります。
体調の悪さは本人にしかわからないものであり、上司や同僚が強引に理由を否定することは難しいです。また、無理をして参加した結果、体調がさらに悪化すれば会社側のリスクにもつながります。そのため、「今日は少し具合が悪くて…」と伝えるだけでも、相手に納得してもらいやすい傾向があります。
ただし、毎回同じ理由を使うと信ぴょう性に欠けてし舞うので気を付けましょう。あくまで自然な流れで使い、場合によっては別の理由で断るようにしましょう。
業務上の都合を理由にして断る
仕事の都合を理由にイベントを断る方法も有効です。例えば「急ぎの案件があり、どうしても残業が必要です」「取引先との調整が入ってしまいました」といった業務に関する事情であれば、比較的理解を得やすいです。
ただし、体調不良は本人しかわからないことですが、業務上の都合は会社も把握できることです。そのため、実際に仕事が溜まっている、取引先から対応を求められているといった状況にならなければ理由として使えません。
断ったことで不利益を受けた場合は記録を残す
社内イベントを断ったことによって、業務上の不利益を受けた場合は、その状況を詳細に記録しておきましょう。例えば、上司からの評価が下がった、仕事を回してもらえなくなった、明らかに上司からの対応が変わった、などの変化が見られたときは、日付や内容をメモに残しておくことが重要です。
証拠として有効なのは、メールやチャットなどのやり取りです。業務に関連する不当な扱いがあれば、スクリーンショットを取るなどして記録を残しておくことで、後に労働相談窓口などへ相談する際にも役立ちます。
また、メモにはできるだけ客観的な内容を記すように心がけてください。「イベントを断った翌日から挨拶を無視されるようになった」「担当業務が他の人に引き継がれた」など、具体的な行動を記録しておくと信頼性が高まります。
証拠集めに関しては、以下の記事が参考になりますので、ぜひご確認ください。
関連記事:パワハラの証拠集めはどうする?注意点とポイントをわかりやすく解説します
参加を強制するようなブラック企業であれば退職も検討する
社内イベントへの参加をあからさまに強制し、不参加によって不利益を与えるような職場は、ブラック企業の傾向が強いといえます。こうした環境では、イベントに限らず日常業務でもハラスメントや労基法違反が横行している可能性が高いです。
プライベートの時間まで会社に拘束される、自由に断ることすら許されないなどの状況が続いているなら、その職場環境自体を見直す必要があります。
とくに、上司や会社全体が強制を当然と考えている場合は、改善を求めても状況が変わりにくいのが実情です。そのようなときは、無理に環境に適応しようとするよりも、自分自身を守ることを最優先に考えるべきです。
退職や転職は大きな決断ですが、ブラックな環境から抜け出す手段として正当な選択です。限界を感じたら、新しい職場を視野に入れて動き出しましょう。ブラック企業の見極め方については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:ブラック企業の見極め方とは?ブラック企業の特徴や転職を成功させるポイントを解説
社内イベントが強制参加でつらい!無料の相談窓口
社内イベントへの強制参加が精神的につらいと感じたときは、一人で抱え込まず外部の相談窓口を頼ることが大切です。職場に直接言いづらい場合でも、無料で相談できる公的機関や専門団体があります。ここでは、強制参加の悩みを安心して相談できる4つの窓口を紹介します。
- 総合労働相談コーナー
- 労働基準監督署
- みんなの人権110番
- 労働組合
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、厚生労働省が全国の労働局や労働基準監督署に設置している無料の相談窓口です。労働条件や職場環境に関する幅広い悩みに対応しており、社内イベントの強制に関する相談も可能です。
労働問題の専門知識を持った相談員が対応してくれます。匿名での相談も可能なので、職場に情報が伝わることはありません。電話・面談・オンラインのいずれかを選べるため、状況に応じて利用しやすいのも特徴です。
強制参加によって残業代が出ていない、精神的に追い詰められているといった場合には、法的な観点から助言を受けられます。また、必要に応じて労働基準監督署への取り次ぎも行われるため、初期相談の窓口としても安心です。
労働基準監督署
強制参加によって労働基準法違反が疑われる場合は、労働基準監督署への相談が適しています。労働基準監督署は、企業が法令を遵守しているかを監督する公的機関で、必要に応じて企業への調査や指導が可能です。
例えば、業務時間外のイベントに参加を強いられたにもかかわらず、残業代が支払われていないケースや、参加しないことで不利益を受けた場合は、労基法違反となる可能性があります。こうした状況に心当たりがある場合は、証拠やメモを持参して相談してみましょう。
相談は無料で、匿名でも受け付けています。直接窓口に出向くほか、電話での相談も可能です。自分の勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署を調べてから連絡するとスムーズです。
みんなの人権110番
みんなの人権110番は、法務省が設置している人権問題の相談窓口です。職場での差別やハラスメント、自由の侵害など、人権に関わるトラブル全般を対象としています。
社内イベントの強制が、個人の思想・信条の自由を侵害している、または同調圧力によって精神的苦痛を受けていると感じる場合には、みんなの人権110番に相談してみるとよいでしょう。相談内容によっては、人権侵犯として調査・対応が行われることもあります。
相談は電話で受け付けており、平日のみの対応となっています。
労働組合
職場に労働組合が存在する場合は、組合への相談も有効です。労働組合は労働者の権利を守るための組織であり、不当な強制や圧力に対して交渉や是正を求めることが可能です。
例えば、イベントへの参加が実質的に義務化されていたり、参加しないことで評価に影響が出るような状況であれば、組合を通じて会社と交渉できます。また、個人では難しい問題も、組織の力を借りることで改善につながる可能性が高まります。
職場に労働組合がない場合でも、外部の「合同労組(ユニオン)」に加入して相談することも可能です。地域ごとのユニオンは、業種や職場に関係なく加入でき、強制参加の問題にも対応しています。労働組合に相談できることについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説
社内イベントへの強制に関するよくある質問
社内イベントへの強制に関するよくある質問を紹介します。
- 社内イベントへ強制参加させられたのに残業代が支払われないときは?
- 社内イベントはそもそも時代遅れ?
- 社内イベントがくだらないといわれる理由は?
社内イベントへ強制参加させられたのに残業代が支払われないときは?
業務時間外の社内イベントに強制参加させられたにもかかわらず、残業代が支払われない場合は、労働基準法違反に該当する可能性があります。会社がイベントを業務の一部として事実上強制しているのであれば、その時間は労働時間と見なされます。
その場合、残業代が発生するのが原則です。
対応としては、まずイベントが任意なのか業務命令なのかを確認することが重要です。そのうえで、タイムカードやメール記録など、参加状況がわかる証拠を残しておくと安心です。支払われない残業代については、労働基準監督署へ相談することで解決の糸口が見つかります。
社内イベントはそもそも時代遅れ?
最近では、「社内イベント=時代遅れ」と感じる人が増えています。とくに若い世代や、ワークライフバランスを重視する働き方が浸透するなかで、プライベートの時間を削ってまで参加するイベントに疑問を抱く人は少なくありません。
昭和〜平成初期にかけては、社員旅行や飲み会などを通じた結束が重視されていました。しかし現在は、仕事とプライベートの線引きを明確にしたいと考える人が多く、無理に交流を深める文化に違和感を覚える人もいます。
社内イベントがくだらないといわれる理由は?
「社内イベントがくだらない」と感じる理由の多くは、イベント内容が個々の価値観に合っていない、あるいは時間の無駄と感じることにあります。例えば、業務に直結しないゲームやレクリエーションを無理に行ったり、上司の自己満足的な企画が多い場合、参加者にとっては苦痛でしかありません。
また、イベントの目的が不明確なことも問題です。単なる形式的な開催では、参加者のモチベーションも上がらず、不満につながります。さらに、仕事以外の時間にまで職場の人間関係に縛られることが、精神的ストレスとなっているケースもあります。
まとめ
社内イベントへの強制参加は、必ずしも違法とは言い切れません。状況により違法であるか異なるからです。主に違法に当たる場合は、以下の通りです。
- 業務時間外・休日に強制参加させられる
- 社内イベントを断ることができない雰囲気・圧力がある
- 社内イベントに参加しないと不利益を受ける
- 社内イベントでセクハラ・パワハラが発生する
社内イベントへの強制参加を促されたときは、業務時間内か、労働時間に含まれるか、業務時間外であれば残業代が発生するかといったことを確認しましょう。違法であるにもかかわらず、強制参加を求める場合はブラック企業の可能性があります。
労働環境を見直し、場合によっては転職・退職も視野に入れましょう。退職に関する悩みや不安がある場合は、退職代行ほっとラインへご相談ください。


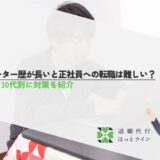
コメントを残す