退職代行サービスを利用すれば、引き継ぎが不要になると思っている人は多いのではないでしょうか。退職代行を利用すれば、引き継ぎの交渉ができるので不要になる可能性を高められます。しかし、必ずしも不要にできるとは限りません。
退職代行を使っても引き継ぎしたほうがいいケースもあります。そこで本記事では、退職代行を使えば引き継ぎ不要で辞められるのか、引き継ぎしたほうがいいケースなどを紹介します。
・退職代行を使えば引き継ぎ不要で退職できる
・退職代行を使っても引き継ぎしたほうがいいケースは、重要なプロジェクトを担当している、取引先との関係が深い、就業規則に引き継ぎに関する規定があるなど
・引き継ぎせずに退職することに不安を感じる場合は、退職代行に引き継ぎの範囲を交渉してもらう、簡易的な引き継ぎ書類を作っておくなど
目次
退職代行を使えば引き継ぎ不要で辞められる?その理由は?
退職代行サービスを利用すると、会社に直接出向くことなく退職手続きを進めることが可能です。しかし、引き継ぎをしなくても問題ないのかと不安に感じる人も多いでしょう。そこで退職代行を利用することで引き継ぎが不要になる理由について、法律の観点から詳しく解説します。
- 引き継ぎは法律で定められていないから
- 法律上では2週間前に退職意思を伝えれば辞められるから
引き継ぎは法律で定められていないから
退職時の引き継ぎは、会社にとって重要な業務ですが、法律上の義務ではありません。民法では労働者が退職する際のルールが定められていますが、引き継ぎをしなければならないとは明記されていません。
企業は業務をスムーズに継続させるため、退職者に引き継ぎを求めるのが一般的ですが、これは法律上の義務ではなく、あくまで企業側の希望です。そのため、退職代行を利用して会社と直接やり取りをせずに退職する場合でも、引き継ぎをしなくても法的な問題にはなりません。
ただし、就業規則に退職時には引き継ぎすること、といった規定がある場合があります。この場合、引き継ぎをしなければトラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。しかし、最終的には労働者が会社に残るかどうかの決定権を持っており、会社が強制的に引き継ぎを求められません。
法律上では2週間前に退職意思を伝えれば辞められるから
民法第627条では、労働者は退職の意思を2週間前に伝えれば退職できると定められています。つまり、雇用契約の内容にかかわらず、会社に退職意思を示してから2週間が経過すれば、法的には退職が可能です。
この法律により、退職代行を利用して退職意思を会社に伝えれば、2週間後には正式に退職が完了します。たとえ会社が引き継ぎが終わるまで認めないと主張しても、法律上は労働者の退職を阻止できません。
ただし、退職時のトラブルを避けるためには、就業規則や雇用契約の内容を事前に確認し、円満に退職できるよう準備することが大切です。退職代行を利用する場合でも、できるだけ円滑に業務を引き継ぐ工夫をすることで、不要なトラブルを避けられるでしょう。
退職代行を使っても引き継ぎしたほうがいいケースもある
退職代行を利用すると、会社と直接のやり取りをせずに退職できるというメリットがあります。しかし、すべてのケースで引き継ぎが不要というわけではありません。とくに、会社や取引先に大きな影響を与える可能性がある場合は、適切な引き継ぎを行ったほうが良いでしょう。
- 重要なプロジェクトを担当している場合
- 取引先との関係が深いポジションの場合
- 自分しか把握していない業務がある場合
- 就業規則に引き継ぎに関する規定がある場合
重要なプロジェクトを担当している場合
退職時に重要なプロジェクトを担当している場合、適切な引き継ぎを行わないと、プロジェクトの進行が滞るリスクがあります。とくに、締切が迫っているプロジェクトや、クライアントと密接に関わる案件では、急な退職による混乱が大きな問題になりかねません。
プロジェクトの進行状況や今後のスケジュールを整理し、後任者がスムーズに業務を引き継げるように準備をすることが重要です。最低限、現在のタスクの進捗や関係者との連携方法をまとめた資料を残すと、引き継ぎの負担を軽減できます。
また、プロジェクトに関する専門知識やノウハウを持っている場合、それを口頭や文書で共有することが必要です。これを怠ると、退職後に問い合わせを受ける可能性があり、思わぬ手間が発生するかもしれません。退職代行を利用しても、できる範囲での引き継ぎすることで、円満退職につながるでしょう。
取引先との関係が深いポジションの場合
取引先との関係が深いポジションに就いている場合、適切な引き継ぎを行わずに退職すると、会社や取引先に混乱を招く恐れがあります。営業職やカスタマーサポートなど、顧客と直接やり取りをする仕事では、担当者の変更がスムーズに行われないと、信頼関係の悪化につながる可能性があります。
取引先によっては、担当者の交代を事前に伝えないことで無責任な対応と見なされ、企業の評価が下がることも少なくありません。引き継ぎしないことで重要な取引先との関係債が悪化すれば、損害賠償を請求される可能性もあります。
そのため、最低限の引き継ぎを行い、新しい担当者の紹介や業務の移行をスムーズに進めることが重要です。
また、取引先から個人的に信頼を寄せられている場合、退職後に直接連絡が来るケースもあります。そうした事態を避けるためにも、事前に後任者を紹介し、適切な引き継ぎを済ませることが望ましいでしょう。
自分しか把握していない業務がある場合
業務の中には、特定の担当者しか詳しく把握していないものもあります。例えば、社内システムの管理や特定のクライアント対応、独自の業務フローなど、自分にしかわからない業務を抱えている場合、適切な引き継ぎを行わないと、会社へ与える損害が大きいでしょう。
中小企業やスタートアップでは、一人の担当者に業務が集中していることが多く、急な退職によって業務が停滞するリスクが高まります。こうした状況を避けるためにも、業務のマニュアル化や、後任者への引き継ぎを事前に準備することが重要です。
引き継ぎを怠ると、会社側から損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。実際に、業務の滞りが原因で会社に損害が発生した場合、法的なトラブルに発展するケースもあります。退職代行を利用する場合でも、自分が担当している業務の重要性を見極め、適切な引き継ぎを行うことで、退職後のリスクを減らせられます。
就業規則に引き継ぎに関する規定がある場合
企業の就業規則には、退職時の引き継ぎに関する規定が設けられていることがあります。例えば、退職の〇日前までに引き継ぎを完了することや、退職時には業務マニュアルを作成することなど、具体的なルールが定められている場合があります。
こうした規定を無視して退職すると、最悪の場合、懲戒処分や退職金が支払われないといったトラブルに発展する可能性も少なくありません。実際に、引き継ぎをせずに退職したことで会社側が業務に支障をきたし、法的措置を取られた事例も存在します。
退職代行を利用する場合でも、事前に就業規則を確認し、引き継ぎに関する規定があるかどうかをチェックすることが重要です。もし引き継ぎが義務付けられている場合は、最低限の引き継ぎを行うことで、トラブルを回避できるでしょう。
退職代行を使って引き継ぎ不要で辞めるリスク
退職代行を利用して引き継ぎを行わずに退職すると、リスクが生じる可能性があるため注意が必要です。退職後にトラブルへ発展するケースもあり、最悪の場合、懲戒処分を科されることも考えられます。リスクを踏まえた上で、引き継ぎするかしないかを判断しましょう。
- 民間業者では引き継ぎの交渉ができない
- 職場や取引先に迷惑がかかる
- 会社から損害賠償請求される可能性もある
民間業者では引き継ぎの交渉ができない
退職代行サービスは、依頼者に代わって会社へ退職意思を伝えますが、民間業者では引き継ぎの交渉を行えません。これは、退職代行業者が弁護士資格を持たない場合、法的な交渉ができないためです。そのため、民間業者の退職代行を使って退職する場合は、基本的に会社と本人が直接対応する必要があります。
退職代行を使って引き継ぎ不要の交渉をしたいときは、弁護士が運営しているサービスや弁護士と連携しているサービスを利用しましょう。
職場や取引先に迷惑がかかる
引き継ぎをせずに退職すると、会社の業務が滞るだけでなく、職場の従業員や取引先にも大きな迷惑をかけることになります。業務上の重要な役割を担っている場合、急な退職によって周囲にかかる負担は大きいです。
例えば、特定のプロジェクトを担当している場合、突然抜けることでスケジュールが遅れ、チーム全体の負担が増大します。また、取引先との関係が深い職種では、担当者の交代をスムーズに行わないと、取引先との信頼関係が失いかねません。
職場内で引き継ぎもせずに突然辞めた人として悪い印象を持たれると、将来的に同じ業界で転職を考えた際に不利になる可能性もあります。業界内で情報が共有されることもあるため、とくに狭い業界では注意が必要です。
退職代行を利用する場合でも、最低限の引き継ぎを行い、同僚や取引先に不要な負担をかけないようにする配慮が大切です。円満退職を心がけることで、退職後も良好な関係を維持できるでしょう。
会社から損害賠償請求される可能性もある
引き継ぎをせずに退職すると、会社の業務に支障をきたし、損害が発生することがあります。その結果、会社から損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。しかし、実際のところ損害賠償を請求されるケースは多くありません。
損害賠償請求が認められるかどうかは、会社が実際にどの程度の損害を被ったかによります。例えば、重要な取引が破談になった、プロジェクトが遅延して違約金が発生したといった具体的な損害が発生した場合、会社はその損害を補填するために法的手段を取ることがあります。
損害賠償を請求されなかったとしても、就業規則に違反していれば、懲戒処分のリスクがあるので注意が必要です。
退職代行を使えば引き継ぎ不要!でも心配な人がトラブルを避けるなら
退職代行を利用すれば引き継ぎ不要で退職できます。しかし、引き継ぎをせず退職することはリスクを伴います。心配な人は少しでもトラブルを避けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 可能な範囲で引き継ぎする
- 退職代行に引き継ぎの範囲を交渉してもらう
- 簡易的な引き継ぎ書類を作っておく
- 自分の業務を終わらせて引き継ぎする量を減らす
可能な範囲で引き継ぎする
退職代行を利用する場合でも、最低限の引き継ぎを行うことで、トラブルを軽減できます。すべての業務を細かく引き継ぐのが難しくても、重要な業務や自分にしか分からない業務だけでも共有しておくと、会社も納得しやすいです。
例えば、担当しているプロジェクトの進捗状況や、取引先とのやり取りの記録などを簡単にまとめるだけでも、後任者の負担を減らせます。また、業務のマニュアルや手順書がある場合、それを共有するだけでも引き継ぎの手間を大幅に減らせるでしょう。
退職代行に引き継ぎの範囲を交渉してもらう
退職代行を利用する際、業者によっては引き継ぎする範囲を交渉してもらえます。弁護士が運営する退職代行サービスでは、法律の範囲内で会社との交渉を行えるため、引き継ぎの方法についても相談しやすいです。
民間の退職代行業者は、基本的に退職意思を伝えることが主な業務ですが、引き継ぎに関する伝達は可能です。例えば、後任者へ引き継ぎ資料を渡してほしい、退職日までにやるべき業務を整理して伝えたいといった要望がある場合、代行業者に相談するとスムーズに進められます。
ただし、業務の詳細な引き継ぎ交渉は、弁護士資格を持たない民間業者では対応できません。そのため、引き継ぎに関する具体的な条件交渉が必要な場合は、弁護士監修の退職代行を利用するのが安心です。適切な退職代行サービスを選ぶことで、引き継ぎに関するトラブルを防げます。
簡易的な引き継ぎ書類を作っておく
引き継ぎを円滑に進めるためには、簡易的な引き継ぎ書類を作成しておくことが有効です。文書にまとめておけば、直接引き継ぎを行わなくても、後任者が業務を把握しやすくなります。引き継ぎ書類には、以下のような内容を含めると効果的です。
- 業務の概要と担当範囲
- 進行中の業務のステータス
- 使用しているシステムやツールの情報
- 取引先や社内の関係者の連絡先
- よくある業務のトラブルと対処法
書類の作成は、すべてを細かく記載する必要はなく、ポイントを簡潔にまとめるだけでも十分です。また、すでに社内に業務マニュアルがある場合は、その参照先を記載するだけでも、後任者の負担を軽減できます。
自分の業務を終わらせて引き継ぎする量を減らす
引き継ぎをスムーズに進めるためには、退職前にできる限り自分の業務を終わらせておくことが大切です。業務が中途半端な状態で退職すると、後任者の負担が増え、会社に迷惑をかけることになります。以下のような対応を取ることで、引き継ぎの負担を減らせます。
- 進行中の業務を完了させる
- 期限のある仕事を前倒しで終わらせる
- 未処理のタスクを整理して、後任者が対応しやすい状態にする
社内でしか対応できない業務がある場合、退職日までに完了させておくことで、退職後に会社から連絡を受けるリスクを減らせます。とくに、顧客対応やシステム管理など、自分が担当していた業務が止まると会社に影響を与えるようなものは、できるだけ終わらせておくことが望ましいです。
退職代行を利用した引き継ぎに関するよくある質問
退職代行を利用した引き継ぎに関するよくある質問を紹介します。
- 退職代行を利用した場合、引き継ぎは絶対にしなくていいの?
- 退職代行利用後に、会社から「引き継ぎのために出社してほしい」と言われたら?
- 引き継ぎが難しい場合、最低限やっておくべき対応は?
- 退職代行の利用におすすめの人は?
- 退職代行を利用して退職までの流れは?
退職代行を利用した場合、引き継ぎは絶対にしなくていいの?
退職代行を利用したからといって、必ずしも引き継ぎが不要になるわけではありません。法律上、退職に際して引き継ぎを義務付ける規定はありませんが、会社の就業規則に退職時の引き継ぎを求める内容が明記されている場合、それを無視するとトラブルになる可能性があります。
また、引き継ぎをせずに退職すると、会社や同僚に大きな負担をかけることになり、退職後に連絡が来るケースも考えられます。退職代行を利用する場合でも、可能な範囲で引き継ぎを行うことがおすすめです。最低限、業務内容や担当していた案件の進捗状況を簡単にまとめておくなど、後任者が困らないよう配慮しましょう。
退職代行利用後に、会社から「引き継ぎのために出社してほしい」と言われたら?
退職代行を利用して退職意思を伝えた後、会社から引き継ぎのために出社してほしいと求められるケースがあります。この場合、対応方法を慎重に検討することが大切です。
どうしても出社したくない場合は、退職代行業者に引き継ぎについて直接対応しないことを伝えてもらうことも可能です。また、出社は難しくても、メールや書面で最低限の業務情報を伝えるなど、代替手段を検討するのもよいでしょう。
少しでもトラブルを避けたい場合は、可能な範囲内で会社に協力する姿勢を見せることです。
引き継ぎが難しい場合、最低限やっておくべき対応は?
退職後のトラブルを避けるために、最低限の対応を行っておくことが望ましいです。例えば、以下のような対応を取っておきましょう。
- 業務の進捗状況を簡単にまとめる
- 後任者が困らないよう最低限の情報を整理する
- 取引先や関係者の情報を共有する
- メールや書類で簡単な引き継ぎメモを作成する
退職代行の利用におすすめの人は?
退職代行を利用したほうがいい人には、以下のような人です。
- 会社と直接やり取りをしたくない人
- 上司の引き止めが厳しく、辞めたいと言い出せない
- 退職を伝えるのが精神的に負担になっている
- 職場に行かずに退職したい人
- 退職意思を伝えた後、会社に行かなくて済むようにしたい
- 残業代未払い、パワハラ、長時間労働が常態化している
- 退職を申し出ても受理されるか不安がある
- できるだけ早く退職し、新しい仕事に移りたい
- 退職の手続きを自分で進めるのが面倒に感じる
退職代行を利用して退職までの流れは?
退職代行を利用して退職する場合、一般的な流れは以下の通りです。
- 退職代行業者に相談
- 契約・支払い
- 退職の連絡を代行業者が実施
- 退職完了
まずは退職代行サービスへ相談しましょう。希望する退職日や料金、サービス内容を確認して依頼するか判断します。利用する退職代行業者が決まれば、契約を交わしたうえで料金を支払います。
そのあとは基本的に会社と直接連絡を取ることはありません。代行サービスが依頼者の希望を汲みながら退職手続きを進めます。会社からの連絡はありませんが、代行サービスから連絡は来ますので、返事ができるようにしておきましょう。
退職代行サービスを利用しても会社から直接連絡が来るなど、トラブルが生じる可能性はゼロではありません。どのようなトラブルがあるのか、以下の記事を参考に把握しておくと良いでしょう。
関連記事:退職代行でよくあるトラブル事例15選!リスクを避けて確実に辞めるにはどうしたらいい?
まとめ
退職代行サービスを利用すれば、引き継ぎ不要で退職することは可能です。ただし、引き継ぎせずに退職することは、リスクを伴うことも覚えておきましょう。退職代行は、引き継ぎ以外にも役立つサービスです。退職手続きを代行してもらうことで、転職先の準備に専念したり、精神的苦痛から解放されたりなどメリットが多くあります。
退職代行ほっとラインでは、ご依頼者様が無事に退職されるまで全力でサポートします。弁護士とも連携していますので、専門的なサポートも可能です。まずは退職に関する悩みをご相談ください。

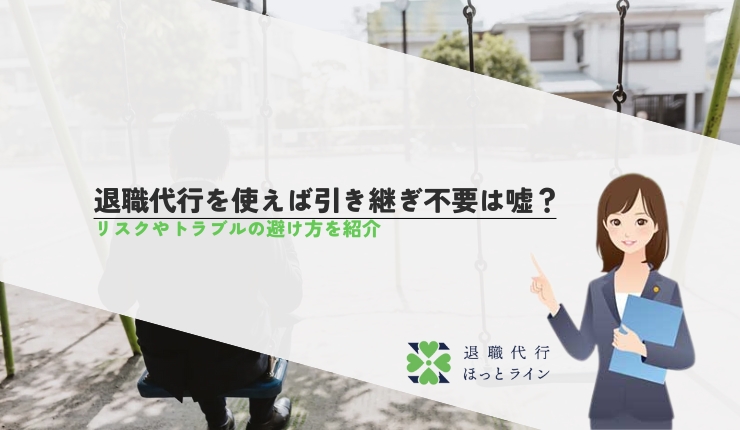


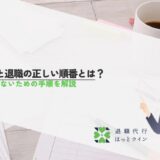
コメントを残す