新型コロナウイルスの影響を受けて、多くの企業がリモート勤務(テレワーク)を導入しました。しかし、状況が改善される中で、リモート勤務を廃止し、出社を強制する企業も増えています。
出社しなくても良いことに魅力を感じて入社したのに、突然リモート勤務を廃止されるのは違反だと感じる人も多いのではないでしょうか。本記事では、リモート勤務廃止は拒否できるのか紹介します。また、リモート勤務廃止が増加する理由や出社強制への対処法について解説していますので、参考にしてください。
・リモートワーク(テレワーク)を実施する企業は14.6%
・リモート勤務廃止する企業が増えている理由は、通信環境や物理的環境を整えるのが難しい、仕事のオン・オフを切り替えるのが難しいなど
・リモート勤務廃止を拒否できる条件は、リモート勤務限定の雇用契約を結んでいる、廃止が合理的ではないなど
・リモート勤務廃止による出社強制への対処法は、廃止が妥当か判断する、会社に交渉する、団体交渉を行う(労働組合がある場合)など
目次
リモート勤務廃止の背景と増加する理由
リモート勤務(テレワーク)は、コロナ禍で一時的に多くの企業で導入されました。しかし、現在ではその廃止を決定する企業も増えています。リモート勤務を継続するためには、さまざまな条件をクリアする必要があるため、企業側は実施においてさまざまな課題を抱えていることが分かります。
- リモートワーク(テレワーク)を実施する企業は14.6%
- Wi-Fiなどの通信環境の整備を整えるのが難しい
- 物理的環境の整備を整えるのが難しい
- 職場に行かないとできない業務がある
- 仕事のオン・オフを切り替えるのが難しい
- コミュニケーションが不足してしまう
リモートワーク(テレワーク)を実施する企業は14.6%
公益財団法人日本生産性本部が2025年1月に発表した「第16回 働く人の意識調査」によると、リモートワーク(テレワーク)を実施している企業は14.6%です。リモートワークの実施率は年々減少しており、今回の調査では過去最低となる結果になりました。
リモートワークの実施率が高かったのは、新型コロナウイルスが流行した2020年5月です。31.5%の企業がリモートワークを導入しており、その差は16.9%に及びます。なお、リモートワークは従業員規模によって実施率が異なります。従業員100名以下の会社は実施率9.7%に対し、1,001名以上は25.6%です。
このようにリモートワークを廃止する企業が増えています。次は、リモートワークを廃止する企業が増えている理由について紹介します。
参考元:公益財団法人日本生産性本部|第16回 働く人の意識調査
Wi-Fiなどの通信環境の整備を整えるのが難しい
リモート勤務を導入するためには、社員一人ひとりが快適に働ける通信環境を整える必要があります。しかし、全社員に対して高品質なインターネット環境を提供することは企業にとって大きな負担となります。とくに地方に住んでいる社員の場合、高速なWi-Fiを整えることが難しいです。
また、リモートワーク用の専用機材やセキュリティ対策を取ることが必要になるため、費用や時間をかけて準備を整える必要があります。このような環境整備が企業の負担となり、リモート勤務廃止の理由となっていることが少なくありません。
物理的環境の整備を整えるのが難しい
リモート勤務には、快適に作業を行うための物理的な作業環境も重要です。多くの社員が自宅で仕事をする際、デスクや椅子、照明などの作業環境を整える必要があります。しかし、全社員が十分な作業スペースを確保できるわけではありません。
自宅に十分なスペースがない場合、集中できる環境を整えることが難しいです。また、家族との共同生活がある場合、仕事に集中するための空間を確保することも課題となります。このような物理的な環境が整えにくいため、リモート勤務を廃止し、オフィスでの勤務に戻す企業が増えているのです。
職場に行かないとできない業務がある
リモート勤務では、全ての業務がオンラインで完結するわけではありません。例えば、現場での作業や確認すべき資料、対面でのミーティングが必要な業務があります。また、機密情報を取り扱う部署や法的に出社を求められる業務も存在します。
さらに、上司や同僚とのリアルタイムでのコミュニケーションが必要な場面もあります。このように、出社をしないと完結しない業務があることから、リモート勤務廃止を決定する企業も多いです。とくに、製造業や医療業界などでは、リモート勤務が難しいため、出社を強制する場合があります。
仕事のオン・オフを切り替えるのが難しい
リモート勤務では、仕事とプライベートの境目が曖昧になりがちです。自宅で仕事をしていると、仕事の時間と休憩時間の切り替えが難しくなります。これにより、長時間働きすぎてしまうケースや、逆に業務に集中できないケースが発生することがあります。
企業としては、社員が規則正しい働き方を維持するためにも、オフィスでの勤務に戻すことを選択することが多いです。仕事の生産性を保つためには、オン・オフをしっかりと切り替えることが重要とされており、オフィス勤務でのメリットが再評価されています。
コミュニケーションが不足してしまう
リモート勤務では、顔を合わせてのコミュニケーションが減少するため、チーム内での情報共有や意思疎通が不足しがちです。これにより、誤解や情報漏れが発生することがあり、業務の効率が低下する可能性があります。
リーダーシップを発揮する必要がある上司やマネージャーにとって、リモート勤務での社員とのやり取りが難しく、業務進捗を管理しづらくなる場合があります。このような理由から、リモート勤務の廃止を決定し、対面でのコミュニケーションができるオフィス勤務を再開する企業も増加しているのです。
リモートワークでコミュニケーションが不足してしまう原因については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:リモートワークでコミュニケーションが不足する原因と解決法を解説
リモート勤務廃止を拒否できる条件は?
リモート勤務廃止の際に、リモート勤務のまま働きたいと考える人は少なくありません。リモート勤務の廃止を法的に拒否できるかどうかは、勤務条件や雇用契約の内容によって異なります。
- 就業規則や雇用契約書にリモート勤務に関する記載がない場合
- 会社とリモート勤務限定の雇用契約を結んでいる場合
- リモートワークの廃止が合理的ではない場合
- リモート勤務廃止を拒否できない条件は?
就業規則や雇用契約書にリモート勤務に関する記載がない場合
リモート勤務を拒否できるかどうかは、まず就業規則や雇用契約書の内容を確認する必要があります。リモート勤務が制度として正式に定められていない場合、企業は出社するのが当たり前だと主張するでしょう。しかし、契約書や就業規則に「本社に出社しなければならない」といった内容が明記されていなければ、必ずしも企業側の出社命令が自動的に正当とは限りません。
とくに、長期間リモート勤務が継続していた場合には、黙示的な労働条件の合意が成立していたと主張できる可能性もあります。これは労使間でリモート勤務が当然の働き方と認識されていた、という解釈につながるため、一方的な出社命令に対し、合理性の有無が問われることになります。
また、企業がリモート勤務を容認していた事実が証明できれば、不利益変更と見なされるケースもあるのです。東京地裁 平成27年3月25日判決(学校法人二松学舎事件)は、「黙示の合意」によって労働条件が変化しうることを認めた判例です。
長期的にリモート勤務をしていた実績があれば、リモート勤務が黙示的に合意されたと主張する余地があることがわかります。ただし、リモート勤務が暫定措置として導入されていた場合などは、黙示の合意が認められない可能性があります。そのため、状況に合わせて弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
会社とリモート勤務限定の雇用契約を結んでいる場合
雇用契約書に「勤務地:自宅」「勤務形態:テレワークを基本とする」などと明記されている場合、会社は原則として一方的に出社を強制できません。これは、労働契約法第8条の「契約内容の変更は労働者と合意の上でなされるべき」という原則に基づきます。
契約書に勤務地や働き方が明確に定められている場合、それを変更するには本人の同意が必要です。また、就業開始時にフルリモート勤務を前提とした募集要項で入社していた場合も、状況によっては労働条件の黙示的合意と見なされる可能性があります。
企業がこのような契約内容を無視して出社を強要した場合、違法性を問われるおそれもあります。したがって、リモート勤務が契約上の明確な条件となっている方は、その証拠となる書類やメール、求人票などを保管しておくことが重要です。
リモートワークの廃止が合理的ではない場合
企業がリモートワークを一方的に廃止するには、業務上の必要性や合理的な理由が求められます。これは労働契約法第10条における「不利益変更の合理性」に基づいています。合理性がない状態での勤務形態変更は、労働者の生活や働き方に重大な影響を与えるため、無条件に認められるものではありません。
例えば、業務の性質上、在宅勤務でも支障なく遂行できている場合や、テレワーク環境で高い生産性が維持されている場合、あえて出社に戻す必要性は薄いと考えられます。また、通勤によって心身に大きな負担がかかるようなケースでは、健康配慮義務(安全配慮義務)に違反する可能性もあります。
このように、リモートワーク廃止の背景に業務的・組織的な必然性が見当たらない場合は、変更に正当性があるとは言えません。必要に応じて第三者機関や労働基準監督署への相談も視野に入れましょう。
リモート勤務廃止を拒否できない条件は?
一方で、すべてのケースでリモート勤務を拒否できるわけではありません。例えば、雇用契約書に「勤務場所:本社」などと記載されていたり、「リモート勤務は一時的措置」と明示されていたりする場合、会社側が出社を命じることに一定の正当性があります。
また、業務内容の変更によりリモートでは対応できない業務が発生した場合や、チーム全体のパフォーマンスに悪影響が出ている場合などは、労働契約法第7条に基づき、業務上の指示に従う義務が優先されるケースもあります。
36協定や就業規則に出社を前提とした勤務体系が明記されていれば、企業側の判断が尊重されやすいです。拒否し続けると、職務命令違反とみなされ、懲戒処分の対象になるリスクもあるため注意が必要です。
リモート勤務廃止による出社強制への対処法
リモート勤務の廃止が進む中で、突然の出社強制に困惑している方も少なくありません。企業側にも事情がありますが、労働者にも生活や働き方のペースがあります。一方的な指示に従う前に、まずは自分の立場や契約内容を確認し、適切に対処することが重要です。
- 契約書・就業規則を確認して廃止が妥当であるか判断する
- 上司や人事部門と交渉する
- 団体交渉を行う(労働組合がある場合)
- 転職を検討する
契約書・就業規則を確認して廃止が妥当であるか判断する
まず確認すべきは、雇用契約書や就業規則における勤務場所の取り決めです。契約書や就業規則にリモート勤務の明記がある場合、企業側の一方的な勤務形態の変更には合理的な理由が必要となります。逆に、契約書に勤務地が「本社」などと記載されている場合や、リモート勤務が特例的に認められていた場合は、出社要請にも一定の正当性が認められる可能性があります。
また、契約時の説明内容や、実際の勤務実態も重要な判断材料です。これらを整理した上で、リモート勤務廃止が妥当であるかどうかを見極めましょう。
上司や人事部門と交渉する
契約内容や勤務実態を確認したら、上司や人事担当者に相談してみましょう。企業側がリモート勤務を廃止する理由を尋ねたうえで、自身の業務内容や家庭事情、通勤負担などを具体的に伝えることが重要です。交渉の際は、感情的にならず、事実と要望を冷静に伝える姿勢が信頼を得やすくなります。
また、これまでのリモート勤務での成果や生産性についてもアピール材料として活用すると効果的です。柔軟な対応が可能な場合は、出社と在宅を併用するハイブリッド勤務などの妥協点を探るのもひとつの方法です。
団体交渉を行う(労働組合がある場合)
勤務先に労働組合が存在する場合は、個人での交渉に限らず、組合を通じた団体交渉を行うという選択肢もあります。団体交渉は労働組合法で保障された権利であり、会社側は正当な理由なくこれを拒否できません。複数の社員が同様の悩みを抱えている場合、組合が会社と交渉することで、勤務形態に関するルールの見直しや個別対応の可能性が生まれます。
団体交渉の申請には一定の手続きが必要ですが、労働者全体の利益を守るためにも有効な手段となります。労働組合がない場合でも、外部の労働相談窓口を活用する方法も検討してみてください。労働組合に相談できる内容や手続きについては、以下の記事を参考にください。
関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説
転職を検討する
交渉や組合による働きかけでも状況が改善されない場合は、転職も視野に入れる必要があります。働き方に対する価値観やライフスタイルは人それぞれ異なります。リモートワークが自分にとって不可欠であるなら、それを尊重してくれる企業へ転職するのも一つの方法です。
現在は柔軟な働き方を推進する企業も増えており、リモートワークを前提とした求人も多く見られます。無理に環境へ適応しようとするのではなく、自分に合った職場環境を探すという選択も、立派な対処法といえます。初めて転職する人は、以下の注意点もご確認ください。
関連記事:初めての転職活動で失敗しない21の注意点!転職の流れを押さえよう
リモート勤務廃止を拒否できない場合、出社しないとどうなる?
リモート勤務の廃止に納得がいかない場合でも、企業側に正当な理由があるケースでは、出社命令に従わなければなりません。出社せずに働き続けようとした場合、どのようなリスクがあるのか紹介します。
- 懲戒処分を受ける可能性がある
- 上司や同僚との信頼関係が崩れる
- 転職活動が不利になる
懲戒処分を受ける可能性がある
企業が就業規則や業務命令として出社を明確に指示しているにもかかわらず、正当な理由なしに出社を拒んだ場合、業務命令違反として懲戒処分の対象になる可能性があります。懲戒処分には始末書の提出や戒告、減給、出勤停止、そして重い場合には懲戒解雇の処分が科されます。
とくに、何度も出社命令に従わない場合や、会社との対話の機会を拒絶するような対応をしてしまうと、より重い処分が科される可能性が高いです。ただし、家庭の事情や健康上の理由など、出社を拒むにあたって合理的な事情がある場合は、その内容によって処分の妥当性を争える余地があります。
処分を受けそうになった際は、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士への相談を検討してください。
上司や同僚との信頼関係が崩れる
出社命令を無視した行動は、たとえ懲戒処分を受けなかったとしても、職場内での人間関係に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。上司からは会社の方針に従わない社員と見なされ、信頼を失う可能性が高いです。
こうした評価は、業務上の連携に支障をきたすだけでなく、評価面談や昇進の機会にも悪影響を与えかねません。チームワークを重視する企業文化の中では、協調性や柔軟性が求められる場面が多いため、独断的な行動はマイナス評価につながりやすいです。
たとえ自分の希望と異なる判断が下された場合でも、その理由を相手に伝えたうえで、丁寧に対話を重ねる姿勢が信頼維持には重要です。
転職活動が不利になる
リモート勤務廃止に伴って出社を拒否し、結果として会社を退職することになった場合、次の職場での印象に影響を及ぼす可能性があります。とくに、懲戒処分を受けた経緯がある場合は、職務経歴書の記載内容や面接時の説明に苦慮することもあります。
企業は採用の際、前職での勤務態度や協調性を重視する傾向があるため、自社ルールに従えない人と見なされると選考に不利になるでしょう。
リモート勤務廃止後に代替として活用できる制度・働き方
リモート勤務が廃止されても、柔軟な働き方を完全に失う必要はありません。企業によっては、リモートに代わる働きやすい制度を導入しているケースもあります。
- フレックスタイム制度
- 時差出勤制度
- 週1~2日の在宅勤務(ハイブリッド型勤務)
- 短時間勤務制度(時短勤務)
フレックスタイム制度
フレックスタイム制度は、労働者が始業・終業時刻を自身で調整できる制度です。1日の中でコアタイム(必ず勤務する時間帯)を設け、それ以外の時間帯で自由に働けます。通勤ラッシュを避けたい方や、家庭の事情に合わせた働き方を希望する方にとって、活用したい制度です。
ただし、制度の運用方法は企業によって異なるため、導入されているかどうか、またコアタイムの有無や条件について確認しておきましょう。
時差出勤制度
時差出勤制度は、始業時間をずらして出勤することが認められる制度です。一般的に満員電車を避ける目的で導入されており、心身の負担を軽減する効果があります。通勤時間帯を調整できれば、朝の支度に余裕が生まれたり、子育てや介護との両立がしやすくなったりします。
とくにリモート勤務に慣れていた人にとって、出社の負担を最小限に抑えるための一手段となるでしょう。
週1~2日の在宅勤務(ハイブリッド型勤務)
完全なリモートワークは難しくても、週に1~2日程度の在宅勤務を認める「ハイブリッド型勤務」が可能か交渉するのも一つの手です。通勤負担の軽減や、集中して作業を進めたい業務がある日などに活用することで、生産性を維持しながら柔軟な働き方が可能になります。
企業にとっても、一定の出社を求めることでチームの一体感やコミュニケーションを保ちつつ、社員の働きやすさを確保できるため、双方にとってメリットのある制度です。制度の適用には、上司との相談や業務内容の確認が必要になることもあるため、あらかじめ希望を明確に伝える準備をしておくとよいでしょう。
短時間勤務制度(時短勤務)
短時間勤務制度は、1日の労働時間を短縮する制度であり、子育てや介護などの事情を抱える労働者に活用されています。一般的には所定労働時間よりも1〜2時間短い勤務が認められており、フルタイム勤務が難しい人にとって心強い制度です。
法律に基づく制度として、育児や介護のために利用する場合は企業がこれを認めなければならないケースもあります。勤務時間が短くなることで収入に影響が出ることもありますが、その分プライベートとの両立がしやすくなり、仕事への集中力も高まる可能性があります。勤務形態に悩んだ際は、このような制度を活用できないか検討してみてください。
リモート勤務廃止に関するよくある質問
リモート勤務廃止に関するよくある質問を紹介します。
- 会社が一方的にリモートワーク勤務を廃止するのは違法ですか?
- フルリモート前提で入社した場合でも廃止に従わないといけませんか?
- リモートワークを廃止した企業はありますか?
- リモート勤務が廃止したことにより転職する人は多い?
- リモート勤務廃止により出勤拒否するのは違法ですか?
会社が一方的にリモートワーク勤務を廃止するのは違法ですか?
結論からお伝えすると、会社が一方的にリモートワーク勤務を廃止するのは必ずしも違法とは限りません。
会社が従業員に対して出社を命じるには、就業規則や雇用契約書に明示された勤務場所の定めに従う必要があります。契約内容に基づいていれば、リモート勤務の廃止は原則として違法ではありません。
一方で、雇用契約書や採用時の求人票にフルリモート勤務と明記されていたり、入社後から長期間リモート勤務が継続していた場合には、労働条件の黙示的合意が成立しているとみなされる可能性があります。このようなケースで合理性がないまま一方的に勤務形態を変更した場合、違法と判断されることがあります。
フルリモート前提で入社した場合でも廃止に従わないといけませんか?
フルリモート勤務を前提として入社した場合、その条件が雇用契約書や求人票に明記されていれば、会社側の一方的な変更は不当とされる可能性が高いです。
一方で、契約書に勤務地が特定されていない場合や、業務の必要に応じて出社を命じることがあるといった但し書きがある場合には、会社の指示に従う必要があるケースもあります。実務では、使用者側と協議し、納得のいく形で働き方を調整することが望ましいです。
リモートワークを廃止した企業はありますか?
2024年から2025年にかけて、リモートワークを廃止または縮小し、出社を義務づける企業が増えています。例えば以下のような企業です。
- ヤフー株式会社:2025年3月にハイブリッド制度を再検討し、週2〜3日の出社に変更。
- 楽天グループ:2025年2月から原則週4日出社へ移行。全社的な業務の一体感を重視し、ハイブリッド勤務制度から段階的に出社中心へ転換。
- 三井住友銀行:2025年1月以降、週3日以上の出社を義務化。行内のセキュリティ強化や若手育成を目的とした方針。
- Amazon(アマゾン):2024年中盤より週3日以上のオフィス出社を義務化。
上記のように大手企業もリモートワークを廃止する傾向が増えています。
リモート勤務が廃止したことにより転職する人は多い?
公益財団法人日本生産性本部が発表した「テレワークに関する意識調査」によれば、勤め先でテレワークが廃止・制限されたときに退職・転職を検討する人の割合は16.4%です。今の勤め先で継続して働く人の割合は58.7%で、勤め先を変えずに時短勤務など働き方の変更を検討する人の24.9%でした。
つまり多くの人は、リモート勤務が廃止になったとしても現在の勤め先で働いているようです。
参考元:公益財団法人日本生産性本部|テレワークに関する意識調査
リモート勤務廃止により出勤拒否するのは違法ですか?
原則として、会社が正当な理由に基づいて出社を命じたにもかかわらず、従業員がこれに応じない場合、業務命令違反とみなされる可能性が高いです。場合によっては、懲戒処分の対象となることもあるため注意が必要です。
まとめ
リモート勤務は拒否できるのかについて解説しました。近年ではリモート勤務を廃止する企業が増えています。そのため、フルリモート勤務として入社しても、廃止により出社を求められるケースは少なくありません。
雇用契約や就業規則などによって、拒否できるか異なるため、迷ったときは専門家に相談しましょう。もし、今の職場にどうしても耐えられないと感じたら、退職代行サービスを利用して転職するのも一つの方法です。退職に関する悩みや不安がある人は、退職代行ほっとラインへご相談ください。

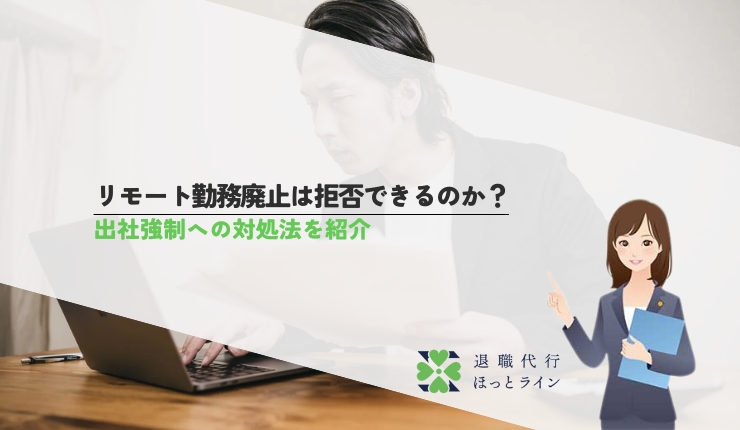

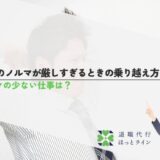

コメントを残す