仕事の失敗や責任の重さ、人間関係などさまざまな理由でストレスは溜まります。ストレスは溜めすぎると身体ともに悪影響を及ぼすため、定期的に発散することが重要です。ストレス発散方法は人により異なります。そのため、自分に合った発散方法を見つけることが大切です。
本記事では、ストレス発散方法を12つ紹介します。また自分のストレスを分析したり、溜め込まない心得を紹介したりしていますので、ぜひ参考にしてください。
・仕事でストレスが溜まる理由は、仕事の失敗・責任の発生、仕事量が多い、対人関係、顧客や取引先からのクレームなど
・職場ですぐにできるストレス発散方法は、短い休憩・昼寝を取る、ストレッチ、デスク周りを整理整頓、雑談タイムを設けるなど
・自宅でできるストレス発散方法は、お風呂に入る、趣味に没頭する、軽い運動をする、友人や家族とコミュニケーションを取るなど
目次
仕事でストレスが溜まる理由とは?職場の5大ストレス
仕事をしていると、ストレスは溜まるものです。その要因は一つではなく、複数の要素が絡み合っているケースが少なくありません。中でも多くの人が悩まされているのが、業務内容・人間関係・責任感などからくる精神的な負担です。
まずは、仕事のストレスが溜まる理由を見ていきましょう。
- 仕事の失敗・責任の発生によるストレス
- 仕事量が多いことによるストレス
- 対人関係(セクハラ・パワハラ)によるストレス
- 顧客・取引先からのクレームによるストレス
- 仕事の質(やりがいや仕事内容)によるストレス
- 雇用形態によってストレスになる原因が変わる
仕事の失敗・責任の発生によるストレス
厚生労働省が発表「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、正社員が仕事で抱えるストレスとして最も多いのが「仕事の失敗・責任の発生によるストレス(42.9%)」です。誰しも一度は仕事で失敗することがあります。
その際に、自分のせいで迷惑をかけてしまったと感じる人は多いです。
とくに20歳未満の若い人は、仕事の失敗によるストレスを強く感じる傾向があります。また、年齢が高くなると、責任のある立場に就く人が多く、責任の重さを負担に感じる人が多くなります。そのため、50~59歳未満の年代も責任の発生によるストレスを強く感じる人が多いです。
また、契約社員やパートタイムなどに比べて、正社員は仕事の責任が重くなるため、ストレスを感じやすくなるようです。仕事の責任が重くて耐えられないときの対処法は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:仕事の責任が重くて耐えられないときの対処法!責任を持つメリットも紹介
仕事量が多いことによるストレス
厚生労働省の同調査によれば、2番目に多いのが「仕事量が多いことによるストレス(41.2%)」です。
明らかに人手が足りていないのに業務が次々と降ってくる、定時で終わるはずの仕事が常に残業になる、といった状況は多くの人にとって強いストレスの原因となります。仕事量が過剰になると、集中力が続かずミスも起きやすくなりますし、心の余裕もなくなってしまいます。
厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等」によれば、一般労働者の平均労働時間は156.1時間です。所定内労働時間は142.9時間、所定外労働時間(残業時間)は13.2時間となっています。
業種により異なりますが、平均よりも大幅に労働時間が長ければ、仕事量が過剰であるといえます。
残業が当たり前のようになってしまうと、プライベートの時間が削られ、心身ともに回復する時間が持てません。とくに真面目な人ほど、自分が頑張らなければと思い込んでしまい、さらに無理を重ねてしまう傾向があります。
参考元:厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等
対人関係(セクハラ・パワハラ)によるストレス
3番目に多いのが「対人関係(セクハラ・パワハラ)によるストレス(29.6%)」です。職場での人間関係は、仕事のストレスの中でもとくに深刻な要因のひとつです。中でもセクハラやパワハラといったハラスメント行為は、精神的にも肉体的にもダメージを与え、仕事に行くことさえ苦痛に感じるようになります。
上司からの威圧的な態度、理不尽な叱責、性的な言動などが日常的に行われている場合、心の傷は深くなる一方です。また、同僚との関係がうまくいかない、孤立してしまっているといった状況も、ストレスを大きくする要因です。
職場の人間関係は逃げ場が少なく、我慢を続けることで限界を超えてしまうこともあるため、ひとりで抱え込まず早めの相談が重要になります。セクハラやパワハラの対処法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:セクハラの相談先はどこ?12つの無料相談窓口と被害の対策法を紹介
パワハラ被害にあった場合の無料相談窓口8選!被害にあったときの対処法とセットで解説します
顧客・取引先からのクレームによるストレス
4番目に多いのが「顧客・取引先からのクレームによるストレス(29.2%)」です。接客業や営業職など、顧客と直接やり取りする仕事では、クレーム対応が大きなストレスになります。理不尽な要求や怒鳴り声、感情的な言葉をぶつけられると、自分に非がないとわかっていても大きなダメージを受けます。
電話対応や窓口業務では逃げ場がなく、何度も同じような対応を繰り返すことで精神的に追い詰められてしまうことも少なくありません。また、取引先からのプレッシャーが強く、納期や結果に対して過剰な期待をかけられる場合も、ストレスを感じやすくなります。
こうした状況が続くと、対人恐怖や自己否定感が強くなるリスクもあり、適切なサポートが求められます。
仕事の質(やりがいや仕事内容)によるストレス
5番目に多いのが「仕事の質(やりがいや仕事内容)によるストレス(27.8%)」です。自分の仕事にやりがいを感じられない、仕事内容が単調でつまらないといった理由でストレスを抱える人も少なくありません。
スキルや適性と合わない業務を強いられていると、常にフラストレーションを感じるようになります。また、自分の仕事が誰の役に立っているのか分からないと感じると、働く意義を見失い、モチベーションの低下につながります。
仕事の質と自分の価値観が合っていないと、長期的にストレスが蓄積されやすくなるため、自分に合った働き方を見直すことも必要です。
雇用形態によってストレスになる原因が変わる
雇用形態によってもストレスになる原因が異なります。正社員・契約社員・パートタイム労働者・派遣労働者のストレスの原因を見ていきましょう。
| 正社員 | 契約社員 | パートタイム労働者 | 派遣労働者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仕事の失敗・責任の発生 | 雇用の安定性 | 仕事量の多さ | 仕事の失敗・責任の発生 |
| 2 | 仕事量の多さ | 仕事量の多さ | 対人関係 | 仕事の質 |
| 3 | 対人関係 | 対人関係 | 雇用の安定性 | 雇用の安定性 |
| 4 | 顧客・取引先からのクレーム | 仕事の失敗・責任の発生 | 仕事の失敗・責任の発生 | 対人関係 |
| 5 | 仕事の質 | 仕事の質 | 仕事の質 | 仕事量の多さ |
契約社員は雇用期間が決まっているので、安定して雇用してもらえるか心配する人が多いです。そのため、雇用の安定性に関するストレスが一番多くなっています。一方で管理職や意思決定のポジションに就くケースが少ないため、責任によるストレスが少ないようです。
パートタイム労働者も契約社員と同様に、仕事の失敗や責任の発生に関するストレスは少ないです。一方、限られた時間の中で多くの業務をこなす必要があり、仕事量の多さに対するストレスが多くなっています。
派遣労働者のみ、仕事の質に関するストレスが上位に挙がっています。組織の中で補助的な役割を担うことが多く、やりがいを感じられない人が多いのではないでしょうか。また、会社によっては、雑務などを回されるケースもあり、ストレスにつながります。
このように、雇用形態によってもストレスになる原因が異なります。原因によっても対処法が異なるので、自分はどのような理由でストレスを感じるのか分析してみましょう。
あなたのストレスは何タイプ?自分のストレスを分析しよう
ストレスと一口に言っても、その原因や感じ方は人それぞれです。原因が曖昧なままでは、適切な対処ができず、状況が悪化してしまうこともあります。まずは自分のストレスのタイプを知ることが大切です。
- 仕事のプレッシャーに弱いタイプ
- 人間関係に悩むタイプ
- 過剰に責任感を感じるタイプ
- 仕事にやりがいを感じないタイプ
- 時間に追われるタイプ
仕事のプレッシャーに弱いタイプ
仕事の成果や評価に対して強い不安を感じやすいタイプです。このタイプは、完璧を求めすぎる傾向があり、少しのミスでも自己否定につながりやすいという特徴があります。とくに成果主義や目標達成を重視する職場にいる場合、プレッシャーに常にさらされてしまいます。
また、ノルマや数字に追われる職種でよく見られるタイプです。例えば営業職や販売職などでは、日々の結果が目に見えるため、プレッシャーが積み重なりやすくなります。本人にとっては努力しているつもりでも、成果が出ないと自己評価が下がり、ストレスの悪循環に陥ることもあります。
仕事のプレッシャーに弱いタイプにおすすめのストレス発散方法は、以下の通りです。ストレス発散の詳細については、後ほど紹介します。
- ポジティブな言葉で自分を鼓舞する
- 短い休憩・昼寝を取ってリセットする
- 軽いストレッチで心身をほぐす
- お風呂にゆっくり入ってリラックスする
- 日記をつけて気持ちの整理をする
人間関係に悩むタイプ
職場の人間関係にストレスを感じやすいタイプです。チームワークや報連相が求められる職場では、周囲とのコミュニケーションがうまくいかないと、大きなストレスにつながります。
このタイプは、相手の言動を深読みしやすく、悪意のない言葉でもネガティブに受け取ってしまう傾向があります。嫌われている、自分だけ浮いている気がするといった不安に悩まされやすいのが特徴です。
内向的で気を遣いすぎる性格の人や、自分のことがどのように思われているのか気にしすぎる人は、このタイプに該当しやすいです。
また、上司との関係がギクシャクしていたり、同僚からの無視や陰口といった職場いじめを受けていたりするケースもあります。こうした状況では、出勤そのものが苦痛になり、体調にも影響が出やすくなります。悩みを一人で抱えず、信頼できる第三者に相談することが重要です。
人間関係に悩むタイプにおすすめのストレス発散方法は、以下の通りです。ストレス発散の詳細については、後ほど紹介します。
- 同僚や上司などと雑談タイムを設ける
- 日記をつけてモヤモヤを言語化する
- 自然に触れて気分転換する
- 趣味に没頭して自分だけの時間を過ごす
- 友人や家族とコミュニケーションを取る
- デスク周りを整理整頓する
過剰に責任感を感じるタイプ
自分がやらなければという思いが強く、すべてを抱え込んでしまうタイプです。周囲に頼るのが苦手な人や、自分の思ったように仕事を進めたい人に該当しやすいです。
このような人は、業務の負荷が増えても断らずに引き受けてしまい、結果的にキャパオーバーになってしまうケースが多く見られます。責任感が強いこと自体は長所ですが、限度を超えるとストレスや燃え尽き症候群の原因になるので注意が必要です。
また、他人のミスやトラブルまでも「自分のせいでは?」と思い込んでしまう傾向もあります。この責任感の強さは、職場で頼りにされやすい反面、自分を追い込んでしまう危うさも含んでいます。適切な線引きと、任せる勇気が必要です。
過剰に責任感を感じるタイプにおすすめのストレス発散方法は、以下の通りです。ストレス発散の詳細については、後ほど紹介します。
- デスク周りを整理整頓して気持ちを落ち着かせる
- 自分を甘やかす時間を意識的に作る
- 軽いストレッチで肩の力を抜く
- 短い休憩・昼寝を取って切り替える
- お風呂にゆっくり浸かって緊張をほぐす
仕事にやりがいを感じないタイプ
仕事がつまらない、モチベーションが上がらないなど、働く意義を見出せないタイプです。毎日同じ作業の繰り返しや、単純作業が中心であると、この仕事に意味があるのかと感じるようになります。派遣社員やパートタイム勤務など、補助的な業務が中心となる職場で、とくにこのタイプのストレスが見られやすいです。
業務の中に工夫や達成感を感じられないと、モチベーションは低下します。誰でもできる仕事しか任されない、自分の意見が反映されないといった状況が続くと、やりがいを持つのは難しくなります。こうした状態が続けば、仕事への興味を失い、転職やキャリアチェンジを考えるきっかけになる場合も少なくありません。
仕事にやりがいを感じないタイプにおすすめのストレス発散方法は、以下の通りです。ストレス発散の詳細については、後ほど紹介します。
- 趣味に没頭して充実感を得る
- 自然に触れて刺激を受ける
- 軽い運動で気持ちをリフレッシュする
- 日記をつけて目標や感情を見直す
- デスク周りを整えて気分を変える
時間に追われるタイプ
業務量が多く、労働時間が長くなりやすいタイプです。常にスケジュールに追われていると、心にも余裕がなくなります。このタイプはもっと早く終わらせなければ、時間内に完了させないといけないと、自分に強いプレッシャーをかけてしまいがちです。
とくに子育てや介護と両立して働いている人、または残業が多い職場で働く人に多く見られます。1分1秒を争うような感覚で動く日々が続くと、精神的な疲労が蓄積しやすくなります。
また、計画通りに進まないと焦りや苛立ちを感じやすくなるため、些細なことで感情が爆発してしまうこともあります。周囲からの時間に余裕がなさそう、という印象が人間関係の悪化につながるケースも少なくありません。
優先順位の見直しや、タスク管理の工夫が必要です。
時間に追われるタイプにおすすめのストレス発散方法は、以下の通りです。ストレス発散の詳細については、後ほど紹介します。
- 軽いストレッチで緊張を和らげる
- お風呂にゆっくり入って時間を忘れる
- デスク周りを整理して作業効率を上げる
- ポジティブな言葉で自分にゆとりを与える
- 短い休憩・昼寝を取り入れてリズムを整える
職場ですぐにできるストレス発散方法5選
業務中でも取り入れやすい発散方法を知っておくことで、心の負担を軽くできます。今回は、忙しい仕事の合間でも実践しやすいストレス発散方法を5つ紹介します。どれも特別な道具や準備が必要ないため、すぐに取り入れられるのが特徴です。
- 短い休憩・昼寝を取る
- 軽いストレッチで体をほぐす
- デスク周りを整理整頓する
- 同僚や上司などと雑談タイムを設ける
- ポジティブな言葉で自分を鼓舞する
短い休憩・昼寝を取る
仕事の合間に意識的な休憩を取ることは、ストレス発散方法として効果的です。とくに、10~15分の短い仮眠は集中力の回復に役立ちます。脳をリセットさせる時間を作ることで、気分転換になり、イライラや疲労感の軽減につながります。
休憩を取るタイミングは、自分が集中力を失いやすい時間帯に合わせると効果的です。例えば、昼食後や午後の始まりなどが適しています。職場の環境によっては目を閉じるだけでも十分にリフレッシュできるため、できる範囲で実践してみましょう。
軽いストレッチで体をほぐす
長時間のデスクワークは、肩や首、腰などに負担がかかりやすくなります。そのまま放置すると、身体のこわばりがストレスの原因にもなります。そこで、簡単なストレッチを取り入れて体をほぐすことが大切です。
椅子に座ったままでも、肩を回したり首をゆっくり伸ばしたりするだけで血行が良くなります。身体がほぐれることで、自然と気分も前向きになりやすくなります。定期的なストレッチはストレス発散に効果的なので、1時間に1回程度のペースを目安に取り入れてみてください。
デスク周りを整理整頓する
乱雑なデスクは集中力を妨げるだけでなく、ストレスの原因にもなります。整理整頓をすることで、気分がすっきりし、仕事へのモチベーションも上がりやすいです。書類や文房具を定位置に戻す、不要なものを捨てるといった簡単な作業でも十分効果があります。
視界に入るものを整えることで、頭の中も整理されていきます。また、きれいな環境は周囲にも良い印象を与えるため、職場の人間関係にもプラスの影響をもたらすでしょう。ストレスを感じたら、まずは机の上を見直してみてください。
同僚や上司などと雑談タイムを設ける
ちょっとした会話は、心の緊張を緩めてくれる大切な手段です。業務の合間に同僚や上司と雑談をすることで、孤独感や不安感が和らぎます。話す内容は仕事に限らず、趣味や最近あった出来事など何でも構いません。
会話を通じて共感や笑いを共有することで、心に余裕が生まれます。また、人とのつながりを感じることで安心感が得られ、精神的な安定につながるケースも多いです。もちろん、周囲の状況に配慮しながら、短時間でストレス発散できる範囲にとどめることがポイントです。
もし職場で話す相手がいない・相談できる人がいない場合は外部の相談窓口を利用しましょう。以下の記事を参考にしてください。
関連記事:会社に相談できる人がいない場合どうする?対処法と相談窓口を紹介します
ポジティブな言葉で自分を鼓舞する
自分に対して前向きな言葉をかける「セルフアファメーション」は、ストレス発散に効果的です。例えば、自分ならできる、今日はここまで頑張ったといった言葉を口にするだけで、気持ちが切り替わります。
ネガティブな感情に引きずられそうなときこそ、意識的にポジティブな表現を使いましょう。鏡の前で声に出すのが難しい場合でも、心の中で唱えるだけで効果があります。言葉の力を活用して、自分の心にエネルギーを与える習慣を作っていくことが大切です。
自宅でできるストレス発散方法7選
仕事や人間関係で疲れた心は、自宅でしっかり癒すことが大切です。ストレスは溜め込まず、自宅に帰って定期的にストレスを発散しましょう。誰でも気軽に取り入れられる自宅でのストレス発散方法を7つ紹介します。
- お風呂にゆっくり入る
- 趣味に没頭する
- 軽い運動をする
- 友人や家族とコミュニケーションを取る
- 自然に触れてリフレッシュする
- 自分を甘やかす
- 日記をつけて気持ちを整理する
お風呂にゆっくり入る
お風呂に浸かることは、自律神経を整える効果があるとされています。38〜40度のぬるめのお湯に15分程度浸かると、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスしやすくなります。入浴中にアロマオイルを使ったり、照明を落としたりすると、さらに癒し効果が高まります。
シャワーだけで済ませがちな方も、疲れが溜まっていると感じた日は意識的に湯船に入るようにしましょう。入浴は心の疲れを流し去るだけでなく、ぐっすり眠るための準備にもつながります。
趣味に没頭する
趣味の時間は、ストレスから自分を解放する貴重なひとときです。好きなことに集中することで、ネガティブな思考からポジティブな気持ちへと切り替えられます。読書、手芸、料理、音楽など、自分が心から楽しめるものを選ぶのがポイントです。
忙しい毎日の中でも、少しでも自分のためだけの時間を確保することが、メンタルバランスを保つために大切です。
軽い運動をする
運動はストレスホルモンを減らし、気分を明るくする効果があるとされています。散歩やヨガ、軽い筋トレなどは無理なく続けやすく、自宅でも取り入れやすいのが特徴です。身体を動かすと血流が良くなり、心もすっきりしやすくなります。
また、運動によって分泌されるエンドルフィンには、幸福感を高める働きがあります。疲れたときこそ軽い運動を取り入れることで、ストレスを発散できるのです。運動の習慣は、ストレスをためにくい体質づくりにもつながるでしょう。
友人や家族とコミュニケーションを取る
信頼できる人との会話や愚痴を聞いてもらうことは、ストレス発散に効果的です。悩みやモヤモヤを言葉にするだけでも、心が軽くなる感覚を得られることがあります。直接会えない場合は、電話やメッセージのやり取りでも構いません。
大切なのは一人で抱え込まないことです。話すことで自分の気持ちを整理でき、相手の共感や励ましが新たな活力になります。コミュニケーションは心の支えとなる、大切なストレス対策のひとつです。状況に応じて外部の相談窓口を利用するのもおすすめです。
自然に触れてリフレッシュする
ベランダで植物を眺める、近所の公園で木々に囲まれるなど、自然と触れ合う時間もストレス発散になります。自然には癒し効果があり、視覚的にも嗅覚的にも心を穏やかにする力があります。
晴れた日に窓を開けて太陽の光を浴びるだけでも、気分がスッと軽くなる人もいるのではないでしょうか。忙しい毎日でも、意識して自然と関わる時間を取るようにしましょう。
自分を甘やかす
頑張っている自分にご褒美をあげる時間も大切です。好きなスイーツを食べる、好きなドラマを一気見するなど、自分に優しく接することで心が回復します。今日は頑張ったからOKと自分を認めることで、自己肯定感も高まりやすくなります。
常にストイックであろうとすると、知らず知らずのうちに心が疲れてしまうものです。ときには自分に甘くなってもいい、そんな気持ちを大切にすると、明日への活力が自然とわいてきます。
日記をつけて気持ちを整理する
自分の気持ちを文字にして書き出すことは、頭の中のモヤモヤを整理するうえで非常に効果的です。日記には、誰にも言えない本音や小さな不満も素直に書き出せます。書くことで「何がストレスなのか」が客観的に見えてくることもあります。
1日数行でも構いません。感情を言語化する習慣は、自己理解を深め、ストレスへの耐性を高める助けになります。寝る前の時間などに、静かに自分と向き合う時間を作ってみましょう。
毎日のストレスを軽減!仕事でストレスを溜め込まないための心得
ストレスは突然爆発するものではなく、日々の小さな我慢や無理の積み重ねによって蓄積されていくものです。だからこそ、毎日の中でストレスを溜めない工夫が重要です。仕事のストレスを溜め込みすぎないようにするための4つの心得を紹介します。
- 仕事とプライベートを切り替える
- 他人との比較をやめて自分のペースで仕事を進める
- ポジティブな考え方を身につける
- 何でも相談できる人を見つける
仕事とプライベートを切り替える
仕事とプライベートの境界があいまいになると、常に仕事のことを考えてしまい、心が休まりません。とくにテレワークやスマホでの仕事対応が当たり前になった今は、意識的な切り替えが求められます。
仕事が終わったらパソコンを閉じる、通勤時に音楽やラジオで気分を変える、帰宅後は仕事関連の話題を避けるなど、オンとオフをはっきり分ける工夫をしましょう。切り替えを習慣化することで、頭の中がリセットされ、次の日にストレスを持ち越しにくくなります。
業務時間外に仕事の連絡が来て、切り替えが難しい人も少なくありません。基本的には業務時間外は労働者の自由な時間なので、仕事の連絡を返す必要はありません。詳しい内容については、以下の記事で説明しておりますので、参考にしてください。
関連記事:業務時間外の連絡は無視していい?違法性や連絡が来たときの対応を解説
他人との比較をやめて自分のペースで仕事を進める
職場には必ずと言っていいほど仕事が早い人や評価されやすい人がいます。しかし、そういった人と比べてばかりいると、自分を責めてしまいストレスの原因になります。ストレスを溜め込まないためには、他人と比較するのではなく、昨日の自分と比べるように意識を変えてみましょう。
目の前の業務に集中し、自分の成長を実感できれば、自然と自信もついてきます。自分のペースで着実に進めていけばよいのです。焦らず、着実に取り組む姿勢が長く働くうえでの安定にもつながります。
ポジティブな考え方を身につける
ストレスを感じやすい人ほど、物事を悪い方向に考えてしまいがちです。ミスを引きずったり、失敗を恐れすぎたりすることで、さらに不安やプレッシャーが大きくなります。そこで意識したいのがポジティブ思考です。
例えば、うまくいかなかったけど、次に活かせそうと前向きに捉えたり、今日はここまでできた、とできたことに目を向けたりする習慣が大切です。ポジティブな思考は、メンタルの安定に直結します。少しずつでも自分の思考の癖を見直してみましょう。
何でも相談できる人を見つける
一人で悩みを抱え込んでしまうと、どんどんストレスが大きくなってしまいます。そのため、職場でもプライベートでも何でも話せる人を見つけておくことはとても大切です。気軽に雑談できる同僚、話を聞いてくれる家族や友人がいるだけでも、心の支えになります。
ときには愚痴を言うことも、ストレスを外に出す有効な手段です。誰かに話すことで気持ちが整理され、客観的に物事を見られるようになります。信頼できる相談相手を大切にしましょう。
仕事のストレス発散方法に関するよくある質問
仕事のストレス発散方法に関するよくある質問を紹介します。
- 仕事のストレスを相談する相手は誰がいい?
- おすすめできないストレス発散方法は?
- ストレスチェック制度とは?
- 仕事でストレスが溜まりやすい人の特徴は?
仕事のストレスを相談する相手は誰がいい?
厚生労働省が発表「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、実際に相談相手として最も多いのが家族・友人(65.7%)です。次いで同僚(60.0%)、上司(54.3%)となっています。職場の人には言いづらい悩みがある場合は、外部のキャリアカウンセラーや心療内科、産業医を利用する方法もあります。
また、ストレスが原因で退職したい場合は退職代行サービス、転職したい場合は転職エージェントなどに相談してもよいでしょう。大切なのは、我慢せずに声を上げることです。自分一人で抱え込まず、誰かに話すことで、ストレスはぐっと軽減されます。
おすすめできないストレス発散方法は?
ストレス発散を目的にしていても、かえって心身に悪影響を及ぼす方法もあります。例えば、過度な飲酒や暴飲暴食、ギャンブル、衝動買いなどは一時的に気分が晴れても、根本的な解決にはなりません。習慣化すれば健康や金銭面でのトラブルに発展するリスクもあります。
また、SNSで愚痴や不満を公開する行為も、後にトラブルに発展する恐れがあるため避けたほうが安心です。短期的な快楽ではなく、自分を大切にする発散方法を選びましょう。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルスを守るために設けられた制度です。2015年12月から労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業所に対して実施が義務付けられました。内容は、職場でのストレス状況をアンケート形式で確認するもので、労働者自身が自分の状態を知る手助けになります。
高ストレスと判定された場合は、希望すれば医師との面談も可能です。ストレスの見える化によって、早期の気づきや職場環境の改善につながることもあります。受け身で終わらせず、結果をもとに自分自身の働き方を見直す機会として活用しましょう。
仕事でストレスが溜まりやすい人の特徴は?
仕事でストレスが溜まりやすい人の特徴は、以下の通りです。
- 責任感が強く、完璧主義な傾向がある
- 他人の評価を気にしすぎる
- 感情をうまく表に出せない
- 頼まれごとを断れず仕事を抱え込みがち
- 物事をネガティブに捉えやすい
- 休むことに罪悪感を持ちやすい
これらの特徴を持つ人は、日々の業務の中でストレスを溜め込みやすくなります。ストレスに対処するためには、まず自分の傾向を客観的に把握することが大切です。そのうえで、本記事で紹介したような発散方法を実施し、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
まとめ
仕事のストレス発散方法と溜め込まない心得について解説しました。仕事にストレスはつきものです。ストレスは溜め込んでもメリットがないので、少しずつ発散しましょう。発散方法も人によりそれぞれです。どの発散方法が自分に合っているか試しながら、取り組んでいきましょう。
もし、仕事のストレスが溜まりすぎて心身に不調が出る場合は、退職を検討してください。退職代行ほっとラインでは、無料で退職に関する悩みや相談を受け付けています。

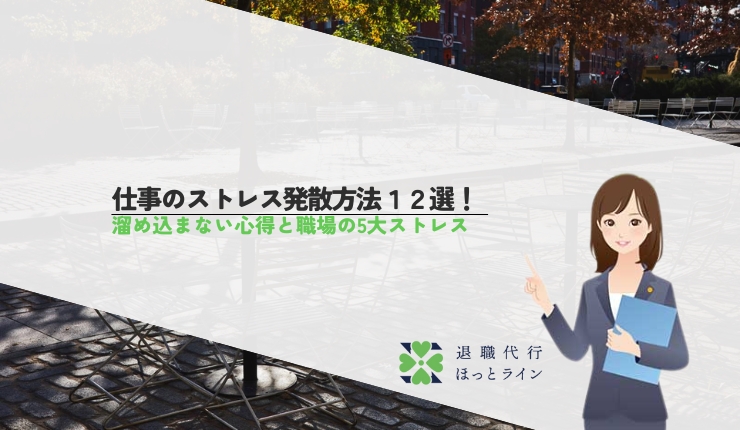



コメントを残す