上司からのパワハラや嫌がらせなどが原因で、退職したいと考える人は少なくありません。出社拒否してそのまま辞めたいけど、法律的に大丈夫なのか、そもそも辞められるのか不安になるところです。
結論からいえば、出社拒否から退職することは可能です。本記事では、出社拒否から退職する方法や手順について紹介します。出社拒否になる原因や出社拒否症についても解説しているので、参考にしてください。
・出社拒否から退職する方法は、2週間前に退職意思を示す、会社からの同意を得る、退職代行サービスを利用するなど
・出社拒否から退職するまでの手順は、電話やメールで会社に退職意思を伝え、退職届を郵送し、有休消化などを会社と交渉する
・出社拒否が認められるケースは、会社からハラスメントを受けた、精神疾患などの病気がある
・出社拒否になる原因は、職場の人間関係が悪化、過度な業務量とプレッシャー、やりがいを感じられない
目次
出社拒否から退職する方法は?即日退職は可能?
出社拒否から退職することは可能です。即日退職も可能ですが、いくつかの条件を満たさなければなりません。そのため、できるだけスムーズに退職するには、法的なルールや適切な手続きを理解しておくことが大切です。
- 法律上では2週間前に退職意思を示す必要がある
- 会社からの同意があれば即日退職も可能
- 退職代行サービスを利用すれば即日退職できる可能性がある
- 出社拒否が2週間以上続けば懲戒解雇のリスクがある
法律上では2週間前に退職意思を示す必要がある
退職を希望する場合、法律上は退職意思を示してから2週間後でなければ退職できません。これは民法第627条に定められています。会社の就業規則に「退職1カ月前に意思を示すこと」といった規定がある、会社の合意を得られていない場合でも2週間前に退職意思を示せば退職が成立します。
つまり、退職意思を示して2週間後であれば出社拒否しても、退職扱いとなるので処罰を科されることはありません。中には、退職意思を示してから出社拒否したいと思う人もいるでしょう。もちろん即日退職は可能です。即日退職の詳しいやり方については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:即日で退職することは可能?即日退職の条件・やり方・注意点をわかりやすく解説!
会社からの同意があれば即日退職も可能
法律上は2週間前の通知が原則ですが、会社側が同意すれば即日退職することも可能です。例えば、会社が「引き継ぎの必要がない」「辞めても業務の進行に支障がない」と判断すれば、その場で退職が認められることもあります。
また、有給休暇を消化することで、実質的に即日退職のような形にすることも可能です。
ただし、一般的には業務の引き継ぎや退職手続きなどが必要になるため、即日退職を認めてもらえないケースが多いです。
特に、就業規則に「退職は1カ月前までに申請すること」と明記されている場合、スムーズに退職できない可能性があります。そのため、即日退職を希望する場合は、会社の状況を考慮しながら交渉することが重要です。
退職代行サービスを利用すれば即日退職できる可能性がある
会社との交渉が難しい場合や、精神的に追い詰められていて自分で直接連絡を取るのが困難な場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。退職代行サービスは、本人に代わって会社に退職の意思を伝えてくれます。
それだけでなく、有給休暇や退職日の交渉など退職手続き全般をサポートします。
ただし、有給休暇や退職日の交渉は民間のサービスでは対応してもらえないため、弁護士が運営するサービスを利用しましょう。
退職代行を利用するれ、基本的に本人が直接会社とやり取りする必要はありません。そのため、上司と顔を合わせたくない場合や、強引な引き止めが予想される場合には、有効な手段となります。自分では交渉が難しい場合でも、代わりに交渉してもらい有給休暇の消化を提案することで、実質的に即日退職することが可能です。
出社拒否が2週間以上続けば懲戒解雇のリスクがある
出社拒否を続けたまま正式な退職手続きを取らない、いわゆるバックレてしまうと懲戒解雇される可能性があります。とくに、会社の就業規則にバックレたときの処罰が明記されていると、厳しい処分を受けることもあり得ます。懲戒解雇となると、履歴書に傷がつくだけでなく、失業保険の受給にも影響を及ぼすため、注意が必要です。
会社によっては、一定期間の無断欠勤を続けた場合に「自然退職」とみなす場合もありますが、これは企業ごとの就業規則により異なります。そのため、出社拒否したとしても退職意思は必ず伝えておくべきです。
退職したい旨を伝えておけば法律上問題ありませんので、直接上司に伝えなかったとしても退職届を郵送したり、電話で伝えたりしておきましょう。
出社拒否から退職するまでの手順
出社拒否から退職するためには、適切な手順を踏むことが大切です。会社とのトラブルを避けながら退職するために、意思表示の方法や必要書類の提出など、基本的な流れを押さえておきましょう。
- 1.電話やメールで会社に退職意思を伝える
- 2.退職届を郵送する
- 3.有休消化などを会社と交渉する
1.電話やメールで会社に退職意思を伝える
最初に行うことは、会社に退職意思を伝えることです。通常であれば、直属の上司に直接会って伝えるのが望ましいですが、出社拒否をしている場合は、電話やメールを活用する方法が現実的です。電話が難しい場合でも、メールや書面で明確に退職意思を伝えれば、正式な通知としての効力があります。
退職の意思を伝える際には、以下のポイントを押さえておくとスムーズに進められます。
- 退職したい具体的な日付を明記する
- 会社の就業規則に沿った退職手続きを確認する
- 必要があれば、有給休暇の消化についても相談する
会社側が退職を認めないケースも少なくありません。先に述べた通り、法律上は退職意思を表示から2週間が経過すれば、会社の同意がなくても退職が成立します。そのため、過度に引き止められた場合でも、冷静に対応し、正式な手続きを進めることが大切です。
退職を引き止められたときは、以下の記事で上手な断り方を紹介していますので参考にしてください。
関連記事:退職を引き止められる人の特徴とは?引き止められた際の上手な断り方を解説します
2.退職届を郵送する
退職の意思を伝えた後は、退職届を提出する必要があります。出社が難しい場合は、郵送でも可能です。郵送する際には、内容証明郵便を利用し、確実に会社に届いたことを証明できる形にするのが望ましいです。
退職届には、以下の内容を記載します。
- 退職意思と理由
- 退職希望日
- 提出日と本人の署名・押印
また、会社の就業規則によっては「退職願」と「退職届」を使い分ける場合があります。退職願は会社の承認を求めるものであり、撤回が可能ですが、退職届は提出した時点で効力が発生するため、原則として撤回できません。そのため、提出前に内容をしっかり確認し、トラブルにならないように注意しましょう。退職届の書き方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:退職届を出すタイミングはいつ?書き方や出し方、提出時期を徹底解説します
3.有休消化などを会社と交渉する
退職日までに有給休暇が残っている場合は、可能な限り消化するのが理想的です。有給休暇の消化は労働者の権利として認められているため、会社は拒否できません。引き継ぎなどを理由に有休消化を拒否した場合は、違法ですので訴えましょう。
有給休暇をスムーズに消化するためには、以下のような方法がおすすめです。
- 退職の意思を伝える際に、有給休暇の取得希望を明確に伝える
- 退職届とともに、有給休暇の申請書を提出する
- 会社側が有給休暇の消化を認めない場合は、労働基準監督署に相談する
また、即日退職を希望する場合は、退職日までの期間を有休消化することで、実質的にすぐに退職できる場合もあります。
出社拒否が認められるケース
出社拒否は基本的に労働義務の放棄とみなされ、無断欠勤が続けば懲戒処分の対象となることがあります。しかし、特定の理由がある場合には、正当な理由として認められるケースもあります。それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
- 会社からハラスメントを受けた場合
- 精神疾患など病気と診断された場合
会社からハラスメントを受けた場合
職場でパワハラやセクハラ、モラハラなどのハラスメントを受けている場合、精神的な苦痛が原因で出社できなくなることがあります。この場合、出社拒否が正当な行為とみなされる可能性が高いです。労働契約法第5条では、会社は労働者の安全に配慮する「安全配慮義務」があるとされており、ハラスメントが原因で働けない場合は、これに違反します。
ただし、ハラスメントの被害を会社に報告し、会社が適切な措置を取った場合、出社拒否が認められないケースが高いです。この場合は会社からの説明を受け、ハラスメント行為が改善されたか確かめましょう。
精神疾患など病気と診断された場合
精神疾患など病気や体調不良を原因に出社拒否することは、原則認められています。とくに医師の診断書があり、「就労困難」「一定期間の休養が必要」などの記載がある場合、会社は労働者に出社を強制できません。
そもそも体調を崩している社員に出社させるのは、安全配慮義務違反に該当する可能性が高いです。精神的な不調を感じたら、まずは病院で診察を受け、正式に診断を受けとりましょう。上司が出社拒否を拒んだとしても、診断書があれば納得してもらえやすくなります。
出社拒否症とは?特徴やチェックリスト
強いストレスや精神的な負担が大きければ、体が出社することを拒む場合があります。出社拒否症や自分が出社拒否症に当てはまっていないかチェックしてみましょう。
- 出社拒否症とは?
- 出社拒否症か診断チェック
- 出社拒否症になりやすい人の特徴
出社拒否症とは?
出社拒否症とは、仕事に対する強いストレスや不安が原因で、出社することが困難になる状態です。朝になると「会社に行かなければ」と思いながらも、外に出られない、最終的には欠勤してしまうのが特徴です。一般的には、精神的な負担が蓄積し、次第に出社すること自体が大きなハードルとなってしまいます。
この状態は一時的なものではなく、長期間続くのが一般的です。初期の段階では「今日はちょっと休みたい」と思う程度ですが、次第に「明日も行ける気がしない」「もう会社に行きたくない」という感情が強くなり、最終的には家から出られなくなります。
出社拒否症は、うつ病や適応障害などの精神疾患と関連していることも多く、無理に出社しようとすると症状が悪化することもあります。まずは医療機関に連絡して診断してもらいましょう。
出社拒否症か診断チェック
出社拒否症は、特定の診断基準があるわけではありませんが、以下のような症状が当てはまる場合、出社拒否症の可能性があると考えられます。自分の状態を確認するために、次のチェックリストを活用してください。
【出社拒否症チェックリスト】
- 朝になると強い憂鬱感や不安を感じる
- 仕事のことを考えると動悸や息苦しさを感じる
- 会社に向かおうとすると腹痛や頭痛が起こる
- 週末は元気だが、日曜の夜になると気分が落ち込む
- 出社しようとしても体が動かず、外に出られない
- 上司や同僚と会うのが怖く、避けたいと思う
- 仕事のミスや叱責を過度に恐れてしまう
- 会社の電話やメールを見るのがつらい
- 出社を考えると涙が出たり、パニックになったりする
- 「このまま会社を辞めたほうがいいのでは」と何度も考える
3つ以上当てはまる場合は、精神的な負担が大きくなっている可能性があります。5つ以上当てはまる場合は、出社拒否症の傾向が強いと考えられるため、無理をせず、カウンセリングや医師の診察を受けることをおすすめします。
出社拒否症になりやすい人の特徴
出社拒否症は、誰にでも起こりうるものですが、特に以下のような特徴を持つ人は発症しやすいです。
- 責任感が強く、完璧主義な人:責任感が強い人ほどミスを許せず自分を追い込みがちになる。期待に応えようと無理をして心身のバランスを崩す。
- 人間関係にストレスを感じやすい人:ハラスメントを受けている場合や、職場の雰囲気になじめず孤立し、ストレスになる。
- 環境の変化に弱い人:新しい環境に馴染めず不安やプレッシャーになる。
- 慢性的に体調不良の人:体調不良が多く仕事を休みがちになると休み癖がつく。
出社拒否症は、自分の力だけでは改善が難しいため、医療機関やカウンセリングを利用しましょう。
出社拒否になる原因
出社拒否は、職場の人間関係や業務量の負担、仕事への意欲低下などが原因になることが多いです。これらの要因が積み重なることで、仕事に対するモチベーションが低下し、最終的に出社すること自体が困難になってしまうことがあります。
- 職場の人間関係のトラブル
- 過度な業務量とプレッシャー
- 仕事にやりがいを感じられない
職場の人間関係のトラブル
職場の人間関係は、出社拒否の大きな要因の一つです。上司からのパワハラや同僚とのトラブルがある場合、職場に行くこと自体が苦痛になり、次第に足が遠のいてしまいます。
例えば、上司から理不尽な叱責を受け続けたり、過度なプレッシャーをかけられたりすると、自信を失い、仕事に対する意欲が低下してしまいます。また、職場内で孤立していたり、集団いじめにあっていたりすると、仕事を休みたいと思うようになるでしょう。
さらに、モラハラやセクハラなどの問題がある場合、精神的なダメージが深刻になり、出社どころか、日常生活にも支障をきたすことがあります。このような状況に陥った場合、社内の相談窓口や労働基準監督署に相談することが重要です。
過度な業務量とプレッシャー
仕事の量が多すぎたり、プレッシャーが強すぎたりすることも、出社拒否の原因です。残業が常態化している職場では、仕事とプライベートのバランスが崩れ、精神的・肉体的に疲弊しやすくなります。
例えば、一人で担当する業務量が多すぎる場合、どれだけ頑張っても仕事が終わらず、常に追い詰められている感覚に陥ります。加えて、「納期に間に合わせなければならない」「ミスをしてはいけない」といったプレッシャーが重なると、仕事するのが嫌になり普段通りに働けません。
また、過度なプレッシャーがかかる職場では、ストレスが蓄積し、うつ病や適応障害を引き起こすリスクも高まります。このような状態が続くと、出社すること自体が困難になり、最終的には仕事を辞めることを考えるようになるケースも少なくありません。業務量が多すぎると感じた場合は、上司に相談し、負担を軽減する方法を模索することが重要です。
仕事にやりがいを感じられない
仕事に対するやりがいを感じられないと、モチベーションが低下し、出社拒否につながります。単調な業務を繰り返すだけで達成感が得られない場合や、自分の成長を実感できない職場では、仕事に対する意欲が徐々に薄れがちです。
例えば、自分が興味のない仕事を続けていると、「この仕事を続けても意味がないのでは」と考えるようになり、次第に出社すること自体が無意味に感じられることがあります。また、頑張っても評価されない環境では、モチベーションを維持するのが難しくなり、「どうせやっても無駄だ」と思うようになります。
このような場合、異動を希望したり、キャリアチェンジを考えたりするのも一つの方法です。また、自分が本当にやりたいことは何かを見つめ直し、必要であれば転職を検討することも視野に入れるとよいでしょう。やりがいを感じられない状態が続くと、最終的には出社拒否に陥る可能性があるため、早めに対策を講じることが大切です。
出社拒否から退職する方法に関するよくある質問
出社拒否から退職する方法に関するよくある質問について見ていきましょう。
- 出社拒否から退職しても退職金をもらえる方法はある?
- 出社拒否から退職する場合、退職理由はどう書けばいい?
- 会社が退職届を受け取ってもらえないときは?
出社拒否から退職しても退職金をもらえる方法はある?
退職金の支給は、法律ではなく就業規則や雇用契約によって決まります。そのため、出社拒否から退職した場合でも、退職金の支給条件を満たしていれば受け取ることが可能です。まずは就業規則に退職金に関する記載がないか確かめましょう。
退職金をもらってから退職する方法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:ボーナス・賞与をもらって辞めるのは問題なし?逆算スケジュールやポイントを解説します
出社拒否から退職する場合、退職理由はどう書けばいい?
退職届に記載する退職理由は、一般的には「一身上の都合」とするのが無難です。「出社拒否」や「精神的に限界」などの詳細な理由を記載する必要はありません。退職理由は会社側に対する配慮も必要ですが、法律上はどのような理由であっても退職する権利があります。
退職届の書き方に悩んだ場合は、シンプルな表現を心がけましょう。
会社が退職届を受け取ってもらえないときは?
会社が退職届の受け取りを拒否することは法律上認められていません。労働者には退職する自由があり、民法627条に基づき、原則として2週間前に退職意思を示せば辞められます。もし会社が退職届を受け取らない場合は、以下の方法を試してください。
- 内容証明郵便で送付する
- メールやFAXで送る
- 退職代行サービスを利用する
会社側が退職を認めない態度を取ったとしても、法律上は労働者の退職の権利が優先されます。冷静に対処し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
まとめ
出社拒否から退職する方法について紹介しました。出社拒否から退職することは可能です。しかし、適切な手続きをせずバックレてしまうと、懲戒解雇などのリスクがあるので注意しましょう。
会社の同意があれば、出社拒否から即日退職も可能です。しかし、会社と交渉するのに自信のない人は退職代行サービスを利用しましょう。退職代行サービスであれば、退職手続きを代行してもらえるので、直接会社とやり取りする必要がありません。
ストレスの軽減や転職活動に専念できるためおすすめです。

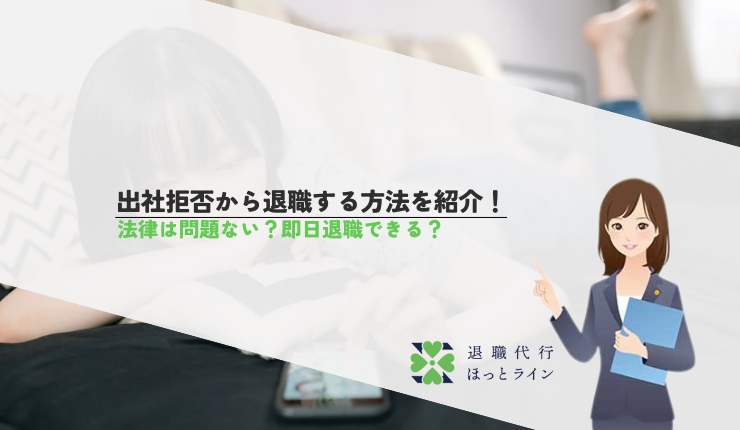



コメントを残す