「何のために仕事をするのだろう」「この会社で働く意味があるのかわからない」といった悩みを誰しも一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。仕事する意味を見出せない状態が続くと、モチベーションが低下し、退職を検討する傾向があります。
このような状態に陥ったときは、何のために働いているのか、働く目的を再確認しましょう。本記事では、働く目的を12つ紹介します。仕事する意味がわからなくなったときは、本記事を参考に、気持ちの整理をしてください。
・働く目的は、収入を得る、生きがいを見つける、誰かの役に立ちたい、自立するため、家族を支えるため、安定した未来をつくるためなど
・仕事する意味がわからなくなる原因は、正当に評価されない、やりたい仕事ができない、プライベートが充実していない
・仕事する意味がわからなくなったときに試してほしい行動は、職場の人に働く目的を聞く、「楽しい・おもしろい」瞬間を探す、転職して環境を変える
目次
仕事する意味がわからない!12の働く目的
「仕事をする意味がわからない」という悩みを持つ人は多くいます。毎日モチベーションを維持することは簡単ではありません。しかし、仕事にはさまざまな目的があり、人によって働く目的が異なります。
- 1.収入を得るため
- 2.社会の一員として役割を果たすため
- 3.自分の能力や才能を発揮するため
- 4.生きがいを見つけるため
- 5.自分のやりたいことを実現するため
- 6.誰かの役に立ちたいため
- 7.社会的なつながりを求めるため
- 8.自立するため
- 9.家族を支えるため
- 10. 安定した未来をつくるため
- 11.仕事を通じて新しい経験を得るため
- 12.周りが働いているから仕事する
上記の12の目的を考えながら、自分がどの目的に共感するのかを見極めてみましょう。
1.収入を得るため
内閣府が発表した「国民生活に関する世論調査(令和6年8月調査)」によれば、「お金を得るために働く」と答えた人は全体の62.9%です。つまり、多くの人は収入を得ることを目的に働いています。
働くことで得られる給与や報酬は、生活を支えるために不可欠です。家賃や食費、光熱費、教育費など、日々の生活に必要な支出をまかなうためには、定期的な収入が必要になります。また、将来のために貯金をしたり、趣味や娯楽に使ったりすることも収入を得る目的の一つです。
生活が安定していないと、精神的にも不安定になりがちですが、収入を得ることでその不安を和らげ、安定した生活を送ることが可能になります。収入を得るために働くことは、非常に現実的で重要な目的と言えます。
参考元:国民生活に関する世論調査(令和6年8月調査) | 世論調査 | 内閣府
2.社会の一員として役割を果たすため
内閣府の同調査では、「社会の一員として、務めを果たすために働く」と答えたは全体の10.5%と、3番目に多くなっています。私たちは、家族や地域社会、さらには広く社会全体の一員として生きています。仕事を通じて、社会に貢献しているという感覚を持つことで、やりがいや自己肯定感を得られるのです。
例えば、教師や医師、エンジニアなど、それぞれの職業には社会に必要とされる役割があり、その役割を果たすことで社会全体が成り立っています。自分の仕事が誰かのためになっていると感じられれば、仕事をする意味がより深く実感できるでしょう。
自分が社会にどのように貢献しているのかを意識しながら働くことが、仕事のモチベーションを高めることにつながります。
3.自分の能力や才能を発揮するため
人はそれぞれ得意分野や特技を持っており、その能力を仕事で活かすことで、仕事に対する満足感や誇りを感じられます。例えば、クリエイティブな才能を活かしたデザイン業務や、分析力を活かしたデータ解析の仕事など、自分の強みを活かした仕事です。
自分のスキルを最大限に活用できる職場環境に就ければ、成長を実感できると同時に、他者との比較ではなく、自分の成長に集中できるようになります。
4.生きがいを見つけるため
内閣府の同調査では、「生きがいをみつけるために働く」と答えたは全体の13.3%と、2番目に多いです。仕事を通じて生きがいを見つけることは、単なる生活のためだけでなく、精神的な充実感を得るためにも重要です。
毎日の仕事が無意味に感じることもありますが、自分が心から情熱を注げる仕事を見つけることで、仕事そのものが人生の目的となり、やりがいを感じられます。例えば、医療や福祉、教育など、人々の生活に直接影響を与える仕事です。
自分の仕事が誰かの役に立っているという実感を得られやすく、生きがいへと繋がります。
自分の生きがいとして働ければ、職場に向かうことが楽しみになり、日々の努力が意味あるものだと感じられるのです。生きがいを仕事の中で見つけることで、仕事をしている時間が充実感で満たされ、心身ともに健康を保てます。
5.自分のやりたいことを実現するため
収入を得るために働く人は多いですが、仕事をするもう一つの大きな目的は、自分のやりたいことを実現することです。近年では自分の好きなことで生きていくことをコンセプトに、YouTuberを目指す人が増えています。
自分のやりたいことがそのまま仕事として働けるのが理想的です。
多くの人が、生活のために働きつつ、自分の夢や目標を達成する手段としても仕事を活用しています。例えば、自分のビジネスを始めたい、アーティストとして活躍したい、旅行をして世界を学びたいという目標を持つ人もいるでしょう。
仕事を通じてスキルを磨き、必要な資金を稼ぐことで、その目標を実現するためのステップを踏めます。仕事自体を自己実現の手段として捉えることで、日々の努力が無駄ではないと感じ、やりがいを見いだせます。自分のやりたいことを実現するためには、仕事での成功やキャリアの積み重ねが不可欠です。そのためには、一つ一つの仕事に対して情熱を持ち、努力を続けることが重要となります。
6.誰かの役に立ちたいため
他人の役に立つことに喜びを感じる人は多いです。仕事を通じて、誰かを助けたり、支えたりすることは、大きなやりがいを生む要因となります。とくに医療・介護・保健士・キャリアアドバイザーなどは、自分の仕事が他人の役に立っているいう実感を持ちながら働ける仕事です。
他人を助けることは、自己肯定感を高めるだけでなく、心の中での充実感を生む大きな原動力となります。また、誰かの役に立っているという実感は、仕事に対するモチベーションを高め、困難な状況に直面しても乗り越えようという意欲を与えてくれます。
7.社会的なつながりを求めるため
社会的なつながりを求めるために仕事をする人も少なくありません。人は孤立していると精神的に不安定になりがちです。しかし、職場という場での交流を通じて、他者との関わりを深めれば孤独感を軽減できます。
とくに、チームで働く仕事や、同じ目標に向かって協力することが求められる環境では、人間関係が重要です。社会的なつながりは、仕事をしている上での支えとなり、困難な時期でも励まし合える仲間を得られます。
また、同じ職場内での関係が広がることで、ネットワークを築き、将来的には新たなキャリアチャンスやビジネスの機会を得ることも可能です。職場で得られる社会的なつながりは、仕事のやりがいや人生の充実感にも影響を与えるでしょう。
8.自立するため
仕事をすることにより、自分の力だけで生活するための収入を稼ぐことになるので、自立しているといえます。成人として独立した生活を送りたいと思う人にとって、収入を得ることは自立の基本です。
自分でお金を稼ぎ、自分の生活を支えることは、他人に依存しない人生を送るために必要な一歩です。とくに親に心配をかけたくないと思っている人は、仕事する目的の一つになります。自立することで精神的に強くなり、自分の成長にもつながります。
また、自立するためには仕事を続けることが不可欠であり、仕事のスキルを高め、自己管理能力を磨くことが重要です。自立を果たすことで、自分の人生を自分の手で切り拓く力を得るられ、充実した生活を送れます。
9.家族を支えるため
家庭を持っている人は、家族を支えるために働くことが仕事をする大きな目的の一つです。子供がいる親は家族を養う責任があります。責任感を持って働くことは、日々のモチベーションを高める要因にもなるでしょう。
仕事を通じて得た収入は、家族の生活を支えるために使われるため、自分の努力が直接的に家族の幸福に繋がっていると実感できます。また、家族を支えることで、自己肯定感や誇りを感じられ、仕事に対する意欲を高められます。
家族との関係や責任を大切にしながら働くことは、仕事の意味をより深く感じさせ、日々の努力が無駄ではないことを強く実感できるようになるのです。
10. 安定した未来をつくるため
仕事をして得る収入は、現在の生活だけでなく安定した未来を築くための礎となります。生活費を稼ぐことはもちろん、将来に向けて貯金をしたり、投資をしたりすることで、経済的な安定を目指すことも重要です。
老後の生活に対する不安を軽減するために、安定した収入源を確保しなければなりません。現代では、働いているうちに自己投資を行い、キャリアアップを目指すことで、将来的に経済的な自由を手に入れることも可能です。
また、安定した職を持ち、経済的に自立することは、生活の中での不安やストレスを減らし、安心した日常を送るためにも必要不可欠です。仕事を通じて安定した未来を築くことは、将来の家族や自分自身を守るためにも大きな意味があります。
11.仕事を通じて新しい経験を得るため
仕事をすることは、単に日々の生活を支えるための手段ではなく、新しい経験を得る大きなチャンスでもあります。仕事を通じてさまざまなスキルを学んだり、異なる業界や職種での経験を積んだりすることで、自分の成長を感じられるでしょう。
とくに転職や異動などを通じて、新しい環境に身を置くことは、さまざまな視点や価値観を得る絶好の機会です。また、職場での人間関係やチームワークを通じて、コミュニケーション能力やリーダーシップを磨くこともでき、これらの経験が今後のキャリアや人生において貴重な財産となります。
新しい経験を得ることは、自己満足や成長感を得るための重要な要素であり、人生の中で新しい挑戦を楽しむためのエネルギー源となります。仕事を通じて自分を高め、さまざまな可能性を広げることで、毎日がより充実したものとなるでしょう。
12.周りが働いているから仕事する
「周りが働いているから仕事する」「働くことが一般的だから」といった理由で仕事する人も少なくありません。周囲の同僚や友人が活発に働いている姿を見て、自分も働かなければいけないと感じることがあります。
社会の中で自分だけが働かずにいると、疎外感や自己不信を感じることがあり、そのプレッシャーから仕事を始めることも少なくありません。周囲が働いていることで、社会の一員としての責任を感じ、働くことに対する意識が高まります。
このような社会的なつながりやプレッシャーは、ある意味で良い刺激となり、自己成長を促すことにも繋がるのです。周りの人たちと協力しながら働くことは、自己実現や社会貢献に繋がり、仕事をしている意味を感じるきっかけになります。
仕事する意味がわからなくなる原因は?
仕事に対してやりがいや意義を感じられなくなると、何のために働いているのかわからなくなります。とくに、一生懸命努力しているのに正当に評価されなかったり、自分のやりたい仕事に就けなかったりすると、仕事への意欲が低下してしまいます。
こうした状況が続くと、仕事の目的を見失い、最悪の場合は心身ともに疲弊してしまうこともあるため、原因を見極め、適切に対処することが大切です。
- 仕事を頑張っているのに評価されない
- 自分のやりたい仕事ができない
- 仕事ばかりでプライベートが充実していない
仕事を頑張っているのに評価されない
仕事を一生懸命頑張っているにもかかわらず、正当に評価されないと、モチベーションが低下します。とくに努力している自分が評価されず、まったく成果を上げていない同僚が評価されると、仕事する意味がわからなくなるでしょう。
上司や会社の評価制度に問題がある場合、能力よりも年功序列や人間関係が優先されることも少なくありません。
また、実力よりも社内の政治的な要素が評価に影響を与えるような環境では、真面目に努力すること自体が無意味に感じられてしまいます。その結果、やりがいを失い、仕事に対する意義を見失うことに繋がるのです。
このような状況を改善するためには、まず評価基準を確認し、自分の努力が適切に認識されているかを見極めることが大切です。また、正当に評価されない環境が続くのであれば、転職や異動を視野に入れることも一つの方法です。
自分の頑張りがしっかりと認められる環境に身を置くことで、再び仕事に対する意味ややりがいを感じられるようになるでしょう。
自分のやりたい仕事ができない
理想とする仕事に就けなかったり、希望とは異なる業務を任されたりすると、仕事をする意味が分からなくなることがあります。とくに、新卒で入社した会社や転職先で、自分が思い描いていたキャリアと現実が大きく異なることが原因で退職する人は少なくありません。
例えば、新卒(大学卒)の就職後3年以内の離職率は34.9%です。約3人に1人は就職後3年以内に退職しています。やりたい仕事があるにもかかわらず、会社の都合で別の業務を任されることも少なくありません。
組織の一員として働く以上、自分が希望だけを優先することは難しいものの、まったく興味のない仕事を続けることは大きなストレスになります。さらに、異動や配置転換によって意図しない部署に配属された場合、仕事へのモチベーションが低下してしまうでしょう。
こうした状況を改善するためには、まず現在の仕事の中に少しでも自分の興味ややりがいを見つける努力が必要です。また、スキルアップや資格取得を通じて、自分の希望する仕事に近づくための準備を進めることも重要です。どうしても現在の職場でやりたい仕事ができないのであれば、転職を考えましょう。
自分が本当にやりたいことを実現できる環境を見つけることで、仕事に対する意義を見出せるでしょう。
仕事ばかりでプライベートが充実していない
生活費などプライベートに使うお金を稼ぐために、働いている人は多くいます。これは、生活のためやプライベートの時間を充実させるためです。しかし、労働時間が長すぎるとプライベートの時間を確保することが難しくなります。
長時間残業が当たり前の会社では、家族や友人との時間を持てないため、趣味やリラックスする時間が取れません。プライベートの時間を充実させるために働いているのに、仕事が生活のすべてのようになると、「何のために働いているのか分からない」と思うようになってしまうのです。
また、仕事中心の生活が続くと、精神的な余裕がなくなり、ストレスが蓄積されやすくなります。休日も仕事のことが頭から離れず、心身ともにリフレッシュできない状態が続くと、次第に仕事自体が嫌になり、モチベーションの低下を招いてしまうでしょう。
こうした状況を改善するためには、意識的に仕事とプライベートのバランスを取ることが重要です。業務の効率化を図り、残業を減らす努力をすることで、自分の時間を確保しやすくなります。休日に来る会社の連絡は無視して構いません。プライベートの時間を確保するためにも休日は仕事から完全に離れましょう。
関連記事:業務時間外の連絡は無視していい?違法性や連絡が来たときの対応を解説
仕事する意味がわからなくなったときに試してほしい3つの行動
仕事に対する意欲が低下し、働く意味を見失ってしまうことは誰にでも起こり得ることです。どれだけ頑張っても評価されなかったり、単調な業務が続いたりすると、モチベーションを維持するのが難しくなります。そのようなときに大切なのは、自分の考え方や視点を少し変えてみることです。
仕事に対する意識を見直し、新たな発見を得ることで、働くことへの意味を再確認できるかもしれません。
- 1.職場の上司や同僚に何のために働いているか聞く
- 2.仕事中に「楽しい」「おもしろい」と思える出来事をまとめる
- 3.働く環境を変えてみる
1.職場の上司や同僚に何のために働いているか聞く
仕事する意味が分からなくなったとき、一人で悩みを抱え込んでもなかなか答えが見つからないことがあります。そのようなときは、身近な上司や同僚に「何のために働いているのか」と聞いてみるのも一つの方法です。
人によって仕事に対する考え方や価値観は異なりますが、周りの考えを知ることで新たな視点を得られる可能性があります。
例えば、ある人は「家族を養うため」と答えるかもしれませんし、別の人は「収入のため」と話すかもしれません。同じ職場で働いている人の考えを聞けば、共感できる部分が見えることもあります。
また、上司に相談することで、キャリアの方向性や目標を再確認することも可能です。上司がどのような考えを持って働いているのかを知ることで、自分自身の仕事への向き合い方を見直すきっかけになります。明確な答えが見つからなかったとしても、誰かと話すことで気持ちが整理され、悩みが少し解消することもあります。
2.仕事中に「楽しい」「おもしろい」と思える出来事をまとめる
仕事する意味を見失ったときは、仕事の中にある小さな楽しさや面白さを意識してみることが大切です。日々の業務の中には、些細なことでも「楽しい」「面白い」と感じられる瞬間があるはずです。それを見つけるために、仕事の中でポジティブな出来事を記録してみましょう。
例えば、取引先から感謝の言葉をもらったときや、難しい業務をやり遂げたときなど、自分が「少しでも嬉しい」と思えた瞬間を書き留めると、仕事の中にやりがいを見出しやすくなります。また、同僚と協力して何かを成し遂げたときの達成感や、業務がスムーズに進んだときの満足感なども振り返ると、仕事に対する意識が変わるかもしれません。
仕事に対する意味が分からなくなる原因の一つは、「ネガティブな面ばかりに目を向けてしまうこと」です。嫌なことばかりに気を取られていると、仕事の価値を見失いがちですが、意識的に良い出来事を探すことで、前向きな気持ちを取り戻せることもあります。
仕事の中で「楽しい」「やりがいがある」と思える瞬間を積極的に見つけることで、働くことの意義を再確認できるでしょう。
3.働く環境を変えてみる
仕事する意味を見失ったときは、今の環境が自分に合っていない可能性もあります。職場の人間関係や業務内容に違和感を感じている場合、そのまま同じ環境で働き続ける必要はありません。このような状況に陥っているなら、思い切って働く環境を変えてみることを検討してみましょう。
環境を変えるといっても、すぐに転職する必要はありません。まずは社内で異動希望を出したり、業務の進め方を工夫したりするだけでも、気分が変わることがあります。職場のレイアウトを変える、仕事の進め方を見直す、リモートワークを取り入れるなど、小さな変化を加えることから始めてみましょう。
それでも仕事に対する意欲が戻らない場合は、転職を視野に入れるのも選択肢の一つです。自分の価値観やスキルに合った職場に移ることで、再び仕事にやりがいを感じられるようになるかもしれません。働く環境を変えることで、新たな気持ちで仕事に向き合えるようになり、仕事の意味を再確認できることもあります。
仕事に対する気持ちが迷子になったときは、自分を取り巻く環境を見直し、少しずつでも改善していくことが重要です。
「仕事する意味がわからない」に関するよくある質問
「仕事する意味がわからない」に関するよくある質問を紹介します。
- どのような仕事が理想?
- 現在の仕事(収入)に満足している人は多い?
どのような仕事が理想?
内閣府が発表した「国民生活に関する世論調査(令和6年8月調査)」によれば、「収入が安定している仕事」が一番理想的だと答えた人は60.8%です、次いで「私生活とバランスがとれる仕事(54.9%)」、「自分にとって楽しい仕事(52.3%)」、「自分の専門知識や能力がいかせる仕事(34.1%)」となっています。
年齢別でみると10~20代は「自分にとって楽しい仕事」、30~40代は「私生活とバランスがとれる仕事」が理想的な仕事です。
現在の仕事(収入)に満足している人は多い?
内閣府の同調査によると、現在の仕事(収入)に満足している人は34.9%、不満を感じている人は64.5%です。性別や年齢に関係なく、収入に満足していない人のほうが多くいます。そのため、現職の収入が相場よりも低いと仕事する意味がわからなくなる可能性があります。
まとめ
働く目的や仕事する意味がわからなくなったときに試してほしい行動について紹介しました。仕事する意味や働く目的を見失う人は少なくありません。働く目的は人それぞれであり、「収入を得る」「家族を支える」「生きがいを見つける」など、さまざまです。
どれが正解というわけではなく、自分にとって納得できる理由を見つけることが大切です。
現職に何らかの問題がある場合は、その問題が原因で仕事する意味を見失っている可能性があります。この場合は、転職して環境を変えることも視野に入れておきましょう。

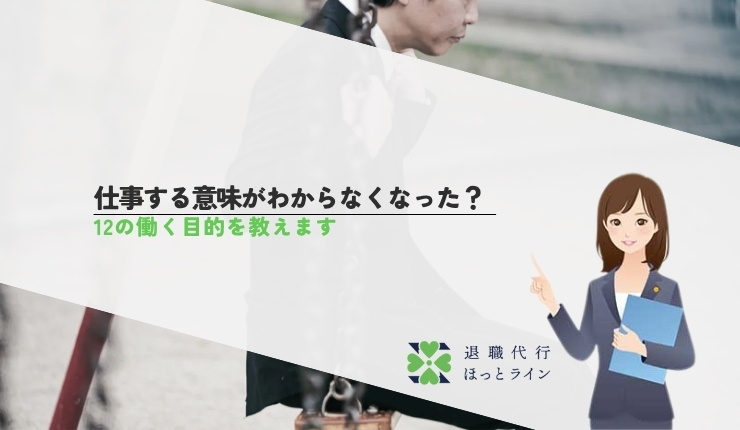


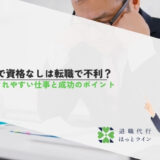
コメントを残す