初めて退職する人は、退職が決まったら何をすればいいのか悩んでしまうのではないでしょうか。退職手続きは思った以上にやることが多く、スムーズに進めるには計画的に行うことが大切です。本記事では、退職が決まったらやるべきことを時系列で徹底解説します。
退職時によくあるトラブルや疑問なども紹介していますので、参考にしてください。
・退職が決まったらやるべきことは、業務の引き継ぎの計画を立てる、有給消化のスケジュールを決める、返却物を確認するなど
・【退職後に転職する場合】退職が決まったらやるべきことは、入社準備のための事務手続き、新しい環境に備える準備を整える、入社後のキャリアプラン設計するなど
・【退職後に転職しない場合】退職が決まったらやるべきことは、健康保険・年金の切り替え、税金に関する手続き、失業保険の申請手続きなど
目次
退職が決まったらやるべきこと【退職日までの準備編】
退職意思が受理されたら、円満退職に向けてやるべきことを計画的に進めましょう。業務の引き継ぎや社内手続き、必要書類の確認など、退職日までに済ませるべき準備は多岐にわたります。また、同僚や上司との関係を整理し、スムーズな退職を目指すことも重要です。
- 退職意思が受理されたら最初にやるべきこと
- 退職日までに有給消化するスケジュールを決める
- 退職日までに整理しておくべき人間関係
- 退職日の最終確認とやるべきこと
退職意思が受理されたら最初にやるべきこと
退職意思が正式に受理されたら、最初にやるべきことは、退職日までのスケジュールを確認し、業務の引き継ぎや必要書類の準備を早めに始めることです。とくに、有休消化の計画や社内規定の確認は、後になってトラブルになることがあるため、早い段階で上司や人事担当者と話し合っておきましょう。
業務の引き継ぎ計画を立てる
円満退職を目指すには、引き継ぎ計画をしっかり立てることです。まず、現在担当している業務をリストアップし、引き継ぎが必要な内容を整理します。とくに、プロジェクトの進捗状況や取引先とのやりとりは、詳細にまとめておくことが求められます。
引き継ぎする際は、一度にすべてを説明するのではなく、時間をかけて少しずつ引き継いでいくのが理想的です。マニュアルを作成したり、実際に業務をやって見せたりすることで、相手の理解が深まります。
必要な書類を確認する
一般的に、退職時には「退職願」または「退職届」を提出する必要がありますが、会社によってはフォーマットが決まっていることもあるため、事前に確認しておきましょう。
また、退職後に必要になる書類として、離職票や雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書などがあります。これらは退職後の手続きに必要不可欠なため、受け取り忘れがないようチェックリストを作成すると便利です。
とくに、離職票はハローワークでの失業保険の申請に必要ですし、源泉徴収票は確定申告や転職先の年末調整で求められることがあります。書類の受け取り漏れがないよう、事前に人事担当者に確認しておきましょう。
職場でのコミュニケーションを整理する
まず、上司や同僚、取引先など、関わる人に対して退職の報告を適切なタイミングで行いましょう。会社のルールや職場の雰囲気によっては、言うべき相手や順番が決まっていることもあるため、慎重に進めることが求められます。
また、メールやチャットツールの整理も忘れてはいけません。業務で使用していたデータや共有フォルダの整理を行い、必要な情報を後任者にスムーズに引き継げるよう準備しておきましょう。
取引先への連絡も重要なポイントです。関係者に迷惑をかけないよう、上司と相談しながら適切なタイミングで退職の報告を行い、後任者の紹介をすることで、円滑な引き継ぎができます。
退職日までに有給消化するスケジュールを決める
退職が決まった後、残っている有給休暇をどのタイミングで消化するかを計画することは非常に重要です。
最初に、残っている有給休暇日数を確認します。その後、退職日までの期間を考慮し、どのタイミングで有給を取るのが最も効率的かを決めます。
有給休暇を計画的に消化するには、業務に支障をきたさないよう、上司やチームメンバーと調整しながらスケジュールを組むことが大切です。例えば、退職日の直前に有給を取ると、引き継ぎが完了していないままで退職することになり、後任者への負担を増やす可能性があります。そのため、退職日から数週間前から有給休暇を使い始め、引き継ぎの時間を確保しておくとスムーズです。
また、残っている有給を一気に消化するのではなく、数日ずつ取ることで、業務の引き継ぎと自分の退職準備のバランスを取りやすくなります。有給を取るタイミングは、会社やチームの状況に応じて調整が必要ですが、できるだけ早めにスケジュールを決め、必要な手続きも忘れずに進めることが大切です。
退職日までに整理しておくべき人間関係
退職が決まった後、職場での人間関係の整理は、円満退職を目指すために非常に重要です。
まず、上司への挨拶は欠かせません。退職が決まった時点で、感謝の気持ちを伝えるとともに、これまでのサポートに対するお礼を述べることが大切です。上司はあなたの退職後の評価に影響を与える重要な人物ですので、感謝の言葉をしっかり伝えておくと良いでしょう。退職理由がネガティブな場合でも、感謝の気持ちを忘れずに伝えることが、円満退職には欠かせません。
また、取引先や顧客にも退職を伝えることが必要です。とくに長期間お世話になった取引先には、退職後に担当者が変更になることを事前に伝え、後任者の紹介をすることが信頼を損なわないために重要です。取引先との関係が今後も続く場合は、丁寧に挨拶し、退職後も引き続き良好な関係を築けるよう努めましょう。
退職日の最終確認とやるべきこと
退職日が迫ってきたら、最後の確認と準備をしっかり行いましょう。退職日当日は、必要な手続きを漏れなく終わらせることが大切です。退職日には退職後のスムーズな生活がスタートできるように、しっかりとした準備を進めておくと、心置きなく次のステップに進めます。
退職時の持ち物チェック
退職時には、職場にある自分の持ち物を整理しておく必要があります。オフィスのデスクやロッカーにある私物や業務用の資料など、退職後に必要ないものは持ち帰り、会社に返却するものをきちんと整理しておきましょう。パソコンや携帯電話、IDカード、名刺など、退職後に使わなくなるものは返却します。
また、退職時に退職書類を受け取る準備も忘れてはいけません。退職証明書や離職票、源泉徴収票など、退職後の手続きに必要な書類は、必ず受け取るようにしましょう。これらは転職活動や失業保険の申請、税務手続きなどに必要となりますので、後から受け取り忘れがないように注意が必要です。
退職書類の受け取り
退職日に最も重要なのが、退職書類を確実に受け取ることです。退職証明書や離職票、源泉徴収票などは、退職後の生活に大きな影響を与えるため、必ず確認して受け取ります。離職票は失業保険を受け取るために必要となるため、必ず受け取り忘れのないようにしましょう。
また、退職書類には誤りがないか確認することも重要です。万が一、誤りがあった場合には、早めに人事部門に連絡して訂正を依頼しましょう。
【退職後に転職する場合】退職が決まったらやるべきこと
退職後に転職を控えている場合、転職先へ入社するための準備が必要です。新しい職場でのスタートを成功させるためには、事務手続きの確認や生活リズムの調整、キャリアプランの見直しなど、事前にやるべきことが多くあります。入社前の期間を有効に活用し、余裕を持って準備を進めることが、転職後のスムーズな適応につながります。
- 入社準備のための事務手続き
- 新しい環境に備えた準備
- 生活リズムと体調管理
- 入社後のキャリアプラン設計
入社準備のための事務手続き
新しい職場での勤務開始に向けて、各種事務手続きを早めに進めておくことが重要です。まず、入社先から提出を求められる書類を確認し、必要なものを揃えましょう。多くの場合、雇用契約書、年金手帳、マイナンバー、住民票、健康診断書などが必要になります。
基本的には、転職先へこれらの書類を提出することで、転職先が事務手続きを済ませてくれます。ただし、退職日と転職先の入社日に1日でも空白の期間が発生する場合、健康保険や年金の切り替えが必要です。
新しい環境に備えた準備
新しい職場でスムーズなスタートを切るためには、環境の変化に備えた準備が欠かせません。まず、新しい会社の業務内容や企業文化を事前に理解しておくことが大切です。会社のホームページや社員向けのガイドラインなどを確認し、求められるスキルや業務フローを把握しておくと、入社後の適応がスムーズになります。
また、業務で必要となるスキルや知識を身につけておくことも重要です。例えば、新しい職場で使用するソフトウェアの操作方法や業界特有の知識などを事前に学習しておくことで、業務に早く慣れやすくなります。
通勤ルートの確認もしておきましょう。自宅から職場までの移動時間や交通手段を事前に調べ、スムーズに通勤できるよう準備しておくと、初出勤の日に焦ることがありません。余裕を持って出発できるように、実際に通勤経路を試しておくとより安心です。
生活リズムと体調管理
転職後に良いスタートを切るためには、体調管理と生活リズムの調整が欠かせません。
まず、起床時間と就寝時間を整え、規則正しい生活を心がけましょう。出社時間に合わせて起床時間を調整し、仕事が始まる時間帯に活動できるようにしておくことが理想的です。次に、食生活の見直しも重要です。健康的な食事を心がけ、バランスの取れた栄養を摂取することで、体調を整えやすくなります。
最後に、ストレス管理も意識しましょう。転職は大きな環境の変化を伴うため、知らず知らずのうちにストレスが溜まることがあります。趣味やリラックスできる時間を確保し、精神的なバランスを保つことが、転職後のパフォーマンス向上につながります。
入社後のキャリアプラン設計
新しい職場でのキャリアを成功させるためには、入社前にキャリアプランを明確にしておくことが重要です。転職を機に、自分が今後どのように成長していきたいのか、どのようなスキルを身につけたいのかを具体的に考えておくと、入社後の方向性が明確になります。
まず、短期的な目標を設定しましょう。例えば、入社後3カ月以内に業務を完全に習得する、特定のプロジェクトに関わる、新しいスキルを身につけるなどの具体的な目標を立てることで、仕事へのモチベーションが高まります。
また、長期的なキャリアビジョンを描くことも大切です。転職を通じて、どのようなポジションを目指すのか、将来的にどのような業務に携わりたいのかを考え、必要なスキルや経験をリストアップしておくと、計画的にキャリアを積み重ねられます。
【退職後に転職しない場合】退職が決まったらやるべきこと
退職後にすぐ転職しない場合、収入や社会保険の管理が重要になります。健康保険や年金の切り替え、失業保険の申請、税金関連の手続きは、適切なタイミングで進めないと不利益を被る可能性があるので注意しましょう。また、転職しない期間を有効活用するために、キャリアやライフプランを見直すことも大切です。
- 健康保険の切り替え手続き
- 年金の切り替え手続き
- 失業保険の申請手続き
- 税金(確定申告)関連の手続き
- 今後のキャリアやライフプランの整理
健康保険の切り替え手続き
退職すると、会社の健康保険から脱退することになり、新たな健康保険への加入が必要になります。健康保険の切り替えには、主に以下の3つの選択肢があります。
- 任意継続保険
- 国民健康保険
- 扶養に入る
任意継続保険を選ぶ場合、退職日から20日以内に手続きが必要です。保険料は全額自己負担となりますが、国民健康保険よりも安くなるケースがあります。国民健康保険への加入を希望する場合は、退職後14日以内に市区町村の役所で手続きを行います。扶養に入る場合は、扶養者の勤務先で手続きが必要です。
いずれの方法を選ぶにせよ、無保険の期間が生じないよう、早めに手続きを済ませることが重要です。万が一、無保険期間に病気や怪我をした場合、医療費が全額自己負担となってしまうため注意しましょう。
年金の切り替え手続き
退職すると、厚生年金から国民年金への切り替えが必要になります。会社員として働いていた間は厚生年金に加入していましたが、退職後に転職しない場合、国民年金に加入しなければなりません。手続きは、退職後14日以内に住民票のある市区町村の役所で行います。手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 退職証明書または離職票
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
また、保険料の支払いが負担になる場合は、免除制度や猶予制度の活用も検討しましょう。所得が一定額以下であれば、申請によって保険料の全額または一部が免除される場合があります。50歳未満であれば、失業中の特例として「国民年金保険料の納付猶予制度」を利用することも可能です。
年金の未納期間が続くと、将来の年金受給額に影響を及ぼすため、しっかりと手続きを進めることが重要です。
失業保険の申請手続き
退職後、一定の条件を満たせば、失業保険を受給できます。失業保険を受け取るためには、ハローワークでの手続きが必要となります。手続きの流れは以下の通りです。
- 離職票を受け取る
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 雇用保険説明会に参加する
- 7日間の待機期間を経て、給付開始
失業保険の受給資格があるかどうかは、過去2年間で12カ月以上雇用保険に加入していたかどうかで決まります(自己都合退職の場合)。給付額は退職前の給与を基に計算され、受給期間は年齢や勤続年数によって異なります。
また、失業保険を受給中は、定期的にハローワークで求職活動の実績を報告する必要があります。一定期間ごとに指定された回数の求職活動を行わなければ、給付がストップするため注意しましょう。
税金(確定申告)関連の手続き
退職後、転職しない場合は、所得税や住民税の支払いについても把握しておく必要があります。翌年に確定申告が必要になるケースがあるため、注意が必要です。
会社を退職した時点で、年末調整が受けられなくなるため、退職した年の翌年に確定申告を行う必要があることを理解しておきましょう。以下のような場合は確定申告が必須となります。
- 退職後に一時的な収入(副業やフリーランスの仕事)があった場合
- 退職金を受け取ったが、所得税が過払いになっている場合
- 医療費控除やふるさと納税の控除を受けたい場合
また、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職後も支払い義務があります。退職すると普通徴収に切り替わるため、自治体から送付される納付書を確認し、期限内に支払いましょう。
今後のキャリアやライフプランの整理
転職しない期間をどのように活用するかを考えることは、今後の人生設計において重要なポイントです。この期間をスキルアップや新たなキャリア構築の準備期間とすることで、将来的により良い仕事に就くチャンスを増やせます。
まず、これまでのキャリアを振り返ることから始めましょう。自身の強みや得意分野を再確認し、今後どのような方向に進みたいのかを整理します。ライフプランを見直すことも大切です。退職後の貯蓄や生活費の計画を立て、必要に応じて支出を見直します。転職を前提としない場合、副業やフリーランスとして働く選択肢も考えられます。
時間がある今だからこそ、自分にとって最適なキャリアやライフプランをじっくり検討し、納得のいく選択をすることが大切です。
退職が決まったらやるべきことに関するよくある質問
退職が決まったらやるべきことに関するよくある質問を見ていきましょう。
- 退職時に会社から嫌がらせを受けたら?
- 退職が決まったら活用したい支援制度は?
- 転職するか退職(独立)するか悩んだときの判断基準は?
- 退職時によくあるトラブルは?
- 退職時に有休消化できないときは?
- 退職時に契約書へサインを求められたら?
退職時に会社から嫌がらせを受けたら?
退職意思を伝えた後、会社側から嫌がらせを受けた場合は、退職代行サービスの利用がおすすめです。会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担を軽減できます。
また、証拠を残すことも重要です。上司や人事担当者との会話を録音したり、メールやチャットのスクリーンショットを保存したりすることで、客観的な証拠を確保できます。会社側の対応が違法である場合、労働基準監督署や弁護士へ相談することで法的措置を取ることも可能です。
関連記事:職場いじめよくでよくある事例と対処法を解説!困ったときの相談窓口も紹介します
退職が決まったら活用したい支援制度は?
退職後の生活を支えるために、国や自治体が提供する支援制度を活用すると、経済的な負担を軽減できます。以下のような制度があるため、状況に応じて申請を検討しましょう。
- 失業保険
- 職業訓練制度
- 国民健康保険・年金の減免制度
- 住宅確保給付金
これらの制度をうまく活用することで、退職後の負担を最小限に抑えつつ、次のステップへ進みやすくなります。
転職するか退職(独立)するか悩んだときの判断基準は?
退職後のキャリアを考える際、「転職するべきか、それとも独立すべきか」と悩む人は少なくありません。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあるため、自身の状況や価値観をもとに慎重に判断することが大切です。
【転職を選ぶべき場合】
- 安定した収入を求めている
- 組織の中でキャリアアップを目指したい
- 社会保険や福利厚生を重視している
【独立を選ぶべき場合】
- 自分のスキルや経験を活かして自由に働きたい
- 組織のルールに縛られず、自分のペースで仕事をしたい
- 収入の上限を決めずに挑戦したい
どちらを選ぶにせよ、リスクを最小限に抑えるために、事前の準備をしっかり行うことが重要です。転職するか退職(独立)するか悩んだときの判断基準については、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:転職か独立か判断に迷ったときの基準は?年齢別でポイントを紹介
退職時によくあるトラブルは?
退職時には、さまざまなトラブルが発生することがあります。例えば、以下のような問題です。
- 退職を引き止められる・退職時期が遅れる
- 退職届を受け取ってもらえない
- 退職時に有給休暇を消化できない
- 退職金を支払ってもらえない
- 退職意思を伝えるとボーナスが支給されなかった
- 退職時の契約書へサインを求められる
- 離職票・源泉徴収票などの書類を発行してくれない
- 退職理由を自己都合退職にさせられた
- 退職意思を伝えると嫌がらせにあう
退職時によくあるトラブルと対処法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:退職時によくあるトラブルと対処法!効率よく退職する方法を紹介
退職時に有休消化できないときは?
退職時に有休消化できないときは、有給消化できるように交渉・言い方を工夫する、買い取ってもらうなどの対処法があります。有給休暇は労働者の権利ですが、会社によっては引き継ぎが終わるまで認めない、会社が忙しいなどの理由で拒否されるケースも少なくありません。
しかし、法律上、退職時の有休消化は原則として認められています。会社が拒否する場合、退職代行サービスを利用することで、スムーズに有給休暇を取得しながら退職する方法もあります。退職時に有休消化できないときの対処法については、以下の記事をご確認ください。
関連記事:退職時に有給消化できない時の対処法は?有給の消化方法と違法について解説
退職時に契約書へサインを求められたら?
退職時に契約書へサインを求められたら、内容をしっかりと確認して、納得できる場合はサインしましょう。納得できない場合は、サインを拒否して構いません。一度サインしてしまうと、後から内容を変更するのは難しくなるため、少しでも不安を感じた場合は、即決せず慎重に対応することが大切です。
退職時に契約書へサインを求められたときの対応については、以下の記事をご確認ください。
関連記事:退職時に誓約書へのサインは拒否できる?効力や断り方について解説
まとめ
退職が決まったらやるべきことを時系列で紹介しました。退職手続きは思った以上にやることが多いです。退職手続きに不安を感じる人や、会社との関係性が悪く上手く手続きが進まない人は、退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行サービスを利用すれば、直接会社とやり取りすることなく、退職手続きを進められます。ストレスが軽減され、新しいスタートを切る準備に専念できます。退職に関する悩みや不安がある人は、ぜひ退職代行ほっとラインへご相談ください。

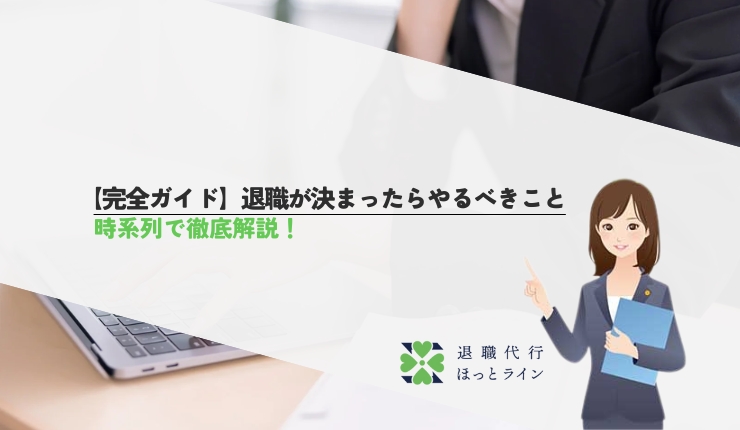



コメントを残す